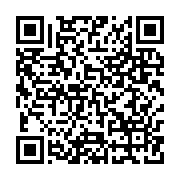|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:11 総数:156352 |
【市P連】母と女性教職員の会 全国集会(3)
2日目は、分科会が開催されました。
全15分科会の中から、参加希望の分科会が選べます。 それぞれの分科会では、問題提起の発表があり、それについての様々な討議が行われ、教員と保護者という立場の違う人々が一緒に学びました。 【分科会一覧】 1. 乳幼児期から学童期の子育て 2. 小学生 3. 中・高生 4. いじめ・不登校 5. 性と生 6. 障害児の共生・共学 7. ジェンダー平等 8. 健康の問題 9. 食の問題 10. これからの教育 11. 社会保障 12. 平和 13. 環境 14. 女性労働 15. 母と女性教職員が手を結ぶ運動 2日間の集会に参加して思ったことは、「先生方はよく勉強していらっしゃるな」ということでした。 日々の多忙な業務をこなしながら、いろいろな研修会に参加されていて、常に新しいことに取り組む意欲を持っていらっしゃることが、討議を聞いていて感じられました。 最近、大津市のいじめ問題に関連して、先生の資質について議論されているのを、目にすることがよくあります。 一部の心ない教師がクローズアップされて、あたかも教師全体がそうであるかのような議論になることに対しては、注意して見ていかなければならないと思います。 少なくとも、我々のまわりにいる、多くの先生方は、教育に志を持って取り組まれている人がほとんどです。 無用な誤解を生まないためにも、学校はもっと開かれるべきですね。 学校の現状や、今取り組んでいること、こんな生徒を育てたいという方針などを、どんどん発信してほしいと思います。 私たち保護者も、学校に任せきりにしないで、子供を通して、学校を知る努力を忘れずにいたいですね。  【市P連】母と女性教職員の会 全国集会(2)
●8/1 全体会 その2
「原発災害と復興へのビジョン」と題して、鈴木浩先生(福島大学名誉教授、明治大学客員教授、元福島県復興ビジョン検討委員会座長)の講演がありました。 1. 東日本大震災とその時代的特質 2. 復興に向けての現状と課題 3. 復興政策に関わるガバナンスの問題点と課題 4. 復興へのビジョン 5. 浪江町復興計画策定に関わって 6. あらためて地域再生に向けて 今回の大震災は、日本が抱える様々な問題が浮き彫りになった災害でした。 疲弊する地方経済、機能しない政治、社会保障への不安など、今までは漠然とした不安として感じていたことが、現実として突きつけられました。 講演の中で、それぞれの問題の現状と課題についてのお話しがありました。 いろいろな人たちがいろいろな提言をしているのに、どうしてすぐに実行できないのかと、もどかしい思いを抱えている様子がよくわかりました。 こうした社会問題に関する話題は、難しくてわからないからと敬遠しがちですが、私たち大人は、もっと自分自身のこととして受け止めて、考えていく必要があるなと思いました。 このまま問題を先送りしていては、結局子供たちにそのツケを押しつけることになってしまいます。 まずは、関心を持って、いろいろな人の考えや意見を聞くことから始めてみようと思います。  【市P連】母と女性教職員の会 全国集会(1)
8/1(水)、2(木)日本教職員組合主催の「母と女性教職員の会 全国集会」が東京で開催されました。
小牧からは、小牧市教員組合の女性部長の先生と、市P連母親委員長の2名で参加しました。 愛知県下の各ブロックごとに、女性の先生と母親代表の方々が集合し、移動の新幹線の車中は、1両の3分の2ほどの大人数で、にぎやかな道中となりました。 2日間にわたるプログラムは、1日目に全体会、2日目に分科会となっていて、盛りだくさんの内容でした。 ●8/1 全体会 さすが全国集会というだけあって、会場が満員御礼になるほど、たくさんの人々が集まりました。 開会行事では、昨年の東日本大震災を受けて、被災地からの報告がありました。 時間が経つにつれ、被災地の現状の報道が少なくなっています。 今回の報告は、日々の生活に追われる中で、ついつい被災地に心を寄せる余裕がなくなっていることに気づかせてくれました。 まだ多くの行方不明者がいて、たくさんの子供たちが仮設住宅に暮らし、不自由な生活を強いられています。 また、原子力発電所の事故のために、避難を余儀なくされ、除染がなかなか進まない中、家に閉じこもりがちな子供たちがたくさんいます。 先が見えない生活は、さぞ不安なことでしょう。 スライドで紹介された子供たちの笑顔を見ていると、せつなくて、やり切れない気持ちでいっぱいになりました。 私たちに何ができるのだろうか・・・考えても、簡単に答えが見つかる問題ではありません。 報告を聞く中で、強く思ったことは「忘れてはいけない」ということでした。 私たちが直接手助けできることは、何もないかもしれません。 しかし、いつも心の中に被災地のことを思う気持ち、そこに生きる子供たちを思う気持ちを持ち続けることはできます。 そして、家庭で、学校で、地域で、被災地のことを話題にすることで、ひとりでも多くの人々の心の中に「想い」を持ち続けてもらえるようなきっかけを作ることはできます。 保護者の皆さん、ぜひお子さんと、ご家族と、地震や津波のこと、原発や放射能のこと、いろいろな話をしてみませんか?  【市P連】尾張小中学校PTA連絡協議会 母親代表研修会(2)
●飛島村立小中一貫教育校 飛島学園
公立学校でありながら、小中一貫校として設立された飛島学園の施設見学をさせていただきました。 通常の学年構成とは違い、小1〜4年生を「初等部」、小5〜中1年生を「中等部」、中2〜3年生を「高等部」という3部構成にし、教室はユニット型になっていました。 低学年は、壁で教室を囲うのではなく、間仕切りで区切り、廊下にあたる部分は多目的スペースとして活用されているとのことでした。 小中一貫校の特徴でもある、学年を超えた活動を行うために、学校施設も様々な工夫がされており、子供たちの楽しそうな歓声が聞こえてきそうでした。(当日は夏休みのため、残念ながら子供はいませんでした) 他にも、体育館やプールなどは、隣接する村営の施設を利用しているため、地域の方々との交流も活発に行われているそうです。 村に唯一の学校として、学校と地域の連携が盛んに行われていて、地域ぐるみで子供を育てようという思いが伝わってきました。 ●情報交換会 学校施設の見学後、情報交換会も実施されました。 尾張地区の23郡市の母親代表がグループに分かれて、各地のPTA活動の特色や課題などを話し合いました。 そこで出ていた話題は、市P連と同様、「役員選出の難しさ」でした。 地域により選出方法の差はありますが、役員がすんなり決まらず困っている、というのは、どこでも同じのようです。 どうしても敬遠されがちなPTA役員ですが、現役員が楽しく活動をしていけば、きっとPTA活動への拒否反応もやわらいでいくでしょうから、我々、現母親代表の使命として、楽しんで活動していきましょう、という意見に勇気をもらいました。 また、学校との関わり方についても、悩みを抱えていらっしゃる方が多く、話題になりました。 P(保護者)T(先生)Aなのだから、先生方も協力してほしいという意見も出ていました。 通常、学校側のPTA担当は教頭先生がやられる場合がほとんどですが、それ以外のとくに若い先生方に、もっと関心を持ってもらい積極的に関わってほしい、ということです。 学校とPTAが、もっと情報や意見の交換をして、よりよい関係を築いていければいいですね。 暑い中でしたが、このように他地区の母親代表の方々と情報交換できたのは、とてもよかったです。 市P連の母親委員会でも、機会をとらえて、いろいろな情報提供をしていきたいと思います。   【市P連】尾張小中学校PTA連絡協議会 母親代表研修会(1)
7/24(火)尾張小中学校PTA連絡協議会の母親代表研修会が開催され、参加しました。
今年度は、事務局である飛島村立飛島学園への見学と、飛島村コンテナふ頭の見学、情報交換会を実施しました。 ●飛島コンテナふ頭 このコンテナふ頭では、貨物の積み下ろしが自動化されており、クレーンやトレーラーなどが遠隔操作で制御されている日本で唯一のコンテナターミナルふ頭だそうです。 設備の自動化でコストを下げ、また日本の中心にあるという立地の良さも活かし、世界中から多くの貨物が運ばれてきています。 2008年のリーマンショック時は、取り扱い貨物量が減少しましたが、その後順調に回復しているとのお話しでしたが、近年は予想どおりの貨物量の増加は見られず、この原因として、製造業が海外に生産拠点を移していることも影響している、という説明を受けました。 物流からも、日本の製造業の現状がわかるのですね。 遠隔操作室も見学させていただきました。 他のターミナルふ頭では、大きなクレーンの上部に操作室があり、オペレーターの方はその中で作業をされるのですが、こちらでは管理棟という建物の中での作業になるため、猛暑や極寒、深夜などの作業時の負担がずいぶん軽減されていました。   【市P連】情報交換会のまとめ
6/29(金)の情報交換会では、「各校のPTA役員決めについて」というテーマで、以下のグループに分かれて、情報交換を行いました。
グループ構成 A:篠岡小、光ヶ丘小、味岡小、本庄小 B:陶小、大城小、桃ヶ丘小 C:米野小、小牧小、小牧南小 D:小木小、三ツ渕小、北里小 E:村中小、一色小、小牧原小 F:応時中、味岡中、岩崎中 G:光ヶ丘中、篠岡中、桃陵中 H:小牧中、北里中、小牧西中 どこの学校でも、毎年苦労されるのが「役員決め」です。 この情報交換会では、他校の役員選考の方法を聞いて、自分の学校でも活かせないかと、皆さん真剣にグループディスカッションをされていました。 グループでの情報交換の後、全体で情報の共有を図るために、グループごとに発表を行いました。 その中で出た内容をご紹介します。 ● PTA会長について いわゆる「一本釣り」がほとんどのようです。基本的には、副会長を1年経験して、次年度に会長へ、という流れになっています。 2年連続での役になることもあり、平日に休みが取りづらいということで、一般の会社員の方は敬遠される場合が多く、最近は公務員の方にお願いする学校が増えています。 ●母親代表について 執行部や総務の中から選ばれることが多いようです。 会長同様、複数年の参加になるため、子供の学年も重要です。 ある学校では、総務役員を地区の輪番制にしていて、当番に当たっている地区から総務委員を選出し、その中から母親代表を決める、というやり方をしているとのことです。他地区の時はいいですが、自分の地区が当たる時は、地区役員決めが大変そうです。 また母代は、専門委員長を兼任することはあまりなく、執行部や総務のまとめ役という位置づけになっている学校がほとんどでした。しかし、中には母代が専門委員長を兼任するという学校もあり、その場合は母代の負担が大きいので、周りから「かわいそう〜」の声が上がっていました。 ● 役員選考委員会について 多くの学校で、役員選考委員会が組織されていました。 その中で次年度の役員候補を推薦してもらい、順番にアタックしていくという方法を取っているようです。 しかし、この選考委員会が形だけになってしまっている学校も多く、実際はなかなか人選が難しいようです。 それに、アタックする担当は会長や母代なので、結局会長や母代に負担がかかることに変わりはありません。 ● 地域の方の協力について 学校の規模や立地にもよりますが、地域の生き字引のような世話役の方がいらっしゃる学校は、とても頼りになるということでした。 地域コーディネーターさんも、地元の情報を持っておられるので、力を貸して下さることもあるようです。 あとは、子供関連のネットワーク(習い事やスポーツのクラブなど)を駆使して、家族総出で適任者を探す、という意見もありました。 ● 学校の協力について 校長先生や教頭先生が、ご自身の教え子を紹介して下さるケースもあるようです。うまくタイミングが合えば、パッと決まることもあるようです。 ● 輪番制について とくに中学校の場合ですが、いくつかの小学校区が集まって、1つの中学校区になっています。ですから、その小学校区で順番に会長や母代を回していく、というやり方もあるようです。 これは、各小学校区から来ている生徒数に違いがある場合もあり、少ない生徒数の校区では成り手がいなくて大変だという声が出ていました。 そのため、今では輪番制が成り立っていない学校もあります。 ● 新執行部、総務の決め方について 執行部や総務の役員さんを決めるのは、だいたい母代が担当するようです。 この決め方にも2パターンあります。 まず1つ目のパターンは、前任の母代が次の役員を決めて卒業する形。これだと、新母代は最初は楽ですが、一緒にやる役員さんたちは知らない人ばかりになってしまう可能性もあり、ちょっとやりにくい思いをすることもあります。 次に2つ目のパターンは、新母代が新年度の役員を決める形。こちらは、母代さんが自分と一緒にやってくれそうな人を探せるので、運営がやりやすいですが、新年度が始まる前からかなり動かなければなりません。 どちらがいいのか、一概には言えませんが、どちらも一長一短です。 このように、どこの学校でも悩みのタネの「役員決め」ですが、イヤイヤ引き受けてしまったけど、1年過ぎるころには「楽しかったわ〜やってよかったわ〜」とおっしゃっていただける方がほとんどです。 新しい友達もたくさんできますし、いろいろなお得情報をゲットすることもできますよ。 それに、多くの学校では役員の負担が少しでも軽くなるように、いろいろな工夫がされています。 やれる時だけお手伝いしてもらう形での活動もあります。 PTAは、子供が学校へ通っている間しか参加できない活動です。 保護者の皆さんには、ぜひ一度は参加していただいて、我が子の学校のことや先生のことをよく知っていただきたいなと思います。 そうすれば、もっともっと学校や先生が好きになれますよ。保護者の方が学校や先生を好きになれば、子供たちもきっと好きになります。 今しかないこの時期を、PTAで楽しく過ごしてみませんか? 役員はムリ!ということであっても、学校ではいろいろなPTA行事が行われています。皆さんのご参加をお待ちしています! ふれあいの森の可憐な「ネジバナ」@趣味'sブログ   【市P連】懇親会
6/29(金)情報交換の後、小牧市小中学校PTA連絡協議会の懇親会が、同会場で開催されました。
PTA会長、母親代表の他に、各校の校長先生にもご参加いただき、盛大に開催することができました。 日ごろ、なかなかお話する機会のない、他校の方々や先生方と、和やかで楽しい雰囲気の中、貴重な情報交換ができ、有意義な時間になりました。 また、教育委員会から江口教育長をはじめ、多数のご来賓の皆様にもご臨席いただきました。ありがとうございました。 【ご来賓の皆様】 小牧市教育委員会教育長 江口 光広様 小牧市教育委員会教育部長 中嶋 隆様 小牧市教育委員会教育部次長 舟橋 泉様 小牧市教育委員会生涯学習課長 高木 大作様 江口教育長のごあいさつの中で、印象に残ったお話しをご紹介したいと思います。 ● 仕事柄、小牧の全小中学校の授業視察に行きます。また、他県や他市の学校の視察にも行きます。そこで感じるのは「小牧の授業レベルの高さ」です。これは、日頃の教職員がしっかり取り組んでいる成果だと思っていますし、教育長として小牧の教育のすばらしさを自負しています。 ● 学校はとかく閉ざされた世界になりがちです。PTAの皆さんには、学校と地域をつなぐ架け橋になってほしいのです。 子供が卒業すると、学校との関わりがなくなってしまうのが普通です。 しかし、子供の育ちには、地域の支えが必要です。なぜなら、子供は地域の中で育つからです。 教育長のお話しは、そのことを改めて思い出させて下さいました。 我々PTAが、地域の方々に、再び、学校への興味や関心を持ってもらえるような活動をしていけるといいですね。 また、市P連会長である、我が小牧中PTA会長の大野会長も、檀上でごあいさつをされました。 大野会長からは、次のようなお話しがありました。 ● 各校のホームページをチェックするのが日課です。ホームページを見ると、それぞれに、いろいろな取り組みをされていることがよくわかります。情報発信は大切ですね。 小牧中のPTAの部屋も、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。 多くの皆さんにご覧いただいていることに、会長、母代ともに、深く感謝しています。ありがとうございました。 これからも、活動の様子がよくわかるホームページを目指してがんばっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。    【市P連】情報交換会
6/29(金)小牧市小中学校PTA連絡協議会の情報交換会が、小牧駅上の小牧コミュニティーホールにて開催されました。
市内小中学校25校の全PTA会長、母親代表の皆さんにお集まりいただき、各校のPTA役員の選考方法について情報交換をしました。 どこのPTAでも、役員選考は、最大に悩みのタネです。 そこで、他校ではどのように選考を行っているかの情報交換をして、自校の役員選考の参考にしてもらおうという趣旨です。 グループに分かれ、ざっくばらんに意見交換をしていただいた後、グループごとに出た意見を発表して、情報の共有を図りました。 いろいろな意見が出ましたので、後日そのまとめの記事をアップしたいと思います。   【市P連】 母親委員会研修会
6/19(火) 市P連 第1回母親委員会研修会が開催されました。
いわゆる社会見学で、市内小中学校25校の母親代表の皆さんが参加して下さいました。 台風が接近する中、天候悪化が心配されましたが、皆さんのご協力のおかげで、無事に全日程を終了することができました。 ありがとうございました。 途中、各学校の緊急メールの配信状況をみんなで確認し合って、「うちの学校はまだ何もメールが来ないよ〜」という母代さんもいらっしゃったので、全市で一律ではなく各校によってメール対応が違うことなどがよくわかり、そういう意味でも興味深い情報交換ができました。 【本日の訪問先】 ●中日新聞本社 新聞ができるまでには、様々な人々の仕事があり、地域によって記事の内容を変えていることや、締切ギリギリまで新しい記事の差し替えや編集が行われていることがわかりました。 見学記念版の新聞を作成していただき、感激しました。 ※写真1、2枚目 ●名古屋市科学館 話題のプラネタリウム鑑賞をしてきました。 リクライニングするイスに座り、ゆったりした気分で、学芸員の方の生解説を聴きながら、春から夏の夜空の様子について教えていただきました。 6/21から数日間、夜空に国際宇宙ステーションが流れ星のように飛ぶ様子が観察できるそうです。詳しくは、名古屋市科学館のホームページをご覧下さい。 ※写真3枚目    6/13 愛知県小中学校PTA連絡協議会 総会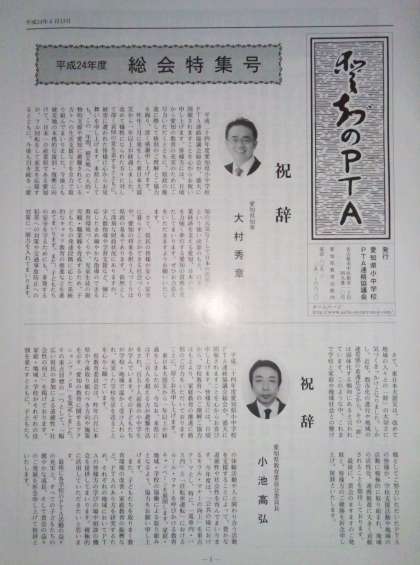 本校からは、大野PTA会長と玉置校長先生が出席されました。(大野PTA会長は県でも要職に 6/13) 大野会長に、総会の様子を伺ったところ、来賓や新会長のごあいさつの中で印象に残ったことを教えていただきましたので、ご紹介します。 −−−−− 来賓として、今年は大村知事が来られました。 たいへん忙しい方で、私(大野会長)は、玄関から受付までの案内係でしたが、センチュリー(公用車)から電話をしながら降りて来られて、ビックリしました。 来賓のご挨拶では、教育は地域を作る源であり、未来を作ることだから、特に力をいれて行くと語られ、教育懇談会を開催するなど積極的に取り組んでいるとのことでした。 (教育懇談会については、最近ニュースでも取り上げられていますね) また、新会長のご挨拶では、PTAは大人が学ぶ場であると言われました。 その環境でより良い子供が育まれるというお話でした。 −−−−− 「大人が学ぶ場」という言葉に、わが校の校長先生が「新しいことを始めるよ戦略会議」でおっしゃた内容がだぶり、「親子で学ぶ夜の小牧中学校」企画が、まさにそれだ!という思いで、これからのPTA活動がますます楽しみになりました。 「学ぶこと」は、子供だけの専売特許ではありません。 私たち大人が、まずは「学ぶこと」を楽しみましょう! 尾P連のおはなし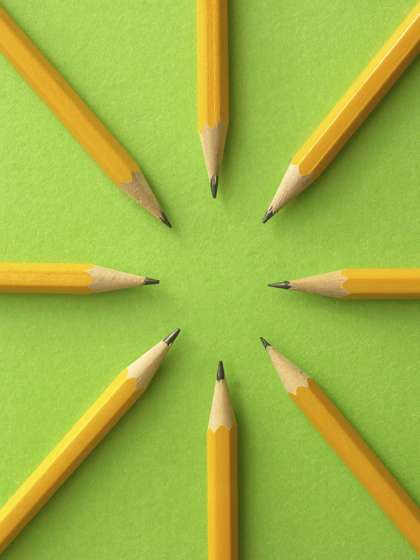 こちらも、市P連と同じように、略して「尾P連」と呼ばれています。 愛知県全体のPTA組織は、「愛知県小中学校PTA連絡協議会」といいます。こちらは略して「県P連」と呼ばれます。 その下に「尾張小中学校PTA連絡協議会」「三河小中学校PTA連絡協議会」「名古屋市小中学校PTA連絡協議会」という3つの組織があります。 小牧市は「尾張小中学校PTA連絡協議会」に所属しており、尾P連は、尾張地区の23市郡が所属する組織です。 こちらも、市P連同様、持ち回りで役員が決められており、今年度は会計監査が小牧市の担当となり、大野会長が就任されたというわけです。 もうひとつ「尾張教育研究会」についても、簡単にご説明します。 「教育研究会」は先生が所属する団体で、教員の技量向上のための研修や新学習指導要領に対応した授業研究などを行っているそうです。 こちらもPTAと同様に、県内に3つの組織(尾張、三河、名古屋)があり、小牧市は「尾張教育研究会」に所属しています。 尾P連から教育研究会へ研究費用の助成を行っている関係で、この後援会の総会も同時に開催しているということでした。 こうしてみると、各小中学校のPTAが一番小さい単位(単位PTA、略して単Pと呼びます)ですが、それが市になり、地区になり、県になり、というように、ずっとつながっていることがわかります。 他地区の情報なども得る機会があれば、ご紹介していきたいと思います。 6/7 尾張小中学校PTA連絡協議会 総会
6/7 愛知県教育会館にて、「尾張小中学校PTA連絡協議会」「尾張教育研究会後援会」総会が開催されました。
市P連を代表して、副会長の安藤校長先生(北里中)、齋藤母親委員長が出席しました。 ●議事 平成23年度の事業報告、決算報告 平成24年度の役員承認、事業計画、予算 今年度、市P連会長である大野会長は、尾P連の会計監査に承認されました。 前会長のごあいさつの中で、昨年度を振り返ってのお話しがありましたので、少しご紹介したいと思います。 昨年3月の東日本大震災の後、学校の役割が再認識されました。 災害時に避難所になる学校は、地域の中で重要な存在です。 これからは、学校を中心とした地域づくりを進めていく必要があります。PTAは、学校と地域をつなぐ役割を担っていると思います。ぜひPTAの皆さんが学校と地域の潤滑油になって下さい。 また、副会長である山田校長会長(常滑市)からのごあいさつで興味深いお話しがありましたので、こちらもご紹介します。 全国学力テストについて、当初は全校一斉実施でしたが、最近は抽出校のみの実施になりました。 愛知県は抽出率がとても低いです。 抽出率は、県内で学力差がある場合は高くなり、逆に学力差があまりなければ低くなります。 愛知県の抽出率が低いということは、県内の学力差があまりないということです。 これは、先生方が日頃から授業研究などに取り組まれ、実践していただいている成果だと思います。 これからも、より一層の成果が出るように、また学校と地域をつなぐ潤滑油となるように、私たちPTAも協力していきたいと思います。  5/25 第1回市P連母親委員会
母親委員会役員会に引き続き、第1回市P連母親委員会が開催されました。
市内小中学校25校から、母親代表の方々にお集まりいただきました。 お忙しい中、全員参加していただき、ありがとうございました。 (人数が多いため、出席者の一覧は省略させていただきます) ●協議事項 1. 小牧市教員組合から、行事への参加依頼 例年通り、今年度も9/8(土)に「小牧父母と教師のつどい」として、午前に「第40回小牧母と女性教師の会」、午後に「教育対話集会」が開催されます。 各学校ごとに動員人数が決められていますので、PTA役員さんを中心に、多くの保護者の皆さんのご参加をお願いしたい、とのことでした。 6月ごろ、学校を通じて案内が配布されますので、ご協力をお願いします。 2. 第1回母親委員会研修会について 6/19(火)に第1回の研修会を予定しています。 予約の都合上、当日キャンセルができませんので、各学校で、不測の事態の場合は代理の方を立てていただくようにお願いします。 3. 情報交換会・懇親会について 6/29(金)に「市P連情報交換会・懇親会」を予定しています。 情報交換会には、各学校のPTA会長、母親代表の方々に参加していただきます。 PTAの悩みのタネでもある、役員選考についてや運営方法についてなどの情報交換を考えていますので、それぞれの学校の現状や今後取り組みたいことなど、自由に意見交換ができればと思いますので、よろしくお願いします。 4. 今後の母親委員会・研修会について 現時点で決まっている日程や内容について、お知らせしました。 初回の母親委員会ということもあり、やや緊張の面持ちの方も多数みえましたが、例年、回を重ねるごとに打ち解けて、他校の情報を得る貴重な機会になっていきます。 委員長のあいさつでも少しお話させていただきましたが、母代さんは各校の活動では中心になりますので、たいへんなことも多いです。 ですから、市P連の母親委員会では、気軽に他校の母代さんとの交流を深めていただき、楽しく過ごしていただきたいと思っています。 そんなの中で、自校のPTA活動に活かせるヒントを得ていただければ、とてもうれしいなという思いで、役員一同がんばりますので、1年間よろしくお願いします。   5/25 第2回市P連母親委員会役員会
5/25(金) パークアリーナ会議室にて、第2回市P連母親委員会役員会が開催されました。
週末に開催される「産業フェスタ」の準備で、まわりがたいへん賑わっていました。 ●出席者(5名) 齋藤母親委員長(小牧中母代)、関戸母親副委員長(応時中母代) 仲母親副委員長(小牧小母代)、山井保健理事(光ヶ丘小母代) 小島事務局担当(小牧中教頭) ●協議事項 1. 小牧市教員組合からの依頼について この後に開催される「第1回母親委員会」の冒頭で、組合行事等への協力依頼のために、小牧市教員組合から2名の先生がお見えになる、とのことでした。 2. 第1回母親委員会について 前回(第1回母親委員会役員会)は、まだ保留になっていた案件などで、日程が決まったものや内容がわかったものなどの確認をしました。 ●その他 今年度は、各学校の母親代表の方々と、より交流を深めたいということもあり、事務局に携帯用の名札を作成していただきました。 今後の委員会や研修会で活用させていただきます。  「見守る」  学校側ではできる限りの対策をしていくが、それだけでは不十分なところがどうしても出てきます。 そういう部分をカバーするには、PTAを始め地域の方々の多くの手助けが必要です。 例えば、子供たちの登下校の時間にちょっと通学路を通ってみる、というような「見守り」をぜひお願いしたい、ということでした。 ボランティアというと、ちょっと構えてしまうかもしれませんね。 しかし、それほど大げさにとらえなくてもいいと思うのです。 私たち保護者側も、子供たちの安全について、親としてできることは何か?ということを、「見守る」をキーワードに、少し気にとめて考えてみませんか? 5/9 第1回市P連母親委員会役員会
第1回市P連役員会のあと、同じく小牧中応接室で、第1回母親委員会役員会が開催されました。
母代の皆さんには、長時間に渡りご参加いただき、ありがとうございました。 ● 出席者(5名) 齋藤母親委員長(小牧中母代)、関戸母親副委員長(応時中母代) 仲母親副委員長(小牧小母代)、山井保健理事(光ヶ丘小母代) 小島事務局担当(小牧中教頭) ● 協議事項 1. 第1回母親委員会について 5/25に開催される「第1回母親委員会」の協議事項や、当日の役割分担について話し合いました。 2. 第1回母親委員会研修会について 6/19に開催予定の「第1回母親委員会研修会」の行程についての説明がありました。 3. その他の研修会の役割分担について その他に、年間3回開催予定の研修会の内容と、役割分担について話し合いました。 今日が今年度最初の役員会ということで、よくわかんないけど、なんか大変そう・・・という感想を持った方もいらっしゃいましたが、千里の道も一歩から。ひとつずつ見ていけば、実はそれほど過酷なわけではなくて、実際にやってみると意外となんとかなるものです。 皆さんと力を合わせて、楽しい1年が過ごせそうです。1年間、よろしくお願いします。  5/9 第1回市P連役員会 皆さんお忙しい中ですが、全員出席していただき、ありがとうございました。 ●出席者(11名) 大野会長(小牧中P長)、嶺岡副会長(応時中P長)、安藤副会長(北里中校長) 添田理事(篠岡小P長)、玉置庶務会計(小牧中校長) 大島会計監査(小木小P長) 齋藤母親委員長(小牧中母代)、関戸母親副委員長(応時中母代) 仲母親副委員長(小牧小母代)、山井保健理事(光ヶ丘小母代) 小島事務局担当(小牧中教頭) ●協議事項 1. H24年度市P連事業開催計画 おもに1学期中に予定されている行事について協議しました。 2. 外部連携団体の事業への参加について 現在までに派遣依頼のあった行事について説明がありました。 大野会長のあいさつでは、先日市内で発生した交通事故に関連して、各小中学校で通学路の見直しが進められていること、我々は被害者にも加害者にもなりうることを肝に銘じて日々を過ごしていきたい、というお話がありました。 とくに自動車を運転される方々は、有名な標語「注意一秒、ケガ一生」を忘れずに、十分に気をつけて運転しましょう。 市P連のお話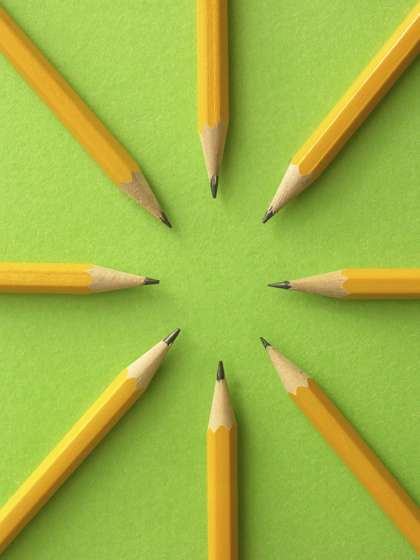 正式には「小牧市小中学校PTA連絡協議会」という名称で、略して「市P連」と呼ばれています。 小牧市には、市立小学校が16校、市立中学校が9校の合わせて25校があります。 その全25校が集まって、市P連が構成されています。 市P連の主な活動は、市内の学校のPTA間の連携をはかり、様々な情報交換をすることです。 市P連には、各学校の「PTA会長」「母親代表」「校長」が会員として登録されており、毎年持ち回りで役員を決めています。 市P連の会長には、中学校のPTA会長があたることになっており、9年に一度、その大役が回ってくることになりますが、小牧中学校は今年がその「当たり年」になっています。 また市P連の中に「母親委員会」が設置されており、各学校の母親代表は母親委員会に所属します。 市P連の会長があたる年は、その学校の母親代表が「母親委員長」を務めることになっているため、今年は母代にとっても「当たり年」になります。 さらに、市P連会長、母親委員長に当たる時、その所属校が「事務局」となります。そのため校長先生は庶務担当の役員となるのです。事務局としての実務は、ほぼ教頭先生が担うことになりますので、学校側もとっても大変です。 追い打ちをかけるように、今年度は本校の大野会長においては、愛日P連の副会長、さらに尾張P連の監査役とたくさんの役に任命されているため、大忙しの1年になります。 それら以外にも、行政(市役所関連)からの依頼があった各種協議会に委員として派遣されます。 ということで、今年は例年以上に市P連への関わりが深い1年になります。 このホームページでも、折にふれて、その活動をご紹介していきたいと思います。 4/25 市P連総会 |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
||||||||||