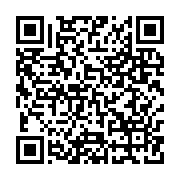|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:10 総数:156329 |
【市P連】「子育て読み物」コーナーに関するお知らせ 講師の尾花先生のご指摘により、一部加筆修正しました。 講演会に参加されていない保護者の皆さんに、よりわかりやすくなるように、表現を工夫していただいたり、説明を加えていただきました。 尾花先生、ありがとうございました。 ●【市P連】県P連合同研修会 講演会(1) ●【市P連】県P連合同研修会 講演会(2) ●【市P連】県P連合同研修会 講演会(6) 時代は、ますますデジタル化していきます。 私たち保護者も「わからないから」とあきらめず、学校任せにせず、子供と一緒に学びながら、子供たちを「賢い安全な使い手」に導いていきましょう! 【市P連】県P連合同研修会 講演会(8) 『最終回』 配布資料を基に、再構成してまとめてあります。 【演題&講師紹介】 「ケータイ&スマートフォン、これくらいは知っておこう!」 〜デジタル社会を健やかに生きる子供を育むために〜 尾花 紀子氏 ※Webサイトはこちら ※尾花氏監修 EMA 「ケータイ・インターネットの歩き方 〜子どもが安心・安全につかうために〜」 ● 小学校と保護者が取り組みたいこと <1.厳しく規制するより「ルールを守りながら使う」習慣付けを!> (1) 「ルールを守れば自由に使える」というゴールへ、ステップを踏みながら徐々に導く (2) ルールとフィルタリング、子供の身の丈に合わせてサイズ調整するのが保護者の役割 <2.会話の多い家庭と気軽に相談できる親子関係を!> (3) 共有のパソコンやケータイで「会話をしながら一緒に体験する」からスタート 最初の試用期間として、保護者の管理のもとに子供専用の貸出ケータイを与えるのがおすすめ (4) ネットに関する話題や報道を見聞きした時には、親子で会話をしながら考える (5) ルールやフィルタリングが窮屈になるたびに「相談→適切な対応」で上記(2)を実行 <3.それぞれの「家庭のルール」情報をみんなで共有する工夫を!> (6) 「家庭ごとにルールがあること」「お互いのルールを尊重すること」を学ぶことが大切 (7) ネットワークで友達みんながつながっているのだから「我が家はやらない」はダメ ● 中学生のために学校と家庭が意識しておきたいこと <1.むやみに強制せず、執拗に叱らず、考えて行動できるように導く> (1) 聞く耳と心を持ち、内緒の行動に走らせない(相談されない大人にならない)努力を! (2) 見えない危険ゾーンに向かわせない最善策は「思春期の心情を理解し、追い込まない」こと (3) 問題が生じた際は、一方的に叱って終わらせず、子供の気持ちと向き合い「考えさせる」 <2.PCもケータイも同じインターネット、公開した情報は戻らない> (4) 個人情報も、誹謗中傷も、犯罪予告も「取り返しのつかない」ことを理解・納得させる (5) 発信する側の責任と、相手・無数の読み手・状況への配慮をしっかりと意識させる <3.学校や家庭で考えたい「コミュニケーションスキルの向上」> (6) パソコン&ケータイ所有の有無に左右されないコミュニケーションを心がけるように促す (7) 洞察力を身に付けさせ、ネット上の情報の安全性や信憑性を判断する力を養う 今後もデジタル化はさらに進み、ケータイ・スマホ・インターネットは生活にかかせないツールになります。 小中学生の保護者の皆さんには、今回の講演の内容を参考にしていただき、ぜひお子さんとたくさん会話をしながら、ともに考えるきっかけにしていただけるといいなと思います。 【市P連】県P連合同研修会 講演会(7) 配布資料を基に、再構成してまとめてあります。 【演題&講師紹介】 「ケータイ&スマートフォン、これくらいは知っておこう!」 〜デジタル社会を健やかに生きる子供を育むために〜 尾花 紀子氏 ※Webサイトはこちら ※尾花氏監修 EMA 「ケータイ・インターネットの歩き方 〜子どもが安心・安全につかうために〜」 ● 大人は模範となる使い方をしましょう こんな大人をよく見かけませんか? 食事中でも、移動中でも、四六時中、ケータイやスマホを操作して、メールやWebをチェックしている大人 電車やバスの中でもゲームに夢中、優先席に座り、前にお年寄りが立っても知らんぷりでケータイを操作している大人 <使い方のマナーやモラルのお手本は、身近な大人> 「ケータイばかり触ってないで・・・」と叱る側が、目の前でずっと使っていては、子供たちは言われてることに「矛盾」や「大人の勝手」を感じます。 身近な大人やメディア等から入ってくる使い方が、子供の基準になるということをお忘れなく! <まずは大人が正しい使い方を> 子供に正しく使ってほしければ、まずは大人がきちんと使いましょう。 子供たちの目に飛び込んでくる、周囲のマナー違反やモラル違反は、記憶に新しいうちに「ああいう使い方はダメだよね」と会話をしましょう。 子どもは身近な大人を見ながら育つものです。 それであれば、普段の規範意識を育てるのは、身近な大人の役割ですね。 ルールやモラルを守って使う保護者が、賢く使える子供を育てるのです。 ●「リスク」と「メリット」を子供とともに考える インターネットが、良い人にとってはすばらしく便利な道具である(メリット)ということは、悪意を持つ人にとってはなおさら”悪事を働くのに”便利で都合のいい道具である(リスク)ということを理解しましょう。 「他人に迷惑をかけない子」「他人に不快な思いをさせない子」に育てるために、自ら手本となるように心がけながら、子供の言動にしっかり向き合い、たくさん会話をしましょう! 【市P連】県P連合同研修会 講演会(6) 配布資料を基に、再構成してまとめてあります。 【演題&講師紹介】 「ケータイ&スマートフォン、これくらいは知っておこう!」 〜デジタル社会を健やかに生きる子供を育むために〜 尾花 紀子氏 ※Webサイトはこちら ※尾花氏監修 EMA 「ケータイ・インターネットの歩き方 〜子どもが安心・安全につかうために〜」 ● パスワードロック 万が一、ケータイやスマホを落としてしまったり、盗難にあったりした場合、本体内の大切な個人情報を守るために、パスワードロックをかけましょう、という話をお聞きになったことがあると思います。 たしかに、パスワードロックをかけておけば、簡単に本体内の情報を見られることはありません。 しかし、万が一、事故などにあって意識がはっきりしない場合、救急隊員は持ち物の中から、身元が特定できるものを探します。 ケータイがあれば、発信履歴などから連絡を取ることがあります。 大人のように、身分証明書などを持ち歩かない子供の場合は、本体にパスワードロックをかけることは避けましょう。 紛失や盗難の際に個人情報を守るためなら、電話帳やメールフォルダへの機能別ロックをかけるようにしましょう。 やり方がわからない場合は、取扱説明書で確認したり、販売店に相談に行くことをお勧めします。 とても大切なことです。子供と一緒に、やり方を覚えましょう。 本体にロックをかける子は、勝手に見られたくないと思っているからです。 親は、子供の入浴時などに、隠れてこっそり盗み見るスパイのような行動を慎み、子供の様子を見失わないよう、日頃からたくさん会話をするように心がけましょう。 ● 電池は大切に いざというときに、電池切れではケータイは役に立ちません。 圏外だからとゲームや音楽を楽しんでしまうと、驚くほど早く電池がなくなります。 肝心な時に電池切れにならないように、外でのケータイの使い方を、子供と一緒に考えましょう。 ※講師の尾花先生のご指摘により、一部加筆修正しました。(8/31) 【市P連】県P連合同研修会 講演会(5) 配布資料を基に、再構成してまとめてあります。 【演題&講師紹介】 「ケータイ&スマートフォン、これくらいは知っておこう!」 〜デジタル社会を健やかに生きる子供を育むために〜 尾花 紀子氏 ※Webサイトはこちら ※尾花氏監修 EMA 「ケータイ・インターネットの歩き方 〜子どもが安心・安全につかうために〜」 ● 災害時でもつながるケータイ 昨年3月の東日本大震災では、ケータイやスマートフォンが使えたというニュースをご覧になった方も多いと思います。 災害時の電柱・電線の倒壊や浸水による大規模な停電の場合、テレビ、ケーブルテレビ、電話、IPフォン、インターネットなどの有線情報網だけでなく、携帯電話の基地局への送電も停止されるため、携帯電話は使えない状態になります。 しかし、基地局には「緊急用バッテリー」が備えられており、災害発生直後は使える可能性もあります。 また、各携帯電話会社には、移動基地局や移動発電機が用意されているため、道路が寸断されていなければ、有線情報網よりも早く復旧できます。 大災害時、通信回線は緊急通報用に制限されてつながりにくく、メール回線もアクセスが集中すれば許容オーバーで使えません。 そんな中でも、インターネット回線は比較的自由につながります。 現在ではいろいろな自治体が、メールやSNSサイトを利用した防災システムを検討しており、すでにサービスを始めています。 自分や家族を守るために有効な緊急警報や避難情報を得る使い方を、身に付けておきましょう。 小牧市では、「緊急速報メール」の配信をしています。 事前に登録しておくと、災害発生時にメールが配信がされます。 小牧市のホームページをご覧ください。 小牧市「危機管理に関する情報」 http://www.city.komaki.aichi.jp/contents/100314... 【市P連】県P連合同研修会 講演会(4) 配布資料を基に、再構成してまとめてあります。 【演題&講師紹介】 「ケータイ&スマートフォン、これくらいは知っておこう!」 〜デジタル社会を健やかに生きる子供を育むために〜 尾花 紀子氏 ※Webサイトはこちら ※尾花氏監修 EMA 「ケータイ・インターネットの歩き方 〜子どもが安心・安全につかうために〜」 ● とってもコワイ「スマートフォン症候群」 「スマートフォン症候群」聞いたことはありますか? 仕事中や勉強中、移動中でも、スマホが手放せない中毒のような症状のこと・・・ ではありません。 スマホを長時間使用することにより引き起こされる、身体の病的変化のことを言い、最近問題視され始めています。 代表的なものに「ストレートネック」があります。 ストレートネックとは、長時間、頭が首よりも前に出た姿勢をとっていることで、首が前傾し、首のカーブが失われてしまった状態です。 これは首が細く、筋肉が弱い女性の方がなりやすいと言われています。 もともと首(頸椎)は、重い頭を支えるため、ゆるやかにカーブしていて、頭からの圧力を分散させています。 ストレートネックになってしまうと、頭を首の筋肉だけで支えることになるため、首の痛み、肩コリ、頭痛といった症状を発症します。 また、首を曲げても下部頸椎は動かないため、手のしびれ、めまい、目の奥の痛み、吐き気といった症状が出ることもあります。 ● スマートフォン症候群予防のポイント とっても怖い「スマートフォン症候群」を予防するために、以下のポイントをチェックしましょう。 (厚生労働省「VDT(画像表示装置)作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を基に、稲毛整形外科(千葉市稲毛区)の南出院長が作成した資料より) <機種選び・設定> - 外装は滑りにくい素材 - 大きめの画面。手が小さな人は大きすぎるのも× - ちらつきが知覚されないもの - 照度の自動調節機能がある場合はオンにする。最大輝度は避ける。 - 入力確認音、または振動機能をオンにし、入力時の指の力を軽減 - フォント(文字)は大きめ <使用環境・姿勢> - 連続使用時間は1時間以内 - 連続使用の場合、10〜15分の小休止を取る - 肘を固定し、目線が下を向きすぎないようにする ※写真は、講演会資料を撮影したものです。 【市P連】県P連合同研修会 講演会(3) 配布資料を基に、再構成してまとめてあります。 【演題&講師紹介】 「ケータイ&スマートフォン、これくらいは知っておこう!」 〜デジタル社会を健やかに生きる子供を育むために〜 尾花 紀子氏 ※Webサイトはこちら ※尾花氏監修 EMA 「ケータイ・インターネットの歩き方 〜子どもが安心・安全につかうために〜」 ●スマホ(スマートフォン)のこと 最近は、スマートフォンの普及率が急速に伸び、子供たちもスマホに興味津津です。 スマホは「進化版のケータイ」と思っておられる方がいらっしゃいますが、それは違います。 スマホは「通話機能付き小型パソコン」です。 パソコンですから、「アプリ」を入れさえすれば、いろんなことができるようになります。とても便利ですね。 しかし「アプリ」にも注意が必要です。 中には「個人情報」にアクセスするアプリがあります。 知らないうちに、スマホの中の連絡先データにアクセスしていたり、GPS機能を使ってスマホの位置情報に勝手にアクセスしていることもあります。 「フィルタリング設定しているから大丈夫」は、もはやスマホでは通用しません。 フィルタリングは、有害サイトの閲覧を防ぐだけで、動画やアプリのダウンロードやメール受信でのウィルス感染を防ぐことはできません。 パソコンと同じように、ウィルス対策ソフトの導入が必要です。 またソフトを入れただけではダメで、しっかり更新することが大切です。 ● スマホへの買い替え、どうする? 中学生でも、スマホ所有率は高くなってきています。 しかし、安易な買い替えは危険です。 ケータイとスマホの違いをきちんと理解し、安全に使うための「技術力」「判断力」「責任力」「自制力」が備わっていると判断できるまでは、スマホを持つには時期尚早と考えましょう。 判断するポイント <ウイルス感染の可能性もある高性能なスマホだから、自分で危機管理できますか?> - セキュリティ対策ソフトを導入する - パターンファイル(ウィルスを定義するファイル)を常に最新の状態に保つ - 送信者に心当たりのないメール(添付ファイルを含む)は開かずに削除する - 怪しげなWebサイトや、怪しげなコンテンツにアクセスしない、利用しない - アプリケーションは信頼できるものだけを利用する <いろんなことができる多機能なスマホだから、自分をしっかりコントロールできますか?> - 家族、友達、先生などとの、リアルなコミュニケーションを大切にする - 食事、宿題、登下校など、自分がすべきことを優先させ、スマホはその次に - 使っていない時は手から離す(例:食事中・入浴中は部屋に置いておく) - 使わない時間帯を決める(例:勉強中・就寝中は電源を切る) スマホへの買い替えは、上記のポイントをお子さんとしっかり話し合って、子供がきちんとできているな、と保護者が「OK」を出せるようになってから検討しましょう。 【市P連】県P連合同研修会 講演会(2) 配布資料を基に、再構成してまとめてあります。 【演題&講師紹介】 「ケータイ&スマートフォン、これくらいは知っておこう!」 〜デジタル社会を健やかに生きる子供を育むために〜 尾花 紀子氏 ※Webサイトはこちら ※尾花氏監修 EMA 「ケータイ・インターネットの歩き方 〜子どもが安心・安全につかうために〜」 ●フィルタリング 18歳未満が使うケータイには「フィルタリング設定」が必要だということをご存知でしょうか。 「青少年インターネット環境整備法(平成21年4月施行)」により、使用者が18歳未満の場合、携帯電話取扱事業者には、フィルタリングを設定して販売することが義務付けられました。 フィルタリングには、大きく分けて2種類があります。 <ホワイトリスト方式> 閲覧許可リスト(安全と思われるサイトやコンテンツをリスト化)にあるWebサイトのみが表示されるようになっている方法。 リストにないWebサイトは全て閲覧不可。 <ブラックリスト方式> 閲覧不可リスト(有害サイトや不適切なコンテンツをリスト化)にあるWebサイトを表示しないようにする方法。 リストにないWebサイトは全て閲覧可能。 フィルタリングの設定は、子供の成長や利用状況に合わせて、変更や調整ができます。 「小学生向け」「中学生向け」「高校生向け」「EMA認定サイトは可」などがあり、それぞれにアクセス制限の強度が違います。 「EMA認定サイト」とは、EMA(青少年の保護と健全な育成を目的とし、サイト管理体制の審査・認定および啓発・教育活動を行う第三者機関)が、18歳未満の利用者に対して、適切な利用環境を提供し続けるための運用・監視体制が整っている、と認めたサイトです。 しかし、せっかくの認定サイトも、フィルタリングを外したケータイや、親名義で購入したケータイから利用すれば「アクセスしているのは18歳以上だ」と判断され、18歳未満の環境に導いてくれません。 監視や各種機能制限が施された安全な環境で使わせたければ、「+EMA認定」のフィルタリング設定が必要なのです。 認定サイトとは「18歳未満のエリアが常備されたサイト」で、「全ての内容が健全なサイト」ではない。 フィルタリング未設定のケータイでは「18歳未満用」の安全な環境が利用できない。 このことを、正しく知っておきましょう。 子供が使い始めると、見たいサイトが見れない、ということで、「フィルタリングをはずしてほしい」と言ってくるかもしれません。 その時に、よくわからないからと一気に「フィルタリングOFF」としてしまうことはとても危険です。 上記のように、細かい設定ができるようになっていますから、保護者が設定方法や種類などがよくわからなければ、携帯電話の販売店に行って、相談しながら設定を変えるようにしましょう。 ●フィルタリングだけでは防げない フィルタリングは、サイトやコンテンツの閲覧を許可したり、制限したりするものです。 サイト自体は安全とされていても、その中のいろいろな機能やサービスを利用する段階で「コンタクトリスク」が生じる可能性があります。 コンタクトリスクとは、例えばブログにコメントを書いたり、ゲームのサイトで他のユーザーと一緒に戦ったりなど、ネット上で他人とコミュンケーションを取ることで生じるリスクのことです。 いくら出会い系サイトをブロックしても、よく使われるSNSや動画サイト、掲示板などを介して、 - 見知らぬ人と連絡を取り合い、実際に会ってしまって被害に遭う - コメントのやり取りが原因で、いじめに発展してしまう というようなことが現実に起こっています。 残念ながら、フィルタリングを設定しているから大丈夫、というように安心はできません。 日頃から、インターネットの使い方、使う上での注意点、節度を持った使い方などを教えていかなければなりませんね。 ※講師の尾花先生のご指摘により、一部加筆修正しました。(8/31) 【市P連】県P連合同研修会 講演会(1) 当日の配布資料を基に、再構成してまとめました。ぜひご覧ください。 「ケータイ&スマートフォン、これくらいは知っておこう!」 〜デジタル社会を健やかに生きる子供を育むために〜 尾花 紀子氏 ※Webサイトはこちら ●ケータイを持たせるタイミング お子さんが「携帯電話が欲しい」と言い出しました。 さて、保護者の皆さんはどうしますか? とはいえ、中学生であれば、すでに携帯電話を持っている子供は多いので、経験済みの方も多いと思います。 「ケータイを持たせるタイミングの判断方法と与え方」について、こんなアドバイスがありました。 *****講演資料より***** 子供がケータイが欲しいと言いだす最初の動機は 友達がみんな持ってるから 友達とメールしたい といったところでしょうか。 それを認めるか認めないかは、各ご家庭の判断になります。 ぜひ、「我が家の判断基準」を持ってください。 本当に必要な時期かどうかを見極めるために、お子さんとたくさん会話をして下さい。 ケータイを持たせるかどうかの見極めのために、次のようなステップで進めましょう。 <ステップ1> 1. 誰と誰が持っているの? 2. 何のために持っているの? はっきり、しっかり答えられるようになったら、次のステップへ <ステップ2> 3. みんなはどんな風に使っているの? 4. あなたはどうしてケータイが必要なの? これらの問いかけに、納得できるような答えが返せるようになったら、検討を開始してもいいのでは。 「持たせる必要あり」と判断しても、すぐに買い与えるのではなく、購入したケータイは、まずは親が管理して、子供が使いたい時に貸し出す「試用期間」を設けてみてはいかがでしょうか。 *****ここまで***** 親が心配なのは、どこへでも持ち運べて、画面の小さいケータイでは、子供が何をやっているのか、誰とメールをしたり電話をしているのかわからないという状況だと思います。 「試用期間中」は、親が管理しますから、電話がきた、メールがきた、という時に、その都度子供にケータイを貸し出します。 そうすれば、誰と連絡をしているのか、子供の友達関係が自然とわかってきます。 また、「使い終わったら返す」を繰り返すことで、四六時中ケータイが手放せない”依存症”になりにくい感覚を育てることもできるそうです。 1台のケータイを介して親子の会話が増える「試用期間」を経ると、子供は、親がケータイのやり取りを親に見せたり教えたりすることに、あまり抵抗がなくなるそうです。 これから子供にケータイを持たせようかという保護者の方は、試してみるとよいかもしれませんね。 ※講師の尾花先生のご指摘により、一部加筆修正しました。(8/31) 【市P連】県P連 母親代表・役員・理事合同研修会
8/7(火)愛知県小中学校PTA連絡協議会主催の、平成24年度母親代表・役員・理事合同研修会が、愛知県教育会館で開催され、参加しました。
県内から各郡市P連母親代表と役員、県P連の役員と理事が参加しての研修会です。 暑い中、大勢が集まり、講演を聞きました。 ●演題 「ケータイ&スマートフォン、これくらいは知っておこう!」 〜デジタル社会を健やかに生きる子供を育むために〜 ●講師 ネット教育アナリスト 尾花紀子氏 我々が子供だったころは、アナログな時代でした。 しかし、今の子供たちが生きる時代は、デジタルが当たり前の時代になります。 そんな中で、子供たちは、我々にはない斬新な発想や感覚で、新たなビジネススタイルや仕組みを作り出しています。 ケータイ、パソコン、スマホ・・・すっかり我々の生活に取り込まれて、今ではなくてはならないツールになりました。 子供たちは、これらのツールをどんどん使いこなし、活用してます。 このようになくてはならないツールだからこそ、正しく使ってほしい、というのはすべての保護者の思いですね。 正しい使い方というのは「情報モラル」と呼ばれており、小中学校でも学習指導要領の改訂に伴い、情報モラルに関する授業を行うことになりました。 小牧中学校でも、1学期に愛知県警サイバー犯罪対策課の梅村さんをお招きして、講座を開催しています。 (サイバー犯罪防止講座 7/18) (愛知県警サイバー犯罪対策課・梅村さんから学ぶ 7/23) 子供たちは、このような講座を通じて、「安易に使うと危険な目に遭うこともある」という認識を、少なからず持ってくれていると思います。 しかし、やはりそこはまだ子供です。 楽しいことにはどんどんはまっていくし、楽な方にどんどん流されていってしまいます。 そこをしっかり見守って、正しい方向へ導いてやるのが、保護者であり、先生であり、我々大人の役目だと思うのです。 今日のお話しの中でも、「ケータイを持たせるかどうかをきっかけに、親子でいろいろな話をして下さい」というアドバイスがありました。 親子で話し合いながら、「うちのルール」を作っていけるといいですね。 今日の講演では、デジタル社会の現状から、子供たちのケータイ事情、子供にケータイを持たせるときにどのようなことに注意したらよいか等々、とても役に立つ情報を教えていただきました。 今後、いくつかの記事にまとめて、順次アップしていきたいと思っていますので、お楽しみ。  【市P連】母と女性教職員の会 全国集会(3)
2日目は、分科会が開催されました。
全15分科会の中から、参加希望の分科会が選べます。 それぞれの分科会では、問題提起の発表があり、それについての様々な討議が行われ、教員と保護者という立場の違う人々が一緒に学びました。 【分科会一覧】 1. 乳幼児期から学童期の子育て 2. 小学生 3. 中・高生 4. いじめ・不登校 5. 性と生 6. 障害児の共生・共学 7. ジェンダー平等 8. 健康の問題 9. 食の問題 10. これからの教育 11. 社会保障 12. 平和 13. 環境 14. 女性労働 15. 母と女性教職員が手を結ぶ運動 2日間の集会に参加して思ったことは、「先生方はよく勉強していらっしゃるな」ということでした。 日々の多忙な業務をこなしながら、いろいろな研修会に参加されていて、常に新しいことに取り組む意欲を持っていらっしゃることが、討議を聞いていて感じられました。 最近、大津市のいじめ問題に関連して、先生の資質について議論されているのを、目にすることがよくあります。 一部の心ない教師がクローズアップされて、あたかも教師全体がそうであるかのような議論になることに対しては、注意して見ていかなければならないと思います。 少なくとも、我々のまわりにいる、多くの先生方は、教育に志を持って取り組まれている人がほとんどです。 無用な誤解を生まないためにも、学校はもっと開かれるべきですね。 学校の現状や、今取り組んでいること、こんな生徒を育てたいという方針などを、どんどん発信してほしいと思います。 私たち保護者も、学校に任せきりにしないで、子供を通して、学校を知る努力を忘れずにいたいですね。  【市P連】母と女性教職員の会 全国集会(2)
●8/1 全体会 その2
「原発災害と復興へのビジョン」と題して、鈴木浩先生(福島大学名誉教授、明治大学客員教授、元福島県復興ビジョン検討委員会座長)の講演がありました。 1. 東日本大震災とその時代的特質 2. 復興に向けての現状と課題 3. 復興政策に関わるガバナンスの問題点と課題 4. 復興へのビジョン 5. 浪江町復興計画策定に関わって 6. あらためて地域再生に向けて 今回の大震災は、日本が抱える様々な問題が浮き彫りになった災害でした。 疲弊する地方経済、機能しない政治、社会保障への不安など、今までは漠然とした不安として感じていたことが、現実として突きつけられました。 講演の中で、それぞれの問題の現状と課題についてのお話しがありました。 いろいろな人たちがいろいろな提言をしているのに、どうしてすぐに実行できないのかと、もどかしい思いを抱えている様子がよくわかりました。 こうした社会問題に関する話題は、難しくてわからないからと敬遠しがちですが、私たち大人は、もっと自分自身のこととして受け止めて、考えていく必要があるなと思いました。 このまま問題を先送りしていては、結局子供たちにそのツケを押しつけることになってしまいます。 まずは、関心を持って、いろいろな人の考えや意見を聞くことから始めてみようと思います。  【市P連】母と女性教職員の会 全国集会(1)
8/1(水)、2(木)日本教職員組合主催の「母と女性教職員の会 全国集会」が東京で開催されました。
小牧からは、小牧市教員組合の女性部長の先生と、市P連母親委員長の2名で参加しました。 愛知県下の各ブロックごとに、女性の先生と母親代表の方々が集合し、移動の新幹線の車中は、1両の3分の2ほどの大人数で、にぎやかな道中となりました。 2日間にわたるプログラムは、1日目に全体会、2日目に分科会となっていて、盛りだくさんの内容でした。 ●8/1 全体会 さすが全国集会というだけあって、会場が満員御礼になるほど、たくさんの人々が集まりました。 開会行事では、昨年の東日本大震災を受けて、被災地からの報告がありました。 時間が経つにつれ、被災地の現状の報道が少なくなっています。 今回の報告は、日々の生活に追われる中で、ついつい被災地に心を寄せる余裕がなくなっていることに気づかせてくれました。 まだ多くの行方不明者がいて、たくさんの子供たちが仮設住宅に暮らし、不自由な生活を強いられています。 また、原子力発電所の事故のために、避難を余儀なくされ、除染がなかなか進まない中、家に閉じこもりがちな子供たちがたくさんいます。 先が見えない生活は、さぞ不安なことでしょう。 スライドで紹介された子供たちの笑顔を見ていると、せつなくて、やり切れない気持ちでいっぱいになりました。 私たちに何ができるのだろうか・・・考えても、簡単に答えが見つかる問題ではありません。 報告を聞く中で、強く思ったことは「忘れてはいけない」ということでした。 私たちが直接手助けできることは、何もないかもしれません。 しかし、いつも心の中に被災地のことを思う気持ち、そこに生きる子供たちを思う気持ちを持ち続けることはできます。 そして、家庭で、学校で、地域で、被災地のことを話題にすることで、ひとりでも多くの人々の心の中に「想い」を持ち続けてもらえるようなきっかけを作ることはできます。 保護者の皆さん、ぜひお子さんと、ご家族と、地震や津波のこと、原発や放射能のこと、いろいろな話をしてみませんか?  |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |