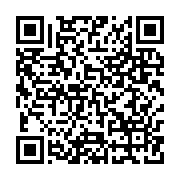|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:6 総数:156411 |
大人にできること 〜親の務め編〜 -----*----- 引用開始 -----*----- 大ニュースではないが、驚いてしまう記事がある。3年前にこんな記述があった。ある人が幼稚園で講演したとき、若い母親に「お茶って自分の家で作れるんですか」と聞かれた。「はい」と答えると、彼女はこう言ったそうだ。 「私のお母さんがお茶を作っているところ、見たことがない。いつもペットボトルのお茶を飲んできた」。彼女はどうやら、お茶を「いれる」という言い方も知らないらしい。 一昨年も似た記事があった。料理教室の先生に、急須を「これは何ですか」と聞く受講生がいたという。だが、そうした例が驚くにあたらないのを、きのう東京で読んだ記事で知った。日教組の教研集会で「今の高校生は日本茶の入れ方を知らない」という報告があったそうだ。 福岡県立高校の家庭科教諭が生徒にアンケートしたら、冬に家で飲むお茶を「急須でいれる」と答えたのは2割しかなかった。授業では急須を直接火にかけようとする生徒もいたという。 おそらくは「粗茶ですが」や「茶柱が立つ」といった言葉も知らないのだろう。市販の飲料は手軽でいいが、文化や歴史をまとう「お茶」と無縁に子らが育つのは寂しい。 「客の心になりて亭主せよ。亭主の心になりて客いたせ」と言ったのは大名茶人の松平不昧(ふまい)だった。庶民もお茶でもてなし、もてなされる。いれてもらったお茶は、粗茶でも心が和むものだ。コンビニエンス(便利)と引き換えに大事なものをこぼして歩いているようで、立ち止まりたい時がある。 -----*----- 引用ここまで -----*----- 世の中はどんどん便利になります。おそらく、これからも「もっと便利に、もっとラクに」なるように、新しい技術や製品が開発されていくことでしょう。 それらを上手に使って、私たちの生活をゆとりあるものにすることは、決して悪いことではありません。 しかし、この記事のように、便利になることで失ってしまうこともあることを忘れてはいけませんね。 「お茶の入れ方を知らない子ども」というのは、決して大げさな話ではありません。 子どもは、教えてもらっていないことは知りません。 家庭でやっているところを見たことがなければ、知らなくても仕方がありませんね。 でも、社会に出てからは「知らないと恥ずかしいこと」がたくさんあります。 「食事のマナー」「電話のマナー」「手紙の書き方」「公共の場でのマナー」など、他にもいろいろあると思います。 それを教えるのは、学校ではなく、家庭だと思うのです。 よく、非常識なことをすると、「親の顔が見てみたい」と言いますね。 これは「親がきちんと教えていることが当然だ」という前提があるからこそ、「教えていない親が恥ずかしい」となるのですね。 一般常識を「しつけ」の中で教えることは、親の大切な役目だと思います。 そのためにも、子どもたちには家の仕事を「お手伝い」させながら、将来(親子ともに)恥ずかしい思いをしなくていいように、礼儀作法をきちんと伝えていくのが、親の務めですね。 【おまけ】 受験シーズン真っただ中です。 先日テレビで「必ず茶柱が立つお茶」が売られているというニュースを見ました。 験担ぎで、飲んでみたいですね。 |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |