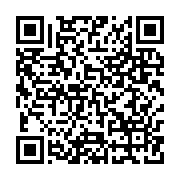|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:10 総数:156329 |
5/19 第1回 総務委員会 新総務委員になって、初めての総務委員会です。 土曜日なので、窓の外の運動場では多くの部活動が行われていました。 がんばっている子供たちの笑顔はいいな〜と感じながらの委員会となりました。 ● 協議事項 1. 専門委員会の進め方 2. 6/18学校公開日について 当日の役割について、PTAサロンの運営についての説明がありました。 3. 役員選考委員の選出について 本日の全委員会で、役員選考委員の選考をするため、その打ち合わせを行いました。 5/18 新旧総務委員会懇親会
5/18 新旧総務委員の懇親会が開催されました。
たくさんの方々に参加していただき、大変楽しい時間を過ごすことができました。 退職された清水先生と小牧小学校に転任された後藤先生にも参加していただきました。 清水先生は、自然に囲まれた職場で第二の教員生活をスタートされ、時間にもゆとりが生まれて、趣味の写真と自然観察に、よりアグレッシブに情熱を注がれています。 後藤先生は、新校舎になった小牧小学校へ教頭先生として赴任され、今まで以上に力を発揮されています。 お二人とも、小牧中のPTAに深い愛着を持って関わっていただき、離れてもなお関心を寄せていて下さいます。 お世話になったこと、心から感謝しています。本当にありがとうございました。これからも温かく見守っていて下さい。 旧総務委員の皆さん、本当にありがとうございました。皆さんのおかげで、新年度への引継ぎもスムーズにでき、新たなスタートが切れました。 引き続きお世話になる方々もたくさんいらっしゃいます。とても心強いです。今年もよろしくお願いします。 今日の校長先生のお話しは、小牧中に新しい風を吹き込もう!という強い思いに溢れていました。 校長先生の頭の中では、小牧中を「開かれた学校」にするための様々なアイデアが続々と生まれているようです。 ぜひPTAも一緒に取り組んでいきたい!とワクワクしています。 今年は、「楽しいPTA、元気なPTA」がキーワードになりそう。おもしろくなりそうな予感がしますよ。    ABCDの原則 〜あいさつ編〜 その時に感じた、あいさつにまつわるお話です。 学校内を見知らぬ大人(オバサンであればなおさら)がウロウロしていても、無関心な態度がふつうだと思っていました。 ところが、牧中の生徒たちは、みんなが「こんにちは!」と元気にあいさつをしてくれるのです。 最初は正直面くらいました。 こちらも負けじとあいさつしましたが、その顔が引きつり気味だったのを覚えています。 最初はたまたまなのか?と思っていましたが、いつでも誰でも(男女の別なく)すれ違う時に、元気に「こんにちは!」なのです。 こちらも調子に乗って、たまに声をかけてもらえそうにない雰囲気だと、こちらから「こんにちは!」と声をかけますが、みんなきちんとあいさつを返してくれます。 あいさつはいいですね。 ほんとにじんわりと温かい気持ちになります。 こういう体験を通して、子供たちが人と関わる基本を身に付けているな〜、「ABCDの原則」がしっかり守れている子が多いな〜と実感しています。 これは、学校の先生方の指導の賜物だと思うのです。 そして、先生方の指導を素直に受け入れる心を育てた保護者の皆さんの力でもあります。 先生方のご尽力に感謝しつつ、家庭でも、まずは笑顔で「おはよう」から。 子供たちの素直な心を伸ばしていきたいですね。 職業としての教師を考える
昨日の学校HPに、遅くまで残ってテストの採点をしている先生の記事がありました。
職業としての教師について考えてみます。 教師は専門職です。授業をするための専門的な知識と技術が必要です。専門職であれば、本来は専門部門の仕事だけをすればいいわけです。 しかし実際は、付随する膨大な事務業務(授業のための準備や資料作成、テスト作成、採点、成績付け、お便り作成等々)、部活動の指導、ときには渉外的な仕事(保護者や業者への対応など)、集金があれば会計業務、といった具合に、非常に多岐にわたる業務を担当しています。 一般企業で考えると、いろいろな部署に分けられて行われる業務を、教師はひとりで行っていると言えます。 授業時間中は拘束されるので、その他の事務や様々な業務は、必然的に生徒が帰った後、または休日にやらざるをえないでしょう。 昨日の記事の様子は、実は日常茶飯事の職員室の風景なのです。 まさに激務といえる職業です。 やらされている仕事であれば、これだけの業務をこなすのは、とても無理でしょう。 体調を崩されて、学校を離れる先生が多いのもうなずけますね。 そんな中でがんばっている先生方を支えているのは、やはり教育に対する情熱や、子供の成長に触れる喜びがやりがいにつながっているということなのだろうな、ということが先生方とお話ししていて感じたことです。 自分の仕事に、誇りとやりがいを感じられる職業が教師なのですね。すばらしい職業だと思います。(激務ではありますが・・・) 応援しています。がんばって下さい、先生! 兒の森でリス発見!@趣味'sブログ   「学び合う学び」に学ぶ 〜聴く編〜 とくに1年生の保護者の方は、初めての定期テストということで、ずいぶん気を揉んだのではないでしょうか? 答案が返ってくるまで、学年順位が出るまでの数日は、少しホッとできるひとときですね。(つまり、答案が戻ってくると・・・雷が落ちたり、竜巻が起きたりするお宅もあるかも?) 今日のところは、「お疲れさま」とやさしく言葉をかけてあげて下さい。人は言葉を浴びて育ちますから(By校長先生) そして、「どうだった?」と話を聴いてあげて下さい。「聴く」です。 3年生の廊下の掲示物にあるように「目」+「耳」+「心」で受け止めてあげて下さいね。(学び合う学び 4/19の記事) ダメだったこと、努力が足りなかったなということがあれば、本人が一番よくわかっているはずです。 今日はゆっくり話を聴いてあげるだけ。 明日からの日常に戻る前のほんのひととき、テストの緊張から心を解放してあげたいですね。 「学び合う学び」に学ぶ 「学び合う学び」という言葉は、小牧市教育委員会の重点施策にも挙げられていて、小牧中学校の「経営目標」にも入っています。経営目標はこちら 学校で、子供たちは先生から学びます。また生徒同士でも学びます。先生も生徒から学ぶこともあるでしょう。こうして、先生と生徒はいろんな形で学び合っているのですね。 さて、私たち保護者はどうでしょうか? 家庭で、子供たちは親から、祖父母から学びます。兄弟がいれば、子供同士でも学びます。そして親も、子供たちから多くを学びます。 さらに、親である私たちは、子供を通して学校(先生)からも学んでいると思うのです。 逆に、学校(先生)も子供を通して、親から学んでいることもあることでしょう。 こうして考えてみると、学校(先生)、生徒(子供たち)、保護者は、お互いに学び合っていると言えませんか? 「学び合う学び」というのは、けっして先生と子供の間だけの話ではなくて、保護者も含めた大きな枠組みで取り組める、とてもすばらしい目標なのではないでしょうか。 学校HPの「学び合う学び」のページから、私たちも一緒に学びたいですね。 見守りのかたち〜その2〜 先日の学年懇談会のときに、ある先生がおっしゃっていたことが、とても心に残りました。 その先生は、毎朝、校門で登校指導をしていらっしゃいます。 「毎日見ていると、子供たちの小さな変化がほんとによくわかります。 ちょっと元気がないな、なにかいつもと違う、気になるなと思ったら、その生徒の担任に様子を伝えています。 そして担任が個別の指導につなげています。」 親でも気付かない小さな変化を、先生が見つけてくれることもあります。 先生にだけ見せる表情もあるかもしれません。 そんな様子を丁寧に拾い上げてくれる先生に感謝しています。 クラス担任だけでなく、いろいろな先生が、子供たちの様子に気を配って下さっています。多くの温かい目に支えられた「やさしい見守りのかたち」ですね。 見守りのかたち 牧中生の登下校のマナーがよろしくない、という苦情が地域の方々から出ていることは、以前記事にしましたね。 学校としても、これは看過できないということで、時々、登下校時に通学路を先生が見回っているそうです。 今週はテスト週間。早い時間に大勢の生徒が帰宅します。一昨日も、先生方が通学路に立たれていたそうです。 「こらーもっと右に寄れー!」と先生から声が掛かると、さすがにビシッと端に寄って、いつもは道いっぱい広がって歩いているところが、この日は半分の空きスペースができたそうです。 すぐに指示に従う素直さは、さすが牧中生!と思わせるかわいらしさですが、きっと先生の目が届かなくなると・・・想像できますよね。 おこられなくても、見られていなくても、自然に行動できるようになるまでには、だいぶ時間がかかることでしょう。 でも、すぐに効果は出なくても、こうした地道な取り組みを先生方は続けて下さっています。 これが、先生方の牧中生への「見守りのかたち」なんですね。 『おまけ』 昨日、市P連役員会からの帰り道、たくさんの生徒たちが下校していました。 様子を見てみると・・・ 狭い歩道でしたが、みんなはみ出さずに歩いていましたよ。 見たのは一部の通学路だけですが、ちょっぴりホッとしました。 ABCDの原則 〜交通ルール編〜
集団登校中の児童の列に乗用車が突っ込んで多数の死傷者が出るという悲惨な交通事故が、先月から各地で立て続けに起きています。そんな中、昨日は、小牧市内でも中学生が登校中に乗用車にはねられて重体になったというショッキングな事故が起きてしまいました。
原因は自動車側にあるのは明白ですが、なんとか子供たちを事故から守りたい、守るためにはどうしたらいいんだろう…と考えていて、ABCDの原則を思い出しました。 実は、当たり前のこと(ここでは交通ルールを守ることですね)ができていない牧中生が意外に多いようなのです。 以前より、学校の先生方から、牧中生の登下校時のマナーについて、地域の方から度々苦情をいただくんですという残念な情報を聞いています。 例えば、歩道いっぱいに広がって歩く、車道にはみ出す、おしゃべりに夢中で道を譲らない等々。 本人たちは気付いていないのでしょうが、中学生であれば、他人に迷惑をかけていることを自覚してほしいところです。 保護者の皆さんは、そんなことで苦情なんて、と思われるかもしれませんが、一事が万事、おそらく氷山の一角なのではないでしょうか。 小牧中は生徒数が800名以上のマンモス校なので、一斉下校ともなると周辺は大混雑になってしまうのは仕方がないことだと思います。 しかし、それでも一人一人が「ABCDの原則」を意識してくれれば、きっと危険も避けられると思うのです。 常に一列になって歩きなさいというわけではありません。他人に迷惑をかけないように、節度と少しの気遣いを持って、元気に登下校してほしいと願っています。 親子で、「交通ルールのABCDの原則って何だろう?」と話し合ってみませんか? 小牧山のツツジが盛りです@趣味'sブログ   「ABCDの原則」に想う ぜひお子さんに聞いてみて下さい。 学校のHPにも特設ページができていますし、始業式や集会で校長先生から生徒にお話しがあったので、お子さんはよくわかっているはずです。 「A」当たり前のことを 「B」バカにしないで 「C」ちゃんとやれる人こそ 「D」できる人 とっても上手いネーミングだと思いませんか?語呂が良くて覚えやすく、求めていることが子供達にストレートに伝わりますよね。 「当たり前のこと」というのは、「社会生活を送る上で必要なこと」と考えれば、子供たちが、今、身に付けておかなければならない大切な力だと思います。 校長先生のおっしゃるように、恥ずかしながら大人の世界では、こんな当たり前のことが出来ていない人がとっても多いのが現状です。始業式の式辞はこちら そんな中で、学校では、先生方が本気で取り組んでおられます。これは学校HPでもよくわかりますよね。 私達は、親として、子供たちが社会へ巣立つ前に「ABCDの原則」がしっかり守れる人間になってほしいと、誰もが願っています。ぜひご家庭でも「ABCDの原則」を話題にしていただいて、親子で考えるきっかけにしていただけたらうれしいです。 各委員長と学校側担当者との顔合わせ
4/19 PTA総会の後、PTAの各委員長さんと学校で活動をサポートして下さる先生方との顔合わせを行いました。
新年度になり、先生方の異動もあったため、お互いの確認の意味でも顔合わせの機会を作っていただいたことはとても助かりました。先生方には、業務でお忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。各担当は以下のとおりです。 ●総務委員会 PTAサロン→(P)齋藤母代 (T)林先生(栄養教諭) ●保健委員会 リサイクル→(P)崎野委員長 (T)林本先生(校務主任) 給食試食会→(P)崎野委員長 (T)林先生(栄養教諭) ●環境委員会 花植え、除草作業→(P)田中委員長 (T)林本先生(校務主任) ●教養委員会 教養講座など全般→(P)舩橋委員長 (T)岩田先生(教務主任) ●広報委員会 新聞作成全般→(P)鬼頭委員長 (T)小島教頭先生 ●生徒指導委員会 登校指導→(P)柚之原委員長 (T)渡邉先生(安全主任) ジュニア奉仕団→(P)柚之原委員長 (T)塚田先生・熊澤先生 PTA総会のおまけ ところで、「A」は何の略だがご存じですか? 「集まれ〜」→意味はイイ線いっていますが、日本語なので不正解 「ありがとう」→感謝の気持ちはいつも持っていたいですね。でも不正解。 正解は「Association」 組織、団体という意味です。辞書によると、「同じ志を持つ人々の組織や団体を指す」とあります。 人の想いは十人十色ですが、PとTは同じ方向に向かって一緒に取り組んでいけるといいですね。 4/19 PTA総会 たくさんの保護者の方々や先生方にお集まりいただき、ありがとうございました。 おかげさまですべての議事についてご承認をいただき、平成24年度の牧中PTAとしてスタートを切ることができました。 1年間、どうぞよろしくお願いいたします。 校長先生のご挨拶で、心に残った言葉「木は光を浴びて育つ。人は言葉を浴びて育つ。」 子供たちにはもちろん、伴侶にも「優しく」言葉をかけましょうね。 校長先生のご挨拶はこちら 4/14 旧総務委員会 今年度から小牧中学校に赴任された玉置校長先生にも参加していただきました。校長先生は、平成10年から15年までの6年間、小牧中学校の教頭先生として勤務されていたとのことで、とても牧中に詳しいのです。 ちょうど校舎が小牧山から現在地に移った時に赴任されたので、その時のこぼれ話を教えていただけました。グランドを囲む形で高圧鉄塔が建っているのをご存じですか?元々、あの鉄塔はまっすぐ伸びて、校舎の上を通ることになっていたそうです。しかし、教育の場にそのような危険なものを置くわけにはいかない!ということで、急角度で方向転換させて今のようにグランドを囲む形になったそうですよ。 学校へお越しの際は、鉄塔の配置もチェックしてみてくださいね。 牧中PTAホームページ リニューアルのお知らせ
平成24年度が始まりました!
先日のPTA総会にて、新役員の承認をいただき、牧中PTAも新体制でスタートしました。 牧中PTAを盛り上げるべく、役員一同がんばっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 先日のPTA総会での玉置校長先生のご挨拶を覚えていらっしゃいますか? 英語の授業で生徒に聞きました。「PTAって、何の略か知っているかい?」「Pは?」「Parentsです」「Tは?」「Teacherです」「Aは?」「うーん、集まって〜かな」思わず吹き出してしまいました。 その後で校長先生が「しかし、私はこの答えがPTAの本質を突いているなと思うのです。教師とおうちの方々が集まっていろいろやっていくのが、まさにPTAだと思います。」とおっしゃり、深く共感しました。 私たちは、学校と保護者が協力して子供たちの成長を支えていく、そんなPTA活動を目指していきたいと思っています。 そんな想いを込めて、学校と家庭のかけはしになるように、いろいろな情報をお伝えしていくホームページを作っていきたいと思っていますので、ご支援ご協力をお願いいたします。 |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
||||||||||