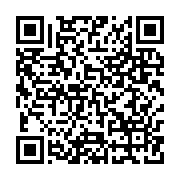|
最新更新日:2024/06/08 |
|
本日: 昨日:12 総数:156422 |
祝!ちゅうでん教育振興助成贈呈式 学校HPに、贈呈書の写真がアップされています。 (教育振興助成金贈呈書 10/6) 以前、PTAの部屋でも「ちゅうでん教育振興助成金」の受賞決定について、記事にしました。 (「第2回 親子で学ぶ夜の中学校」へのお誘い 9/3) 全国からの受賞校の中に「小牧市立小牧中学校」という校名が並んでいることに、とても誇らしい気持ちになりました。 こんなすばらしい体験は、そうそうできるものではありませんよね。 PTA役員冥利につきる一日でした。 助成の対象となった「新しいことを始めるよ!企画」から生まれた「親子で学ぶ夜の小牧中学校」は、毎回好評をいただいており、学校と家庭や地域をつなぐ「名物企画」へと育ちつつあります。 これからも、今回の受賞を励みに、PTAも「夜の小牧中」を応援していきたいと思っています。 次回も、ぜひたくさんの皆さんのご参加をお待ちしています。 表彰式と贈呈式の後、記念講演会が開催されました。 「学校・家庭・地域で取り組む防災教育〜想定を超える災害から子どもたちの命を守るために〜」と題して、群馬大学大学院教授の片田敏孝先生のお話をお聞きしました。 片田先生は、昨年の東日本大震災で、あの「釜石の奇跡」と呼ばれた釜石市で、防災教育を長年にわたり行われてきた方です。 「子どもたちの命を守るために」どのような防災教育を行ってきたのか、ということを、とてもわかりやすくお話しいただき、その内容は、私たち保護者も肝に銘じておかなければならないな、と考えさせられるものでした。 ぜひ皆さんにもお伝えしたい内容でしたので、まとめの記事を、後日アップしたいと思っています。 ※写真は、大賞の表彰の様子です。振興助成は代表表彰でしたので、小牧中の表彰の写真ではありません。ごめんなさい。 「愛知のPTA」の記事より 〜ほめる〜 中面に、スクールカウンセラーの山口 力さんの「子育てワンポイントアドバイス!」というコーナーがあり、今回は「ほめ方」についてのお話でした。 「PTAの部屋」でも、「未来の大人たちへ」の関連記事で「ほめる」ことについて書いたばかりだったので、とても興味を持って読ませていただきました。 (「大人の先輩からのアドバイス」に想う その7 10/5) 「愛知のPTA」をご覧になっていない方にも、ぜひお伝えしたい内容だったので、簡単にまとめましたので、参考にしていただけるとうれしいです。 -----*-----*-----*-----*-----*----- ●ほめ方の種類 「ほめ方」には、2種類あります。 1. 「結果」でほめる 2. 「プロセス」でほめる ●それぞれのほめ方の特徴 1.「結果」でほめる ・一般的によく使われる方法 ・評価の基準は「できる」か「できない」か、しかない ・人との比較によってほめることにつながりやすい → 結果として、子供は「あの子よりもできないといけない」という思いを持ちやすく、出来ない自分のことを認めることができず、自分を好きになれない、ということにつながる 2.「プロセス」でほめる ・他者との比較は関係なく、自分自身が認めてもらえる ・親も、結果ではなく、「今」や「行為」に意識が向く ・評価の基準は無限にある → 結果として、子供は自分に自信をもつことができ、本物の優しさと思いやり、感謝を表現する子供に育つ -----*-----*-----*-----*-----*----- まずは、親が意識を変えることが大切ですね。 「結果」でほめることはわかりやすいので、ついつい「0」か「100」かという極端な基準でほめてしまうことがあります。 また、他者と比較することもわかりやすいので、ついついやってしまいますよね。 でも、それでは子供の心が「優越感」や「劣等感」ばかりになってしまいます。 子供が本当に自分が好きになって、自分に自信を持てるようになるためには、「プロセス」でほめることが、とても大切なのですね。 子供の「ほめポイント」は、「プロセス」の中に見つけるように、努力していきたいと思います。 「大人の先輩からのアドバイス」に想う その8 (柗浦隆子さんから「未来の大人たちへ」 9/17) ●伝統を大切に 我々が子供のころと比べると、今は外国人との交流の機会が増えています。 小牧中にも、7月にアメリカのワイアンドット市からの中学生が訪問してくれました。 (ワイアンドット市小牧訪問団・牧中に来る 7/2) 記事には、「生徒たちが、日本文化(習字、折り紙など)を体験した」とあります。 言葉でうまく伝えられなくても、実際にやって見せたり、体験してもらうことで、外国の方々との距離が、ぐっと近くなることもあります。 日本では、恥ずかしがり屋さんで控えめな人のことを「奥ゆかしい」といって美点とすることがありますが、外国の方々との交流の時は、ぜひ積極的に行動できる「はつらつ」とした人になってほしいと思います。 日本の伝統文化にはいろいろありますが、説明するのがとても難しいことが多いです。 そんな時に、イメージがわきやすいように、実際にやって見せることができれば、とても役立ちます。 例えば、着物を着たり、茶道や華道をしたり、琴などの楽器を演奏したり、といったことは、今では誰でもできることではなくなりました。 柗浦さんがおっしゃるように「日本にはこういう伝統文化がある」と自信を持って言えるようになるためにも、男女問わず、大人も子供も、伝統文化の一つや二つは、たしなみとして身に付けておきたいですね。 「大人の先輩からのアドバイス」に想う その7
大変好評な「未来の大人たちへ」シリーズ企画ですが、第4弾には、小牧市更生保護女性会会長の柗浦隆子さんが登場して下さいました。
(柗浦隆子さんから「未来の大人たちへ」 9/17) それまでは男性からのアドバイスが続いていましたが、今回は女性からのアドバイスをお聞きすることが出来ました。 お母さんたちにとっては、母親として心に留めておきたいお話でしたね。 ●ほめて育てる 「子供はほめて育てましょう」・・・本当に、よく聞く言葉です。 柗浦さんも「ほめて育てることは、子供の成長に一番必要なことです」とおっしゃっています。 まさにそのとおりだと思います。そう思いますが、けっこう難しいことだなぁと感じていらっしゃる保護者の方が多いのではないでしょうか? 「PTAの部屋」でも、以前「ほめる」ことについて記事にしました。 (見守りのかたち 〜ほめる編〜 6/3) 今、改めて、はたして自分は「子供のほめポイント」を見つける努力をしてきただろうか・・・と考えてみませんか? バッチリよ!という方は、そのままどんどん続けて下さい。 う〜ん・・・という方は、今日から始めればよいのです。 忙しい毎日の生活の中で、いつもいつも「子供をほめてあげたい!ほめポイントを見つけよう!」と考えていることは難しいかもしれません。 でも、時々思い出して、1つでも2つでも、子供に「ほめ言葉」をかけることを忘れずにいたいですね。 小牧山のシラカシの木には「ドングリ」がいっぱい。カエデの紅葉はもう少し先のようです@趣味'sブログ   「進路説明会の校長あいさつ」に想う ご覧になった方も多いと思います。 (進路説明会での校長あいさつ 10/1) 「小牧中3年生の中で、毎日の勉強時間がとても短い生徒(1時間以下)が、3分の1以上もいる」という驚くべき内容でした。 4月の全国学力・学習状況調査の時の質問に対する回答だったので、10月になった今では、おそらく「勉強時間は増えている」と信じたいですが、実際はどうでしょうか? 保護者の皆さんからご覧になって、お子さんの勉強時間は多いですか?それとも少ないですか? ただ時間が長ければいい、ということではないと思いますが、やはりやらないよりは、やったほうがいいに決まっていますよね。 家庭学習の時間は、「学年×1時間」という話はよく聞きます。 子供たちは、どうして勉強しなければならないのかをしっかり納得して、自分で「やらなくちゃ!」と決意すれば、どの子もしっかりがんばれる力を持っています。 まずは、「自分の進路をどうするのか」ということを、ご家庭でしっかり相談して、親子でじっくり話し合って、目標設定をしなければいけませんね。 これは3年生だけのことではなく、1・2年生にとっても、すぐに降りかかってくる話です。 進路に関しては、早すぎるということはありませんから、今のうちから、お子さんと話をしておくとよいと思います。 進路という目標が決まれば、子供たちは、どうすればよいかを自分で考え、しっかり努力ができるはずです。 学校HPで、いろいろな活動に一生懸命取り組む子供たちの様子を見ていると、「この子たちなら、きっと大丈夫」という気持ちになりますよね。 子供たちの「がんばる力」を信じて、目標が達成できるように、いつもさりげない「言葉かけ」でサポートができる親でありたいですね。 合唱のチカラ 〜再び〜 これは、3年生の保護者の皆さんからの「あの合唱の様子をぜひ見たい!」というたくさんの声に、学校が快く応えていただいて実現したことです。 学校のご配慮に、心から感謝します。 今回の上映会のために、赤の学年(3年生)の先生方は、ビデオの再編集をして下さったそうです。 タイトル画面から続く、当日のスナップ写真のスライドショーは見ごたえ十分で、進路説明会に参加するために会場にいた3年生たちからも「おぉ〜」と歓声が上がり、すっかり観客になっていました。 お忙しい中、上映会のために尽力していただいた赤の学年の先生方。 本当にありがとうございました。 合唱は、「上を向いて歩こう」「ふるさと」最後にアンコールに応えての「校歌」の3曲でした。 それぞれの曲紹介には、子どもたちのその曲に込められた想いが語られ、大切に、心を込めて練習してきた様子が伝わってきました。 赤の学年の先生方の熱い想いに支えられ、立派に成長した子どもたち。 本当に、すばらしい合唱でした。 修学旅行の出発直前に、「PTAの部屋」でも、この合唱について記事にしました。 (合唱のチカラ 5/21) あのとき、私たちが、子どもたちへ託した想い。 子どもたちは、見事にその想いを受け取って、すばらしい合唱という形で応えてくれたのですね。 通りすがりの、見ず知らずの観客の方々が、次々に足を止めて、子どもたちの歌声に、耳を傾けて下さいました。 「ふるさと」の合唱のあとにかかったアンコール。 子どもたちは、とても誇らしい気持ちになったことと思います。 3年生の皆さん あなた方は、こんなにもいろいろな人に支えられています。 そして、その想いに応えて、素直に成長してくれています。 これから、11/2のコーラス大会に向けて、クラスでの練習を重ねていく中で、この上野公園での合唱を思い出して、さらにすばらしい合唱を作り上げて下さいね。 また、あの感動に出会えることを、期待しています。 【総務】10/1 PTAサロン
10/1(月)リサイクル販売と同時に、保護者の皆さんに大変好評の「PTAサロン」を開催しました。
台風の動向が気になった週末でしたが、予想よりも早く台風が通過したおかげで、今日は台風一過の晴天に恵まれ、今回もたくさんの保護者の方にご参加いただきました。 ありがとうございました。 こちらも広報委員さんが取材して下さいました。 取材報告をお届けします。 -----*-----*-----*-----*-----*----- サロンは時間が経つにつれ、徐々に人が増え、皆さん楽しく、和やかにおしゃべりしてました PTAサロンでは、まず入口で給食のデザートのクレープ、エクレア、りんごゼリーと、役員の方々の笑顔がお出迎え。 「暑〜い」とバテ気味だったのが、これで吹き飛びました(^_^)v 取材を忘れ、記者も暫し休息。 気付くと満席に近い大盛況となっていました。 お菓子を食べ、コーヒーを飲みながらの情報交換はとても楽しそうで、あちらこちらから笑顔が溢れていました。 今日は小学校運動会の代休で、小学生も多数来場していました。 小牧中学校にどんな印象を持ってくれたのかな(^o^) -----*-----*-----*-----*-----*----- 今回は、時間の都合で「ミニミニ講演会」が開催できませんでした。 「今日は先生のお話ないの?」と楽しみにしていただいていた保護者の皆さま、ごめんなさい。 次回は開催できるように調整したいと思いますので、お楽しみに!    体育大会の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(4) 本校では、体育大会は日頃の体育の授業の延長と考え、陸上競技種目を中心にしたプログラムになっています。種目内容・数についていかがでしょうか。 (体育大会保護者アンケート(種目と数) 9/26) 小牧中学校では、生徒数が多いため、時間の都合もあり、そんなに多くの種目は実施できないのが現状です。 その中でも、全員が参加できるように考えられた種目を実施しています。 アンケートの結果からは、だいたい適していると考えておられる保護者が多数ですが、今後、学校で検討されるとのことなので、その動向を見守りたいと思います。 【質問5】 保護者の応援・観覧の様子はいかがだったでしょうか? (体育大会保護者アンケート(保護者の応援観覧) 9/27) たくさんの保護者の方々に来ていただき、ありがとうございました。 保護者の参観場所について、多数のご意見が寄せられているという話を、学校より伺っています。 いろいろと改善するべき点はあると思いますので、今後、学校と協議していきたいと思います。 多くのご意見をありがとうございました。 【質問6】 体育大会全体のことや職員の動き等、どのようなことでもけっこうですので、お気づきの点があればお知らせください。 自由記述のご意見も、多数お寄せいただきました。 今まで、学校に対する意見は、なかなか伝える機会がなかったのですが、今回のアンケートのように気軽に伝えることができるのは、とてもありがたいですね。 学校へは、良い意見ばかりでなく、改善を求める意見も多く寄せられているとのことで、校長先生からも、それぞれ検討していくということをおっしゃっていただきました。 今後、学校HPでも検討結果がアップされると思いますので、ぜひ注目していて下さい。 体育大会の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(3) 生徒の、参加・応援・観覧態度はいかがだったでしょうか? (体育大会保護者アンケート(生徒応援) 9/26) 「体育大会は体育の授業の延長にある」という校長先生のお言葉のとおり、運動が得意な生徒にとっては晴れ舞台になります。 保護者としても、我が子が運動が得意であれば、応援にも力が入りますね。 しかし、当然ながら、すべての生徒が運動が得意ということはなく、運動が苦手な生徒にとっては「できればやりたくない」という気持ちが大きいでしょう。 そんな生徒たちにも、活躍できる場面があります。 仲間たちのサポートや応援、観覧態度です。 当日の生徒たちの様子は、立派だったと思います。 これは、体育大会が、運動が得意な生徒だけでなく、苦手な生徒にとっても晴れ舞台になる、ということですね。 体育大会の様子を見ていて、学校では「全員で作り上げる」という指導をされていたことと思いますが、十分にその成果が出ていたなと感じました。 そして、多くのご家庭で、保護者の方々が子どもたちを励まし、支えて下さったことも、大きな力になったことでしょう。 子どもの笑顔は、親を幸せな気持ちにしてくれます。 たくさんの笑顔の花が咲いた、すばらしい体育大会でした。 体育大会の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(2) 子どもたちは学級応援・全校生徒による全体応援に特に力を入れ、全校で取り組んできました。生徒会年間テーマ「成超」のもと、全力投球・最高の演技をめざし、「燃える闘魂」という体育大会テーマを達成しようとがんばりました。子どもたちの思いは伝わったでしょうか? (体育大会保護者アンケート結果(生徒たちの思い) 9/25) 小牧中学校では、体育大会での生徒の「学級応援」「全体応援」に力を入れています。 生徒会を中心に、1学期の終わりから夏休み中もずっと準備を続けてきました。 生徒たちが、自分たちで作り上げる応援合戦。今年も、とても迫力のある応援を見ることができました。 とくに学級応援は、実行委員と一般の生徒との間で「やる気」の温度差が出るので、どのクラスも山あり谷ありで、苦労しながら、応援を作っていったことでしょう。 そうやって作り上げた学級応援は、どのクラスもとてもすばらしいものになっていました。 全体応援も、少ない練習回数にも関わらず、「成功させよう!」という熱い気持ちが伝わるものでした。 応援合戦の後、保護者の方からの「すごかったね」「よかったね」という声をたくさん聞きました。 きっと各クラスに強い絆が生まれたことでしょう。 この団結力を、これからの活動に活かしていってほしいなと思います。 体育大会の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(1) その後に実施された携帯アンケートについても、多くの回答をいただきまして、本当にありがとうございます。 さっそく、学校HPで、結果についての記事がアップされています。 それを拝見していて思ったことを「保護者の視点で」お伝えしたいと思います。 【質問1】 800人を越える生徒が、一人一人きびきび動き、いい表情で、演技はもちろん、仲間のサポート〈委員会など裏方の仕事なども〉に取り組めるよう、短い時間でしたが全職員で指導してきました。その成果が出ていたでしょうか? (体育大会保護者アンケート結果(体育大会成果) 9/25) 召集時の移動、競技後の移動、どれも皆、きびきびと動いていました。 クラスの仲間が力を発揮できるように、「応援」でサポートする様子もすばらしかったです。 当日は、懸命に大会の運営に携わる、多くの生徒の姿を見ることができました。 それぞれの生徒が、自分のできることを精一杯がんばっている姿をみることができたことが「97%」のご意見となったのだと思います。 これは、生徒たちのがんばりを引き出した、先生方の指導の賜物でもあります。感謝したいと思います。
|
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
||||||||||