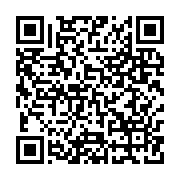|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:10 総数:156329 |
給食のおはなし その2
期末テストが始まり、その間給食はお休みです。
いつも楽しみにしている「今日の給食」のページが見られないのは、ちょっとさみしいですね。 小学生の弟や妹のいるご家庭では、「今日の給食はどうだった?おいしかった?」「うぅ〜食べたかったな〜」なんて会話が交わされているのでしょうか? 先週の火曜日、台風4号が猛威をふるいました。 幸い小牧では大きな被害もなかったようで、なによりでした。 しかし、保護者にとっての関心は、ズバリ「明日の給食があるかどうか」ではないでしょうか? 今回は、「翌日の給食は実施します」というお手紙が配布され、ヤレヤレと胸をなで下ろしました。 今年は、何度このような「台風でドキドキ」な目に遭うのでしょうか・・・ 給食を中止にするかどうかの判断は、どのようにしているのかな?と疑問がわいたので、台風のときの小牧市の学校給食の対応について調べてみました。 小牧市のホームページに、以下のような説明がありましたので、ご紹介したいと思います。 (以下、市HPの引用です) 台風により暴風警報が発令される恐れのある時は、前日の午前10時までに給食を実施するか、中止するかを市教育委員会が決定し各学校に通知します。ただし、前日が土・日曜日や祝祭日などの休日の場合は、その前の学校が開校している日に決定します。 例えば・・・ * 例1 給食実施予定日の10月18日(月)に暴風警報が予測できる場合には、土・日曜日の前日の15日(金)午前10時までに決定します。つまり、3日前に決めることになります。 * 例2 給食実施予定日の10月12日(火)に暴風警報が予測できる場合には、前日の11日(月)は体育の日で祝日なので、8日(金)午前10時までに決定します。つまり、4日前に決めることになります。 なぜ、そんなに早く給食を実施するか、中止するかを、決めるのかと疑問をもつ方もいらっしゃると思いますが、主な理由としては次のことが挙げられます。 * 保護者への連絡手段は児童・生徒を通して行うので、児童・生徒が下校するまでに決定し連絡する必要があるためです。 * 給食に使用する食材の製造や、納入を前もって中止する必要があるためです。 いずれにしても台風という自然現象のため、予測が困難であり非常に難しい判断を迫られるものです。児童・生徒の登下校時の安全を確保しつつ、また給食の食材についても無駄にしないよう、慎重に判断しています。 (以上、引用ここまで) 夜のうちに台風は通過してしまい、今日は青空が広がっている、という天気であっても、前日に「給食中止」の判断がされていれば、弁当持参になるのは仕方のないことですね。 そんな時、当たり前だと思っている毎日の給食が、とてもありがたいことなんだなと感じます。 生徒の皆さん、3日ぶりの明日の給食を、感謝してもりもり食べて下さいね。  「努力の成果は加速度的に現れる」に想う 生徒の皆さんの努力の成果が、しっかり現れるといいなと願っています。 1ヶ月ほど前に、学校HPに校長先生が集会でお話になった「努力の成果は加速度的に現れる」という記事がアップされました。 (努力の成果は加速度的に現れる 5/28) 子供たちは、その子なりに努力していることと思います。 今回のテスト勉強でも、きっと「がんばってるな」と思える姿に、多くのご家庭で出会えたことでしょう。 しかし、その努力が、必ずしも結果に結びつかないことは、よくあることです。 成果が現れなければ、ガッカリして、やる気を失ってしまいますね。 それは私たち大人も同じことなので、気持はよくわかります。 でも、そこであきらめたら終わりです。 校長先生のおっしゃるように「努力の成果は加速度的に現れる→努力し続ければ、その成果は一気に現れる時が来る」となることを信じて、努力することをあきらめないでほしいと思います。 サッカー日本代表の長友佑都選手がインタビューで 「僕にはサッカーの才能はないけど、努力する才能はある」 と言っていました。 彼は、努力は裏切らないという信念で、世界のトップ選手になった今でも努力することを続けています。 努力することの大切さを改めて教えてもらった言葉でした。 私たち保護者も、このことを肝に銘じて、子供とともに努力し続けて成長していきたいですね。 「学び合う学び」に学ぶ 〜学校評価アンケート編〜
学校HPに、先週実施された「学校評価アンケート」の結果が続々と掲載されています。
その中で「学び合う学び」に関する質問への結果が記事になっていましたね。(学校評価アンケート「学び合うシーン」 6/25) 結果の考察だけでなく、保護者から寄せられた意見に対しても、学校の見解が書かれていました。 「HPで拝見する学び合う学びは理想の形を現した一握りのグループであり、現実はいかされていない方が多いと思いました。」という意見は、学校にとっては少し厳しいものだろうと思います。 しかし、そういう厳しい意見もしっかり受け止めて、今後の授業へ活かしていこうとされている校長先生や学校の姿勢はすばらしいことだと思います。 この学校評価システムの導入にあたり、校長先生から次のようなお話がありました。 「背中についているゴミは自分では見つけられません。よりよい学校にするため、良いことばかりでなく、厳しいことでも、ぜひ忌憚のないご意見を聞かせて下さい」 ここに、保護者の意見を聞きたいという学校の本気が表れていると思います。 私たち保護者にとっても、この意見に対する学校の見解を知ることができたことは収穫だと思います。 意見を出して下さった方がいたからこそ、授業の内容によっては「学び合うシーン」を作ることが難しいということや、先生方もHPの記事を見ながら勉強している、ということなどがわかりました。 ありがとうございました。 まだまだ発展途上にある「学び合う学び」が、今後どのように成長していくのか、楽しみに見守りたいと思います。 雨上がりの兒の森@趣味'sブログ   「学び合う学び」に学ぶ 〜わかる編〜
テスト勉強をがんばる子供たちへ
テスト週間中の週末、生徒の皆さんは、テスト勉強の追い込みでがんばったことでしょうね。(と、親は信じたい) 授業中に、わかったようなわからないような・・・という中途半端な形でやり過ごしてきた問題が、いざテスト勉強を始めてみると、やっぱりわからない!という状況になっていませんか? 授業の中で、4人組になって話し合うとき、自分が納得できるまで、友達と意見を言い合っていますか? 時間がなくて、適当に話し合いを済ませてしまうこともあるかもしれませんね。 ほんとは自分はよくわからないのだけど、それをうまく説明できないので、まぁいいかと友達の意見に同調することもあるでしょう。 話し合いをするとき、どんなことに気を付けますか? 友達に自分の意見を伝える時、わかってもらおうと一生懸命説明しますね。「わからない」と言われたら、どうしたらわかってもらえるか、よく考えて、伝え方を変えてみたり、時には絵や図を書いたりして、わかりやすくなる工夫をしますね。 そして、友達の意見を聞く時、自分の意見と同じなのか違うのか、違うならどうしてそう思うのか等、考えながら聞くので真剣に聞きますよね。 そうやって、学んだことは頭の中に入れておく(インプット)だけでなく、発表する(アウトプット)ことで、理解が進む(身に付く)のだそうです。(By 校長先生) 授業中、話し合いの場、それ以外にも学校生活の中では、いろいろな「わかったようなわからないような」場面があると思います。 どうかそのままにせず、小さなことでも「わかった!」を増やしていってほしいと思います。 「安易にわかったふりをしないこと」・・・この言葉には、わかるまであきらめずにがんばってほしい、という先生方の想いが込められていると思います。 (学び合う学び 6/19) 大人になると、わからないことでも知ったかぶりをしてしまうことがよくあります。 恥ずかしくて「わかりません」と言えなくなってしまうのです。 「わからないので教えて下さい」と言うことは、そんなの簡単じゃんと思うでしょうが、見栄っ張りな私たち大人にはとても難しいことなのです。 その点、あなたたちは堂々と「わかりません」と言えるのですから、ぜひその特権を活かして下さいね。 「わかった!」を少しずつ増やして、皆さんが自信を持って期末テストに臨めるように応援しています。 梅雨を彩る花「アジサイ」@趣味'sブログ   新しいことを始めるよ 〜学習クラブ編〜
期末テストのテスト週間に入りました。
保護者の皆さん、お子さんのテスト勉強は、順調に進んでいますでしょうか? 子供たちは、自分でテスト勉強の計画を立てて、それに合わせて学習を進めているはずです。 かなり気になるところではありますが、あまり口うるさく言ってやる気を失ってもらっても困るので、時々「どう?順調に進んでる?」と声を掛けてあげましょうね。 優しい言葉掛けと温かい見守りが大切です。(By 校長先生+春風以化) ところで、学校で「学習クラブ」の活用が生徒にも広がったことを、ご存知ですか? 「学習クラブ」は、すでに先生方が活用されているシステムだそうですが、このテスト週間に合わせて、生徒も利用できるようにしていただいたとのことです。 (【生徒】学習クラブでプリント選択・出力 6/20) このシステムの良いところは、生徒自身が自分に必要な問題を選択して、プリントが作成できることでしょうね。 自分の苦手な教科の、さらに苦手な分野の問題を選択すれば、「自分用の苦手克服問題集」の出来上がりです。 解答や解説も一緒にプリントできるそうなので、わからない問題にじっくり取り組めそうです。 それでもわからなければ、どんどん先生に質問すればいいし、友達に聞くのもいいですね。 市販の問題集を買ってはみたものの、机の上で鎮座しているだけで、開けているところをみたことないわ・・・という経験を、多くの保護者が経験済みではないでしょうか? その点、この「学習クラブ」は無料ですし、気軽に利用できますよね。 せっかくこんなお得なシステムを、学校が生徒に開放して下さっているので、ぜひ「学習クラブって知ってる?利用してみたら?」とお子さんに声をかけてみてはいかがでしょうか? ただし、学年の利用日が決まっているようなので、お子さんに自分が利用できる日を確認させることをお忘れなく! 新緑もゆる「タカノツメ」@趣味'sブログ   「学校評価アンケート」の結果 〜PTA編〜 参加総数178名。初めての試みで、どうなるだろうか・・・と不安いっぱいでしたが、たくさんの保護者の皆さんにご協力いただき、感謝しています。 さて、PTA関連の質問への回答結果です。 ●PTAのホームページをご覧になられますか。【必須】 1. はい 36.0%(178件中64件) 2. いいえ 64.0%(178件中114件) ●(本日参加された方へ)PTAサロン(ミニミニ講演会)に参加されましたか。【非回答可 25件】 1. はい 15.2%(153件中27件) 2. いいえ 70.8%(153件中126件) ●(本日参加された方へ)リサイクル販売をご覧になりましたか。(未購入可)【非回答可 33件】 1. はい 18.5%(145件中33件) 2. いいえ 62.9%(145件中112件) ホームページについては、学校HPで校長先生がおっしゃっていたように、もっと閲覧数が増えるように、PTAとしても広報活動をしていきたいと思います。(学校評価アンケート(学校HP閲覧) 6/21) そして、保護者の皆さんが「見てみたいな」「こんなこと知りたいな」と思う記事が掲載できるように、保護者目線でがんばっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 新しいことを始めるよ「学校評価システム」にぜひご参加下さい 締切は今日(6/20)までなので、まだ参加されていない方は、ぜひご参加下さい。 質問は全部で10問、そのうち記述式の質問が2問あります。 最初の8問は選択式なので、簡単に回答ができます。 うち5問は回答が必須ですが、それ以外は自由回答なので、すべてに回答をしなくても参加できます。 学校は、保護者の皆さんからの率直な意見を求めていると思います。 学校の経営目標にある「学校の責任を果たし、学校・家庭・地域社会との連携を深める」(平成24年度 教育目標より)ということには、私たち保護者の意見を取り入れながら、よりよい学校づくりに活かす、という意味があると思っています。 そのためには、保護者が声をあげることが必要ですよね。 どんな小さなことでもよいので、まずは行動に移してみませんか? きっと、それを受け止めてくれる先生方が、校長先生をはじめ、小牧中にはたくさんいらっしゃいます。 最終的な締め切り時間のお知らせはありませんでしたが、本日中ならまだ間に合うはずです。 ぜひ、一人でも多くの保護者の皆さんのご参加を、お待ちしています。 【総務委員会】 ミニミニ講演会
6/18(月) PTAサロンと同時開催で、「ミニミニ講演会」を開催しました。
以前、このPTAの部屋のホームページでもお知らせしたように、今年度復活させた催しです。 記念すべき第1回には、 梶田先生(3年生学年主任) 岩田先生(教務主任) お二人の先生にご登場いただきました! どちらの先生も、普段あまりお話する機会のない先生ですので、皆さん興味津々でした。 お二人とも、ご自身のお子さんのお話を中心に、楽しいお話で、「先生といえども、我々と同じ親という立場になると、いろいろと悩みがあるものなのね〜」と、とても親近感を覚えました。 詳しいお話の内容は、ミニミニ講演会に参加していただいた方へのプレゼントなので、こちらでは書きませんが、お忙しい中ご協力いただいた先生方に深く感謝しています。 楽しい時間をありがとうございました。 次回のミニミニ講演会もお楽しみに!   【総務委員会】 PTAサロン
6/18(月) 学校公開日に合わせて、「PTAサロン」が開催されました。
PTAサロンはいつもどおり図書館での開催でした。 開始直後は、保護者の皆さんはリサイクル販売へ行ってみえたようで、図書館は準備役の総務委員ばかりという状況でしたが、「ミニミニ講演会」が始まると、どんどん人出が増えて、最後は大盛況でした。 こちらも、広報委員さんが取材して下さいましたので、取材日記をご紹介します。 −−−−− PTAサロンでは、先生の「ミニミニ講演会」も開催され、とても和やかな雰囲気の中、沢山の参加がありました。 お菓子や飲み物も用意され、日頃忙しい保護者の方々が情報交換をしたりと、話に花を咲かせ、楽しい時間を過ごされていました。 −−−−− 校区の小学校が代休だったこともあり、小学生を連れてみえた保護者の方にも、とても好評でした。 多くの保護者の方に足を運んでいただき、ありがとうございました。    読書のすすめ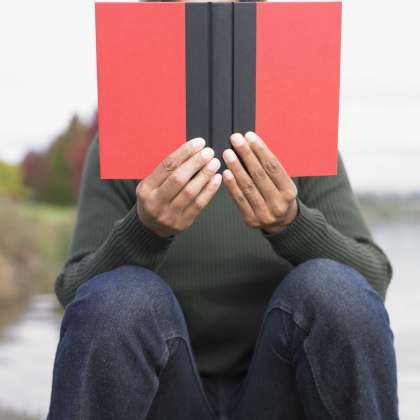 (読書月間によせて 6/7) 朝の牧中タイムを使って、みんな静かに読書をしています。 読む本は、マンガと雑誌以外であればとくに指定がないので、各自が好きな本を読んでいます。 最近は、多くの小中学校で、「朝の読書の時間」を設けて、子供の読書の習慣付けを行っているそうです。 先日、小牧市立図書館長さんのお話を伺う機会がありました。 小牧市は、図書館関連事業に対して、長年力を入れてきたそうで、これは学校HPの記事にもあったとおりです。 ご存じのように、ラピオ内にできた「えほん図書館」はとても好評で、市外の利用者も多いとのことでした。 また、新図書館建設については、今年度中には方向性が見えてくるのではないかというお話でした。実際に計画が動き出すのは、まだ先のようです。 図書館の現状についてのお話の中で、印象に残ったのは、「若年層(10〜20代)の図書館利用率が低い」ということでした。 これは全国的な傾向で、図書館側も若者の取り込みについて、いろいろ知恵を絞っているところです、というお話でした。 たしかに、仲間と集まってワイワイやりたい年頃なので、静かに読書を楽しむ雰囲気には馴染めないかもしれませんね。 そういった中でも、小牧中の図書館の利用率が高いということは、とても誇らしいことです。 冨田先生をはじめとした先生方の取り組み、図書委員のがんばり、図書ボランティアさんの協力、みんなの力が合わさった結果であり、感謝の気持ちでいっぱいです。 これからもHPの「図書館」のページは、要チェックですね。 さて、保護者の皆さん。 皆さんには、読書の習慣がありますか? 親が読書をする家庭の子供は、読書の習慣が身に付いていることが多いそうです。「親の背を見て、子は育つ」ということですね。 今からでも遅くありません。私たちも、子供と一緒に、読書を楽しんでみませんか? ABCDの原則 〜交通ルール編・再び〜 (【教職員】地域からのメールも即共有化 6/14) そのメールの内容に、とても悲しくなりました。 今週初めに、2年生の先生方とPTAの生徒指導委員さんが、朝の登校指導をして下さったばかりなのに・・・ 生徒の登下校時のマナーが悪いということについては、以前もPTAの部屋で記事にしました。そこでは、「他人に迷惑をかけないように、節度と少しの気遣いを持って、元気に登下校してほしいと願っています」と保護者の思いを書きました。 (ABCDの原則 〜交通ルール編〜 5/8) 残念ながら、子供たちに自覚を持たせることは、一朝一夕でできることではありません。 しかし、交通ルールを守ることは、社会の中で生きていく上で、とても重要なことです。 何度も何度も繰り返し伝えていくしかありませんが、先生方や私たち保護者が力を合わせて、みんなで見守っていきましょう。 今回のメールの件を受けて、とくに感じたことは「命を守る」ということです。 前回の記事では「地域の方に迷惑をかけないことの自覚を持ってほしい」ということを書きましたが、それ以外にもとても大切なことに「命を守る」ということがあります。 ABCDの原則で交通ルールを守る = 自分の命を守る このことを忘れないでほしいと、心から願っています。 今一度、交通ルールのABCDの原則について、親子で考えてみませんか? 新しいことを始めるよ 〜学校評価システム編〜 どこの学校でも、いろいろな方法で実施されています。 その目的は、校長先生がコメントされていたように、学校に対しての保護者の意見を聞くことで、問題点や要望を把握し、学校運営に反映させていくことにあります。 (携帯電話等を活用した学校評価を始めます 6/13) 昨年までは、2学期末の個人懇談の時に、廊下にアンケート用紙が置いてあり、「待ち時間に記入していただき、備え付けの封筒に入れて下さい」というスタイルでした。 設問数が多かったので、書くのにけっこう時間がかかりましたね。 その後、回収されたアンケートがどうなったかというのは、校長先生の記事のように、たいへんな労力をかけてまとめられていたわけですが、アンケート結果のまとめってもらったっけ?どうなったんだっけ?という方がほとんどではないでしょうか? 実際には、結果のまとめは配布されているはずですが、忘れたころにやってくるために、あまり関心も持てずによく見ないままになってしまうことが多いですよね。 これは、とてももったいないことだと思います。 せっかくのアンケートですから、我々保護者がもっと関心を持てるように、有効に活用してほしい!そのためには、アンケートに関する一連の流れへの素早い対応が一番でしょう。 今回、新たに始まる、携帯電話などを利用した学校評価アンケートは、学校と保護者の双方にメリットがあるように思います。 気付いたこと、良かったこと、苦言、提言・・・私たち保護者は、学校に対していろいろな思いがあります。 わざわざ電話をするほどでもないし、気軽に知らせる手段があればいいのに、という思いは、多くの保護者の方々がお持ちなのではないでしょうか? 今回の評価システムは、そんな思いに応えてくれそうな気がします。 メールやネットを使うような感覚で、簡単に参加できます。 ぜひ、多くの保護者の皆さんに参加していただいて、保護者の思いを伝える機会にしていただきたいと願っています。 PTAでも、このチャンスに便乗して、PTA活動についての質問項目をアンケートに入れていただくことを企画しています。 こちらの方もご協力をよろしくお願いします。 「ミニミニ講演会」のおはなし
6/18(月)は、学校公開日です。
この日、PTAでは総務委員会が「PTAサロン」、保健委員会が「リサイクル販売」を開催します。 授業参観が始まる前に、たくさんの保護者の方にお立ち寄りいただき、毎回好評のサロンとリサイクル販売ですが、今回は別会場での開催になりました。 PTAサロンは図書館、リサイクル販売は多目的室での開催となりますので、ぜひ両方に足を運んでいただきたいと思います。 そして、今回は新しい試みとして「ミニミニ講演会」を開催することになりました。 実は、この「ミニミニ講演会」は数年前まで、小牧中で開催されていたそうです。 いろいろな先生が参加され、先生の人柄がよくわかるととても好評だったと校長先生からお聞きし、これを復活させようということになりました。 今年度、学校ホームページがリニューアルされて、学校の教育方針を始め、目指している学校の姿や、日々の取り組み、生徒の姿など、いろいろな情報が提供されるようになりました。 私たち保護者にとって、学校の考え方や、子供たちの様子がよくわかるホームページは、とてもありがたく、安心につながっています。 PTAでも、学校の取り組みをフォローしながら、保護者として望むことを発信していきたいと考えています。 学校公開に際して、たくさんの方々に学校へ来ていただきたいという思いが、学校にはあります。 百聞は一見に如かずの言葉どおり、生の学校の様子を見てもらうことで伝わることがたくさんあるからです。 私たち保護者も、知りたいことはたくさんありますよね。 中学生ともなると、学校の話はあまりしてくれなくなりますし、先生についても、担任の先生くらいしか直接お話しする機会はありません。 学校にはたくさんの先生がいます。せっかく学校へ行くのだから、直接先生とお話しする機会を作ろうということで、今回の復活になったわけです。 「今日、学校で◯◯先生の話を聞いてきたよ〜。あの先生、面白いね〜」といった感じで、子供と学校の話をするキッカケ作りになるとうれしいなと思っています。 多くの方々にご参加いただきたいので、PTAサロンと同時開催で、図書館で行います。 どの先生に来ていただけるのかは、当日のお楽しみです。 ぜひ図書館を覗いてみて下さいね。 兒の森で自生しているササユリが満開です。自然の中で咲く美しい花を守るために、たくさんの方々の温かい見守りがあります。@趣味'sブログ    6/9 第2回 総務委員会
6/9(土) 第2回総務委員会が開催されました。
今日は、英検の試験が行われていたため、多目的ホールでの開催となりました。 玄関前のイングリッシュガーデンの周りでは、ジュニア奉仕団の皆さんが草刈りなどの整備を行って下さっていて、作業後にはとてもきれいになっていました。 世話人の皆さん、先生方、そして奉仕団の生徒の皆さん、ありがとうございました。 ● 協議事項 1. 6/18(月) 学校公開日について 当日の役割分担について(PTAサロン、受付など)、「ミニミニ講演会」の説明 ※ミニミニ講演会については、後日記事にします。 2. 各委員会の活動報告 前回の委員会以降の活動報告と、今後の活動予定についての確認 3. 連絡事項 (1) 9/8(土) 父母と教師のつどいの動員について 専門委員会で参加の呼びかけをしていただきました。 (2) 「親子で学ぶ 夜の小牧中学校」について 先日行われた「新しいことを始めるよ戦略会議」にて、校長先生よりご提案のあった企画が、ついに動き出しました。 詳しい内容については、後日ご案内します。  教育実習生へのエール 慣れない実習で、毎日緊張の連続でしょうが、がんばっていることと思います。 学校HPで紹介されたスピーチは、これから教師を目指してがんばろうという気持ちが表れていて、とてもうれしく思いました。 (今朝の教育実習生スピーチに拍手 6/6) 実習生の皆さんは、おそらく「教師を目指すきっかけになった先生との出会い」を経験していることでしょう。 教師という職業は、以前このPTAの部屋でも記事にしましたが、とても厳しい職業です。 それは実習中に先生方の働きぶりを身近に見て、実感できたのではないでしょうか。 しかし、教師にしか感じることができない達成感や満足感があることも、実感できたことでしょう。 いつか、自分がそうだったように、誰かに「○○先生のような先生になりたい」と憧れてもらえる素敵な先生になって、また学校に戻ってきてもらいたいと心から願っています。 実習生のスピーチにあったように、学生であっても、生徒からは「先生」と呼ばれます。 これは本人にとっては、少しこそばゆい思いと同時に、とてもプレッシャーのかかることだと思います。 私たちが親になった時のことを思い出してみてください。 子供が生まれると同時に、私たちは「お父さん」「お母さん」と呼ばれるようになりました。 とくに初めての子育てのときは、こう呼ばれることがプレッシャーに感じたものです。 とにかく何もかも初めての経験で、どうしたらいいかなんて、まるっきりわからず、すべてが手探りでしたよね。 でも、「育児は育自、子育ては親育て」という言葉のように、子供と一緒に少しずつ親になってきたように思います。 先生も同じです。実習生でも、新任でも、学校では「先生」と呼ばれます。でも、最初から何でもできるわけではありませんし、足りないことだらけです。 私たちの子育てを周りの人々がサポートしてくれたように、若い先生のことをベテランの先生方が支え、子供たちが育てていってくれます。 私たち保護者も、温かい見守りで、先生の育ちを支えていきたいですね。 外国籍の子供への支援のおはなし 私たちが子供のころ、身近に外国人がいることは、ほとんどありませんでした。 しかし、今は違います。 小牧は工業が盛んで、大きな工場がたくさんあることから、外国人が多く住んでいます。 今では、外国人はとても身近なところで、私たちと同じように生活していて、多くの子供たちが学校へ通っています。 生まれた時から日本に住んでいる場合は問題ないでしょうが、やはり言葉のカベは、子供にとっても大きな問題になるでしょう。 日本語を話したり、読んだり、書いたりということができなければ、学校の授業もちんぷんかんぷんで、ほんとに困るだろうと思います。 そんな中、学校では特別指導の体制を整えている、という記事に、安心しました。 ただでさえ多忙な先生方なので、十分な支援体制を取ることは難しいことだろうと思いますが、それでも個々の学習計画を立てて実施して下さっているということには頭が下がる思いです。 先日、ある会議で「不登校児童や生徒の中には、外国籍の子供が少なからず、います」というお話を伺いました。 子供が学校へ行かなくなってしまうのは、言葉のカベだけでなく、習慣の違い、文化の違い、家庭の事情など、いろいろな要因があるのだろうとは思います。 でも学校が支援の手を差し延べてくれることで、元気に学校へ通える子は、きっといます。 支援の充実は難しいかもしれませんが、できる範囲でこういった取り組みを続けていっていただきたいと思います。 こうした支援は、子供たちだけに行われているわけではありません。保護者の方へも行われています。 入学説明会のとき、個人懇談のとき、保護者が学校でお話を聞かなければならない時は、通訳の方に来ていただいて対応しています。 これは市が援助してくれていることですが、このように親子ともに支援が行われているということを、ぜひ皆さんに知っていただきたいです。 学校は、楽しい場所です。たくさんの子供たちが、学校で学ぶ機会を持てるように・・・これが我々大人の願いですよね。 見守りのかたち 〜ほめる編〜
先日の学校HPに掲載された、生徒指導主事の先生のコメントはご覧になりましたか?
(4・5月を振り返って(生徒指導主事) 6/1) ほめることはとても大切なことだと思います。「子供はほめて育てましょう」という話はよく聞きますね。 最近、「子供のほめ方がわからない」という声を聞くことがあります。そういう方は、自分がほめられた経験が少なく、ほめたくてもどうやって言葉をかけたらいいのかわからない状態のようです。 先生のコメント中に、 「人の悪い面はすぐに目につくものですが、いい面を見つけるためには、常日頃そういう目で生徒を見ていなければ、なかなか難しいことだと思います。そんな目で生徒たちを見つめていきましょう。」 という言葉がありますが、まさにそうだと思いませんか? ダメな点、足りない点というマイナスな面は、ほんとにすぐに目につきます。 親であれば誰でも、子供のそういう面にばかり目がいって、ついつい注意してしまうことが日常茶飯事ですね。 そんなマイナス面は、ほんとは子供自身もよくわかっているので、そこを突かれると「わかってるのにうるさいな!」という気持ちになるのは当然でしょう。 たしかに、何度も言わなければ身に付かないことはあります。 でもそこを少し我慢して、子供を信頼してみませんか? そして、良い面を見つけるために、そっと見守る気持ちを持ってみませんか? 私たち保護者にも「いいとこ見つけ」の練習が必要かもしれませんね。 「ほめてあげたいな」という気持ちで、子供たちを見ていると、きっと「ほめポイント」が見えてくると思います。 それを見つけたときは、素直に「よくがんばったね」「えらいね」「すごいね」と声をかけてあげて下さい。 特別な言葉でなくても、きっと想いは伝わりますから。 そして、いつも見守っているよというメッセージも伝わるはずです。 先生方の「やさしい見守りのかたち」に感謝しつつ、私たちも「親としての見守りのかたち」について考えていきたいですね。 初夏の花です。「ゼニアオイ」@趣味'sブログ   |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |