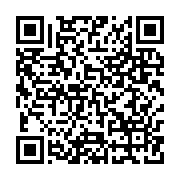|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:10 総数:156329 |
【市P連】県P連 母親代表・役員・理事合同研修会
8/7(火)愛知県小中学校PTA連絡協議会主催の、平成24年度母親代表・役員・理事合同研修会が、愛知県教育会館で開催され、参加しました。
県内から各郡市P連母親代表と役員、県P連の役員と理事が参加しての研修会です。 暑い中、大勢が集まり、講演を聞きました。 ●演題 「ケータイ&スマートフォン、これくらいは知っておこう!」 〜デジタル社会を健やかに生きる子供を育むために〜 ●講師 ネット教育アナリスト 尾花紀子氏 我々が子供だったころは、アナログな時代でした。 しかし、今の子供たちが生きる時代は、デジタルが当たり前の時代になります。 そんな中で、子供たちは、我々にはない斬新な発想や感覚で、新たなビジネススタイルや仕組みを作り出しています。 ケータイ、パソコン、スマホ・・・すっかり我々の生活に取り込まれて、今ではなくてはならないツールになりました。 子供たちは、これらのツールをどんどん使いこなし、活用してます。 このようになくてはならないツールだからこそ、正しく使ってほしい、というのはすべての保護者の思いですね。 正しい使い方というのは「情報モラル」と呼ばれており、小中学校でも学習指導要領の改訂に伴い、情報モラルに関する授業を行うことになりました。 小牧中学校でも、1学期に愛知県警サイバー犯罪対策課の梅村さんをお招きして、講座を開催しています。 (サイバー犯罪防止講座 7/18) (愛知県警サイバー犯罪対策課・梅村さんから学ぶ 7/23) 子供たちは、このような講座を通じて、「安易に使うと危険な目に遭うこともある」という認識を、少なからず持ってくれていると思います。 しかし、やはりそこはまだ子供です。 楽しいことにはどんどんはまっていくし、楽な方にどんどん流されていってしまいます。 そこをしっかり見守って、正しい方向へ導いてやるのが、保護者であり、先生であり、我々大人の役目だと思うのです。 今日のお話しの中でも、「ケータイを持たせるかどうかをきっかけに、親子でいろいろな話をして下さい」というアドバイスがありました。 親子で話し合いながら、「うちのルール」を作っていけるといいですね。 今日の講演では、デジタル社会の現状から、子供たちのケータイ事情、子供にケータイを持たせるときにどのようなことに注意したらよいか等々、とても役に立つ情報を教えていただきました。 今後、いくつかの記事にまとめて、順次アップしていきたいと思っていますので、お楽しみ。  新しいことが始まりました!〜親子で学ぶ夜の小牧中学校編〜
5月の終わりの「新しいことを始めるよ戦略会議」から生まれた新企画がついに始まりました!
(第1回親子で学ぶ夜の小牧中学校 8/5) 暑い中でしたが、予想以上に多くの方々に参加していただき、とても楽しく有意義な時間を過ごすことができました。 むちゃなお願いを快く引き受けて下さった桂紅雀さん(師匠とお呼びしたいところですが、ご本人が固辞されますので) この企画の生みの親である玉置校長先生 事前準備から会場の設営と当日もキビキビと動いていただいた教頭先生、岩田先生、林本先生 そして会を盛り上げて下さったPTA役員の皆さん すべての方々のおかげで、「夜の学校」がすばらしいスタートを切れたことを、心から感謝したいと思います。 昨夜は、初めて落語を聞くという方がほとんどでした。 ライブの良さがいかんなく発揮され、笑って、笑って、とても楽しく落語を堪能させてもらいました。 流れる汗、細やかに変化する表情、声の張り・・・ライブだからこそ感じられる一体感でした。 紅雀さんのポリシーは「人物を描く」ということだそうです。 話を聞いただけで、その情景が思い描ける。登場人物が思い浮かんで、動きが見える。そんな落語を心がけているそうです。 なるほど、紅雀さんの落語を聴いていると、うどん屋さんのお店の様子や、おいしそうにうどんをすする様子、湯気が立つできたてのうどんが見えてきます。 そうやって、知らず知らずのうちに紅雀ワールドに引き込まれていきました。 そして、昨夜は、子供たちもたくさん参加してくれました。 終わったあと「どうだった?」と聞いてみました。 うれしいことに「おもしろかった。落語って、ほんとにその情景が見えるんだね」という答えが返ってきました。 紅雀さんが、子供たちにもわかるようにと心を砕いてお話して下さったおかげで、こうして落語の楽しさが伝わったようです。 おそらく、みんなに見えていたうどん屋さんの情景は、大人と子供では違うものだろうと思います。 そういう想像力は、今まで見てきたもの、聞いてきたものによって変わってくることでしょう。 子供たちには、これからもいろんな経験をして、想像力の引き出しにいっぱいのピースを詰めていってほしいなと願っています。    【市P連】母と女性教職員の会 全国集会(3)
2日目は、分科会が開催されました。
全15分科会の中から、参加希望の分科会が選べます。 それぞれの分科会では、問題提起の発表があり、それについての様々な討議が行われ、教員と保護者という立場の違う人々が一緒に学びました。 【分科会一覧】 1. 乳幼児期から学童期の子育て 2. 小学生 3. 中・高生 4. いじめ・不登校 5. 性と生 6. 障害児の共生・共学 7. ジェンダー平等 8. 健康の問題 9. 食の問題 10. これからの教育 11. 社会保障 12. 平和 13. 環境 14. 女性労働 15. 母と女性教職員が手を結ぶ運動 2日間の集会に参加して思ったことは、「先生方はよく勉強していらっしゃるな」ということでした。 日々の多忙な業務をこなしながら、いろいろな研修会に参加されていて、常に新しいことに取り組む意欲を持っていらっしゃることが、討議を聞いていて感じられました。 最近、大津市のいじめ問題に関連して、先生の資質について議論されているのを、目にすることがよくあります。 一部の心ない教師がクローズアップされて、あたかも教師全体がそうであるかのような議論になることに対しては、注意して見ていかなければならないと思います。 少なくとも、我々のまわりにいる、多くの先生方は、教育に志を持って取り組まれている人がほとんどです。 無用な誤解を生まないためにも、学校はもっと開かれるべきですね。 学校の現状や、今取り組んでいること、こんな生徒を育てたいという方針などを、どんどん発信してほしいと思います。 私たち保護者も、学校に任せきりにしないで、子供を通して、学校を知る努力を忘れずにいたいですね。  【市P連】母と女性教職員の会 全国集会(2)
●8/1 全体会 その2
「原発災害と復興へのビジョン」と題して、鈴木浩先生(福島大学名誉教授、明治大学客員教授、元福島県復興ビジョン検討委員会座長)の講演がありました。 1. 東日本大震災とその時代的特質 2. 復興に向けての現状と課題 3. 復興政策に関わるガバナンスの問題点と課題 4. 復興へのビジョン 5. 浪江町復興計画策定に関わって 6. あらためて地域再生に向けて 今回の大震災は、日本が抱える様々な問題が浮き彫りになった災害でした。 疲弊する地方経済、機能しない政治、社会保障への不安など、今までは漠然とした不安として感じていたことが、現実として突きつけられました。 講演の中で、それぞれの問題の現状と課題についてのお話しがありました。 いろいろな人たちがいろいろな提言をしているのに、どうしてすぐに実行できないのかと、もどかしい思いを抱えている様子がよくわかりました。 こうした社会問題に関する話題は、難しくてわからないからと敬遠しがちですが、私たち大人は、もっと自分自身のこととして受け止めて、考えていく必要があるなと思いました。 このまま問題を先送りしていては、結局子供たちにそのツケを押しつけることになってしまいます。 まずは、関心を持って、いろいろな人の考えや意見を聞くことから始めてみようと思います。  【市P連】母と女性教職員の会 全国集会(1)
8/1(水)、2(木)日本教職員組合主催の「母と女性教職員の会 全国集会」が東京で開催されました。
小牧からは、小牧市教員組合の女性部長の先生と、市P連母親委員長の2名で参加しました。 愛知県下の各ブロックごとに、女性の先生と母親代表の方々が集合し、移動の新幹線の車中は、1両の3分の2ほどの大人数で、にぎやかな道中となりました。 2日間にわたるプログラムは、1日目に全体会、2日目に分科会となっていて、盛りだくさんの内容でした。 ●8/1 全体会 さすが全国集会というだけあって、会場が満員御礼になるほど、たくさんの人々が集まりました。 開会行事では、昨年の東日本大震災を受けて、被災地からの報告がありました。 時間が経つにつれ、被災地の現状の報道が少なくなっています。 今回の報告は、日々の生活に追われる中で、ついつい被災地に心を寄せる余裕がなくなっていることに気づかせてくれました。 まだ多くの行方不明者がいて、たくさんの子供たちが仮設住宅に暮らし、不自由な生活を強いられています。 また、原子力発電所の事故のために、避難を余儀なくされ、除染がなかなか進まない中、家に閉じこもりがちな子供たちがたくさんいます。 先が見えない生活は、さぞ不安なことでしょう。 スライドで紹介された子供たちの笑顔を見ていると、せつなくて、やり切れない気持ちでいっぱいになりました。 私たちに何ができるのだろうか・・・考えても、簡単に答えが見つかる問題ではありません。 報告を聞く中で、強く思ったことは「忘れてはいけない」ということでした。 私たちが直接手助けできることは、何もないかもしれません。 しかし、いつも心の中に被災地のことを思う気持ち、そこに生きる子供たちを思う気持ちを持ち続けることはできます。 そして、家庭で、学校で、地域で、被災地のことを話題にすることで、ひとりでも多くの人々の心の中に「想い」を持ち続けてもらえるようなきっかけを作ることはできます。 保護者の皆さん、ぜひお子さんと、ご家族と、地震や津波のこと、原発や放射能のこと、いろいろな話をしてみませんか?  |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
||||||||||