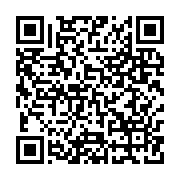|
最新更新日:2024/06/08 |
|
本日: 昨日:12 総数:156422 |
【教養】社会見学 その3
最後の目的地は、安城デンパークです。
ここでは色とりどりの花が咲いていて、美しい庭園を散策できるはずでしたが、雨脚が強まり、残念ですが室内の見学のみとなりました。 デンパークでのメインイベントは、フラワー工作です。 誰でも簡単に製作できるように、必要な材料がキットになっていて、係の方の説明を聞いたあと、皆さん真剣な表情でフラワーポットを製作しました。 皆さんの作品は、文化祭のPTA作品展に出品されますので、お楽しみに。 皆さんのご協力のおかげで、無事に一日の日程を終えることができました。 また教養委員の皆さん方は、事前の準備から当日までご苦労さまでした。 参加していただいた皆さま、一日ありがとうございました。    【教養】社会見学 その2
ほどよくお腹もすいてきて、次はお待ちかねの昼食です。
岡崎城近くの、岡崎ニューグランドホテルへ移動しました。 メイン料理は、ポーク、チキン、魚の3種類から選び、他はバイキングでたくさんの種類の料理を堪能しました。 残念ながら雨が降っていましたが、窓の外には岡崎城が見える素晴らしいロケーションのレストランで、おいしい料理をいただきながら、楽しいおしゃべりに花が咲きました。   【教養】社会見学 その1
7/12(木)教養委員会主催の社会見学が行われました。
朝から雨が降ったり止んだりのはっきりしない天気の中、総勢33名で小牧中を出発しました。 途中、高速道路出口での渋滞もあり、予定時間よりも少し遅くなりましたが、まずは最初の目的地「岡崎八丁味噌の郷カクキュー」に到着です。 八丁味噌は、徳川家康の生誕地である岡崎城より西へ八丁(約870m)にある八帖町(旧八丁村)にある2社のみで生産されている味噌の商標だそうです。 愛知県のグルメとして全国で有名な八丁味噌が、2社だけの商標だということはあまり知られていないことですね。 史料館の見学後、味噌汁の試飲、味噌田楽の試食をいただきました。どちらもとてもおいしく、皆さんがおみやげに味噌を購入していました。    【生徒指導】朝の登校指導
7/10(火)生徒指導委員会では、3年生の先生方と一緒に、朝の登校指導を実施しました。
今回は、 1. 小牧市民病院北バス停 2. 小牧高校北大輪会館前 3. 学生服のイトウ の3か所で行いました。 写真は、学生服のイトウ前での様子です。 この通学路は、自転車通学の生徒が多く利用するため、指導時間(7:30〜7:50)よりも前に登校しているようで、当番が立っている間には、あまり生徒が通らず、少しさみしい写真になっています。 このように、実際に活動してみると、場所により、通学の様子が違うことがわかりました。 これらの経験を、今後や来年度の活動に活かしていきたいと思います。 当番の皆さん、3年生の先生方、どうもありがとうございました。   フラワーアレンジメント活動報告
7/7(土)フラワーアレンジメントの活動がありました。
隣の応接室では、広報委員会のデジカメ講座が開催されており、途中、撮影練習のために広報委員がお邪魔して、素敵なクラブ員の皆さんに被写体になっていただきました。 クラブ員の皆さん、ありがとうございました。    【広報】デジカメ講座
7/7(土)広報委員会では、「デジカメ講座」を応接室で行いました。
吉田写真館の吉田さんを講師にお招きして、デジカメできれいに写真を撮るコツを教えていただきました。 吉田写真館さんは、今年度の小牧中学校の記録写真の撮影を担当して下さっています。 3年生の卒業アルバム撮影では、学校HPでも記事になっていましたね。どんな仕上がりか、今から楽しみです。(卒業アルバム個人写真撮影 5/29) さて、皆さんは、デジカメで写真を撮る時、被写体に合わせて撮影モードを変えていますか? 多くの方は、普通にオートフォーカスの標準モードで撮影されているのではないでしょうか? 講座の参加者も、撮影モードがいろいろあることすら知らなかったり、知っていても、どうやって使えばいいのかわかりません、という状態でした。 そこで、実際に、花や人物を撮影しながら、カメラの操作方法やフラッシュの使い方などを、丁寧に教えていただきました。 参加者からは、実際に自分のカメラを使って教えてもらえたので、とてもわかりやすかったと、感謝の感想がたくさん出ていました。 役に立つ講座の内容をいくつかご紹介します。 ●室内で静物を撮影する場合 花や料理などを撮影する場合は、全体像を撮るだけでなく、接写モードで一部をアップにすると立体感が出てきれいな写真が撮れます。 この時、フラッシュは使わない方がいいです。フラッシュの光は強いので、陰影が失われて、平面的な写真になってしまいます。 接写モードにすると自動的にフラッシュが発光する設定になる場合は、発光禁止に設定しましょう。 手ブレ防止のため、両脇を締めて、なるべくカメラを固定させるようにして撮影しましょう。 三脚を使うのがベストです。 ●フラッシュの使い方 逆光で撮影する場合は、必ずフラッシュを使いましょう。 フラッシュの光が届く範囲は、約1mです。遠すぎると光が届かず、近すぎると光が強すぎて白くなってしまいます。適度な距離が必要です。 ●望遠機能について 遠くのモノを撮影する時、よく望遠機能を使います。 しかし望遠で撮影すると手ブレが起きやすくなります。 また望遠モードにするとき、一旦レンズが止まるポイントがあり、さらに動かすと最大までレンズが動くようになっています。 望遠で撮影する時は、一旦レンズが止まるポイントまでにしておく方が良いそうです。 最大まで動かしてしまうと、手ブレしやすく、ピントが合っていない写真になってしまうことが多いそうです。 ●動く被写体を撮影する場合 運動会などで、走る我が子を撮影しようとして、いつも失敗してしまう…という経験ありますよね。 デジカメでは難しいというお話でしたが、挑戦するなら、まずは子どもの動きに合わせてカメラを移動させないこと、だそうです。 撮影するポイントをあらかじめ決めておいて、その場所にピントを合わせておきます。 デジカメのシャッターを半押しにすればピントが合うので、そのまま待機して、通過する瞬間に全押しします。 うまく撮影するには、かなりの練習が必要ですね。 今回の講座で、コツをつかんだ広報委員さんたちの、今後の取材活動にご期待下さい!    「親子で学ぶ夜の小牧中学校」誕生のおはなし 親子で学ぶ夜の小牧中学校をやりたいのです。 えっ?夜?そんなことやってもいいの? 出席者の目には、たくさんの「?」が浮かんでいたと思います。 そんな出席者を前に、校長先生がおっしゃいました。 「ふだんの学校で教えられないようなことを、学校で教えたい。子供だけでなく、大人も一緒に学んでほしい」 「親(大人)が学ぶ姿は、子供たちにきっと好影響を与えます」 「親(大人)がとんでもない質問をすることで、子供は大人だって知らないことがあるんだ。こんなこと聞いてもいいんだと気が楽になります」 なるほど、これはおもしろそう! 出席者は一気にこの提案に引き寄せられました。 考えてみると、中学生になってから、親子で何かを学ぶ機会なんてなかったなぁ。 そもそも共通の話題を探すのがたいへんで、以前のように気軽に話をしてくれることもあまりないし・・・ これは、親子のきっかけ作りに役立ちそう。 それに、講座の内容がとにかくおもしろそう! これなら、大人が楽しめる内容だし、子供がいなくても、地域の人たちも呼んだらいいんじゃない? よ〜し、やりましょう! あっという間に開催決定です。 その後は、すぐに日程と講師の調整へと進んでいき、とんとん拍子に全体像が決まりました。 全5回を予定していますが、講師の先生方は、すべて校長先生の幅広い人脈を駆使してお願いした超一流の方ばかりです。 子供に負けじと、大人も楽しく学びましょう! 実は、校長先生には、隠された目論見があるようです。 この講座を通じて、キャリア教育までやっちゃおうということも考えておられるようです。 第1回目は落語家さんですが、それ以外にも大学教授やコラムニスト、講談師など、多彩な職業の方々が登場して下さいます。 それぞれの方がご自身の仕事に誇りを持っておられるので、そのお話しを伺うことは、子供たちにとって、自分の将来について考えるきっかけになるのではないでしょうか。 この貴重な機会を、親子ともども有意義に活用してみませんか? 大人も子供も、たくさんの皆さんにご参加いただきたいなと思います。 「親子で学ぶ夜の小牧中学校」へのお誘い テレビなどでご覧になったことはあるかもしれませんが、よほどお好きな方でなければ、生でご覧になることはないのではないでしょうか? テレビのバラエティ番組に出演している落語家さんたちは、知識も豊富で、お話するのがとても上手です。 若手の落語家さんたちの講演や独演会などは、最近若い女性もたくさん足を運んでいるようです。 元々庶民の娯楽として盛んだった落語ですが、最近人気が出てきているとはいえ、なんとなく敷居が高く感じてしまうことがありませんか? わざわざ出かけて行くほど興味ないし…という方がほとんどですよね。 そんな皆さんに、朗報です! なんと、来月、小牧中学校に、本物の落語家さんがきて下さいます。 「親子で学ぶ夜の小牧中学校」の第1回目の講師として、桂紅雀師匠をお迎えします。 桂紅雀師匠は、あの桂枝雀師匠のお弟子さんで、若手の実力派として関西では有名な落語家さんだそうです。 そんなスゴイ方の落語が、生で無料で堪能できるなんて、本当にスゴイことなんです。 8/5(日) 午後7時〜8時30分 多目的ホールにて開催されます。 小牧中の保護者だけでなく、地域の方や、市外の方でも、どなたでも自由にご参加いただけますので、ぜひお誘い合わせの上お越し下さいね。 詳しい内容は、こちらの<a href="突然ですが、皆さんは、落語を生で見たことがありますか? テレビなどでご覧になったことはあるかもしれませんが、よほどお好きな方でなければ、生でご覧になることはないのではないでしょうか? テレビのバラエティ番組に出演している落語家さんたちは、知識も豊富で、お話するのがとても上手です。 若手の落語家さんたちの講演や独演会などは、最近若い女性もたくさん足を運んでいるようです。 元々庶民の娯楽として盛んだった落語ですが、最近人気が出てきているとはいえ、なんとなく敷居が高く感じてしまうことがありませんか? わざわざ出かけて行くほど興味ないし…という方がほとんどですよね。 そんな皆さんに、朗報です! なんと、来月、小牧中学校に、本物の落語家さんがきて下さいます。 「親子で学ぶ夜の小牧中学校」の第1回目の講師として、<b>桂紅雀師匠</b>をお迎えします。 桂紅雀師匠は、あの桂枝雀師匠のお弟子さんで、若手の実力派として関西では有名な落語家さんだそうです。 そんなスゴイ方の落語が、生で無料で堪能できるなんて、本当にスゴイことなんです。 8/5(日) 午後7時〜8時30分 多目的ホールにて開催されます。 小牧中の保護者だけでなく、地域の方や、市外の方でも、どなたでも自由にご参加いただけますので、ぜひお誘い合わせの上お越し下さいね。 詳しい内容は、こちらの<swa:ContentLink type="doc" item="10299">チラシ</swa:ContentLink>をご覧下さい。 先生と子供たちへの応援メッセージ 3年生は最後の大会になるので、悔いのないように持てる力を存分に発揮してほしいと願っています。 努力の成果は加速度的に現れると信じて。 この時期、先生方は、超多忙です。 期末テストの採点をし、成績を付け、通知表の作成をしなければなりません。 さらに、部活動の指導、学期末のいろいろな書類作成、そして3年生の担任の先生方は進路関係の仕事も加わります。 職員室の電気は、毎日遅くまで着いています。 本当に頭が下がる思いです。ありがとうございます。 先日、夏の大会に向けてがんばる子供たちの記事が、学校HPに掲載されました。 (夏の戦いに向かう1 7/4)(夏の戦いに向かう2 7/4)(夏の戦いに向かう3 7/4) 実は、先日実施した「学校評価アンケート」に、こんなコメントが寄せられていたそうなのです。 部活動の記事をもっと載せてほしい どの部活も、顧問の先生方は一生懸命指導して下さっていますし、子供たちも真剣に取り組んでいます。 しかし、先生方は、写真を撮って記事を書く時間の余裕がないのが現状なのです。 それでも、保護者からの要望に応えようと、校長先生が忙しい時間を縫って、あの記事を掲載して下さいました。 こうして、保護者の皆さんへ、子供たちのがんばる姿を届けていただきました。 先生方、いつも本当にありがとうございます。 がんばる先生と子供たちに、保護者からの応援の気持ちが届きますように。 【広報】第3回編集会議
7/6(金)広報委員会では、第3回編集会議を応接室にて行いました。
ほぼ完成に近い原稿の誤字、脱字、全体のチェックをしました。 みんなで話し合いを重ね、より良い感じに出来上がりつつあります。 来週の編集会議にて完成予定です。 本日参加して下さった委員の皆さん、ありがとうございました。  高校の情報収集お役立ちサイト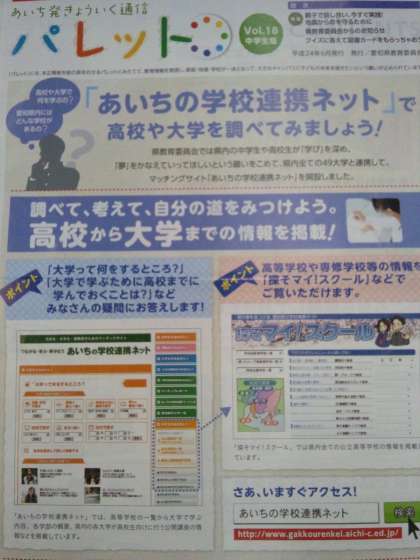 お子さんが持ち帰っている(はず)のチラシです。 ご覧になられていない方のために、ご紹介したいと思います。 表紙に「あいちの学校連携ネット」で高校や大学を調べてみましょう!という記事がありました。 「中学生のみなさんへ」というコーナーから、公立高校一覧(探そマイ!スクール)や私立高校一覧(愛知県私学協会)を見ることができます。 3年生は、夏休みに入るとすぐに個人懇談があり、進路希望について3者面談をします。 ほとんどの生徒が進学を希望していると思いますが、最初はどんな学校があるのかさえわからない状態ですよね。 今はインターネットで、簡単に情報を得ることができます。 1年生や2年生の方も、今のうちから情報収集しておくことをお勧めします。 ぜひ上手に活用して、お子さんの進路決定に役立てて下さい。 公立高校検索サイトの「探そマイ!スクール」は、いろんな条件で学校を検索できます。 なんと「制服のタイプは?」という条件項目もあるのです。最近は、制服がかわいいという理由で学校を選ぶことも多いそうなので、興味がある方は一度見てみて下さいね。  「大人の先輩からのアドバイス」に想う その2
「大人の先輩からのアドバイス」第1弾の船引さんの記事の感想の2回目です。
(船引嘉明さんから「未来の大人たちへ」 7/2) 企業の経営者として、どのような人材がほしいか、という問いに、船引さんは 自分のことは自分でできる人 とおっしゃっています。 これには、さまざまな意味が込められていると思うのです。例えば ●与えられた仕事を、自分で考えて実行できる。自分で考えることが大切。 ●自分でやれることは自分でやり遂げる。安易に他人に頼らない。 ●わからないことやできないことは、すぐにわかる人に聞く。頼るべきところは素直に頼れる協調性が大切。 ●自分の仕事に責任を持つ。 等々です。 これらのことは、社会人になってから身に付けることというよりは、中学生の今、社会に出る前に身に付けておくべきことなのではないでしょうか? 子供達は、学校で、家庭で、地域で、いろいろな人たちと関わり合いながら成長していきます。上記の事は、その時にも必要なことばかりですね。 さらに、船引さんは あいさつや返事など、当たり前のことがしっかりできることが大切 ともおっしゃっています。 まさに「ABCDの原則」ですね。 学校がなぜ「ABCDの原則」に力を入れて取り組むのか、その答えがここにあります。社会人として、とても大切なことだからです。 あなたたちがやっている「ABCDの原則」は、こんな風にあなたたちの将来に関わっているんですよ、必ず役に立ちますよということを、保護者からもぜひ子供たちに伝えたいですね。 小牧山の自然の造形美「モミジバスズカケノキ」@趣味'sブログ   「大人の先輩からのアドバイス」に想う その1 (船引嘉明さんから「未来の大人たちへ」 7/2) とても示唆に富むお話で、深く感じ入りながら記事を拝見しました。 2回に分けて、感想を書きたいと思います。 船引さんの少年時代のお話は、とても興味深いですね。 「好きだから」「楽しいから」「おもしろいから」そんな気持ちがあれば、どんどん深く詳しく知りたくなってきます。 ひとつわかると、さらにおもしろくなって、次が知りたい。またひとつわかると、もっと好きになって、その次も知りたい・・・この無限ループにはまれば、人間は常に進化していけそうです。 船引さんは、ご自身がこのループを体験しておられるのでしょうね。 そして、その良さを実感しているからこそ、中学生に 「一つの物事に集中して取り組むこと」 「自分の興味のあることをとことん追い求めていくこと」 を体験してほしいとおっしゃっているのだと思います。 中学生という、今の時期に、こういった体験をすることは、とても貴重な経験になります。 船引さんのように、それが将来の仕事につながればよいですが、必ずしもそうならないことの方が多いでしょう。 でも、この経験は、きっと子供の人生に役立つと思うのです。 何かをとことんがんばった記憶は、ずっと心の中にあるものです。 いつか困難にぶち当たった時に「あの時のがんばり」を思い出して、困難に立ち向かっていく勇気を与えてくれるはずです。 忙しい子供たちですが、中学生の間に、ぜひそういう「熱中する体験」をしてほしいなと願っています。 学校でも、子供たちをその気にさせるような仕掛けを考えていただけると、うれしいですね。 新しいことを始めるよ 〜未来の大人たちへ編〜
学校HPで新コーナーが始まりました。
その名も「未来の大人たちへ〜大人の先輩からのアドバイス〜」。もうご覧になりましたか? このコーナーが生まれたきっかけについて、紹介がありました。 (「未来の大人たちへ」コーナーが生まれた理由 7/2) この記事を読んで、感動がいっぱいでした。 まず、PTA会長OBの方々が、今後の日本社会を創り上げていく中学生への願いや、今、何を学んでおくべきかなどを熱心にお話下さったということ。 多くの保護者は、自分の子供のことだけで精いっぱいなのに、卒業してもなお、小牧中学校の生徒たちに心を寄せて下さっている。 なかなかできることではありませんよね。なんとすばらしい「大人の先輩」でしょう。 こういうステキな「大人の先輩」が地域にいてくれるということは、学校にとっても、保護者にとっても、また子供たちにとっても財産であると言えますね。 しかし、その「財産」も上手に使わなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。 そこで「つなぐ役割」が重要になってくるのです。 今回、そのつなぐ役割を校長先生が果たして下さいました。 校長先生がつないでくれたことで、隠れた宝(大人の先輩からのアドバイス)が掘り起こされて、私たちの手に届けられたのです。 先日の市P連の懇親会で、江口教育長がおっしゃった「学校と地域をつなぐかけ橋」という言葉がよみがえり、こういうことなんだ!と感動しました。 そして、他にも感謝したい人たちがいます。それは子供たちです。 私たちは、子育ての中で、いろいろな経験をさせてもらい、新しいこともたくさん学んできました。 今回の新コーナー「未来の大人たちへ」でも、また多くのことを学ばせてもらえることでしょう。 子供たちもまた、保護者と学校を「つなぐ役割」をしていると思うのです。 地域、学校、子供たち・・・このすばらしいつながりに感謝しています。 そして、私たち保護者もそのつながりの中に入って、一緒に学び合っていきたいですね。 「オカトラノオ」たくさんのかわいい花が集まって、まるで学校みたいですね@趣味'sブログ   【図書ボラ】7/3 活動報告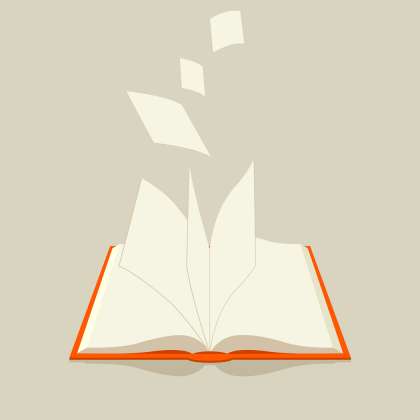 午前は、らいぼらネット『あ〜や』の情報交換会が、小牧小学校で開催されました。小牧小のホームページでも『あ〜や』の情報交換会の記事がありますので、よろしければこちらもご覧下さい。 さらに午後も、小牧中図書館での活動を実施していただきました。 図書ボランティの皆さん、いつもありがとうございます。 以下、図書ボランティアさんの活動報告です。 ********** らいぼらネット『あ〜や』は、小牧市内の小中学生の図書ボランティアの人達と読み聞かせのサークルの人達の集まりです。 各団体の活動内容とこれからの予定を発表し合ったあと、味岡小学校によるパネルシアター「あいうえ王」の上演がありました。 とても面白かったです。 その後、司書の福岡さんによる「語り」(昔話を何も見ないで語るというものです)があり、2話語っていただきました。大人でも、じっくり聞き入ってしまいました。 最後に、新設となった小牧小学校の図書室見学をしました。新しい施設はいいですね。 午後は、小牧中の図書館での活動がありました。 活動内容は ● 読書感想文の書き方、課題図書の紹介のポスター作り ● 図書館廊下壁面と昇降口に掲示物を設置 図書ボランティアさんからのメッセージ 『 子どもさんと同じ本を読んで、読書対話なんていかが?』 ********** 夏休みになると、毎年、子供たちの頭を悩ませるのが、読書感想文ですよね。 書店へ行くと、すでに「課題図書コーナー」が特設されています。 たくさんある課題図書ですが、図書ボランティアの皆さんが、どんな本なのかを紹介するポスターを作成して下さいました。 ぜひ本選びの参考にして下さいね。 昨日の学校HPに、「読書月間の後半に入りました」という記事がありました。(読書月間後半 7/3) 保護者の皆さんも、お子さんと一緒の本に挑戦して、親子で読書談義してみませんか? 【市P連】情報交換会のまとめ
6/29(金)の情報交換会では、「各校のPTA役員決めについて」というテーマで、以下のグループに分かれて、情報交換を行いました。
グループ構成 A:篠岡小、光ヶ丘小、味岡小、本庄小 B:陶小、大城小、桃ヶ丘小 C:米野小、小牧小、小牧南小 D:小木小、三ツ渕小、北里小 E:村中小、一色小、小牧原小 F:応時中、味岡中、岩崎中 G:光ヶ丘中、篠岡中、桃陵中 H:小牧中、北里中、小牧西中 どこの学校でも、毎年苦労されるのが「役員決め」です。 この情報交換会では、他校の役員選考の方法を聞いて、自分の学校でも活かせないかと、皆さん真剣にグループディスカッションをされていました。 グループでの情報交換の後、全体で情報の共有を図るために、グループごとに発表を行いました。 その中で出た内容をご紹介します。 ● PTA会長について いわゆる「一本釣り」がほとんどのようです。基本的には、副会長を1年経験して、次年度に会長へ、という流れになっています。 2年連続での役になることもあり、平日に休みが取りづらいということで、一般の会社員の方は敬遠される場合が多く、最近は公務員の方にお願いする学校が増えています。 ●母親代表について 執行部や総務の中から選ばれることが多いようです。 会長同様、複数年の参加になるため、子供の学年も重要です。 ある学校では、総務役員を地区の輪番制にしていて、当番に当たっている地区から総務委員を選出し、その中から母親代表を決める、というやり方をしているとのことです。他地区の時はいいですが、自分の地区が当たる時は、地区役員決めが大変そうです。 また母代は、専門委員長を兼任することはあまりなく、執行部や総務のまとめ役という位置づけになっている学校がほとんどでした。しかし、中には母代が専門委員長を兼任するという学校もあり、その場合は母代の負担が大きいので、周りから「かわいそう〜」の声が上がっていました。 ● 役員選考委員会について 多くの学校で、役員選考委員会が組織されていました。 その中で次年度の役員候補を推薦してもらい、順番にアタックしていくという方法を取っているようです。 しかし、この選考委員会が形だけになってしまっている学校も多く、実際はなかなか人選が難しいようです。 それに、アタックする担当は会長や母代なので、結局会長や母代に負担がかかることに変わりはありません。 ● 地域の方の協力について 学校の規模や立地にもよりますが、地域の生き字引のような世話役の方がいらっしゃる学校は、とても頼りになるということでした。 地域コーディネーターさんも、地元の情報を持っておられるので、力を貸して下さることもあるようです。 あとは、子供関連のネットワーク(習い事やスポーツのクラブなど)を駆使して、家族総出で適任者を探す、という意見もありました。 ● 学校の協力について 校長先生や教頭先生が、ご自身の教え子を紹介して下さるケースもあるようです。うまくタイミングが合えば、パッと決まることもあるようです。 ● 輪番制について とくに中学校の場合ですが、いくつかの小学校区が集まって、1つの中学校区になっています。ですから、その小学校区で順番に会長や母代を回していく、というやり方もあるようです。 これは、各小学校区から来ている生徒数に違いがある場合もあり、少ない生徒数の校区では成り手がいなくて大変だという声が出ていました。 そのため、今では輪番制が成り立っていない学校もあります。 ● 新執行部、総務の決め方について 執行部や総務の役員さんを決めるのは、だいたい母代が担当するようです。 この決め方にも2パターンあります。 まず1つ目のパターンは、前任の母代が次の役員を決めて卒業する形。これだと、新母代は最初は楽ですが、一緒にやる役員さんたちは知らない人ばかりになってしまう可能性もあり、ちょっとやりにくい思いをすることもあります。 次に2つ目のパターンは、新母代が新年度の役員を決める形。こちらは、母代さんが自分と一緒にやってくれそうな人を探せるので、運営がやりやすいですが、新年度が始まる前からかなり動かなければなりません。 どちらがいいのか、一概には言えませんが、どちらも一長一短です。 このように、どこの学校でも悩みのタネの「役員決め」ですが、イヤイヤ引き受けてしまったけど、1年過ぎるころには「楽しかったわ〜やってよかったわ〜」とおっしゃっていただける方がほとんどです。 新しい友達もたくさんできますし、いろいろなお得情報をゲットすることもできますよ。 それに、多くの学校では役員の負担が少しでも軽くなるように、いろいろな工夫がされています。 やれる時だけお手伝いしてもらう形での活動もあります。 PTAは、子供が学校へ通っている間しか参加できない活動です。 保護者の皆さんには、ぜひ一度は参加していただいて、我が子の学校のことや先生のことをよく知っていただきたいなと思います。 そうすれば、もっともっと学校や先生が好きになれますよ。保護者の方が学校や先生を好きになれば、子供たちもきっと好きになります。 今しかないこの時期を、PTAで楽しく過ごしてみませんか? 役員はムリ!ということであっても、学校ではいろいろなPTA行事が行われています。皆さんのご参加をお待ちしています! ふれあいの森の可憐な「ネジバナ」@趣味'sブログ   ポーセラーツの活動紹介
6/30(土) 今年度1回目のポーセラーツの活動がありました。
ポーセラーツ&絵付けクラブは、今年で四年目になるPTAクラブです。 白磁に、専用シールや色を塗って作るので、自分だけの陶器ができあがります。 シールなので、誰でも気軽に本格的な作品が出来るのが魅力です。 過去には、お重や大皿など、大作にもトライしてます。 同じ作品でも、作り手の個性が出るのが、楽しいです。 いつも10人程度で和気あいあいと行ってるので、良かったら覗いて見て下さいね。 講師の杉野英美先生は、名古屋から来てくださっています。 私たちと年も近いので、とても気さくで、ステキな先生ですよ。    【市P連】懇親会
6/29(金)情報交換の後、小牧市小中学校PTA連絡協議会の懇親会が、同会場で開催されました。
PTA会長、母親代表の他に、各校の校長先生にもご参加いただき、盛大に開催することができました。 日ごろ、なかなかお話する機会のない、他校の方々や先生方と、和やかで楽しい雰囲気の中、貴重な情報交換ができ、有意義な時間になりました。 また、教育委員会から江口教育長をはじめ、多数のご来賓の皆様にもご臨席いただきました。ありがとうございました。 【ご来賓の皆様】 小牧市教育委員会教育長 江口 光広様 小牧市教育委員会教育部長 中嶋 隆様 小牧市教育委員会教育部次長 舟橋 泉様 小牧市教育委員会生涯学習課長 高木 大作様 江口教育長のごあいさつの中で、印象に残ったお話しをご紹介したいと思います。 ● 仕事柄、小牧の全小中学校の授業視察に行きます。また、他県や他市の学校の視察にも行きます。そこで感じるのは「小牧の授業レベルの高さ」です。これは、日頃の教職員がしっかり取り組んでいる成果だと思っていますし、教育長として小牧の教育のすばらしさを自負しています。 ● 学校はとかく閉ざされた世界になりがちです。PTAの皆さんには、学校と地域をつなぐ架け橋になってほしいのです。 子供が卒業すると、学校との関わりがなくなってしまうのが普通です。 しかし、子供の育ちには、地域の支えが必要です。なぜなら、子供は地域の中で育つからです。 教育長のお話しは、そのことを改めて思い出させて下さいました。 我々PTAが、地域の方々に、再び、学校への興味や関心を持ってもらえるような活動をしていけるといいですね。 また、市P連会長である、我が小牧中PTA会長の大野会長も、檀上でごあいさつをされました。 大野会長からは、次のようなお話しがありました。 ● 各校のホームページをチェックするのが日課です。ホームページを見ると、それぞれに、いろいろな取り組みをされていることがよくわかります。情報発信は大切ですね。 小牧中のPTAの部屋も、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。 多くの皆さんにご覧いただいていることに、会長、母代ともに、深く感謝しています。ありがとうございました。 これからも、活動の様子がよくわかるホームページを目指してがんばっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。    【市P連】情報交換会
6/29(金)小牧市小中学校PTA連絡協議会の情報交換会が、小牧駅上の小牧コミュニティーホールにて開催されました。
市内小中学校25校の全PTA会長、母親代表の皆さんにお集まりいただき、各校のPTA役員の選考方法について情報交換をしました。 どこのPTAでも、役員選考は、最大に悩みのタネです。 そこで、他校ではどのように選考を行っているかの情報交換をして、自校の役員選考の参考にしてもらおうという趣旨です。 グループに分かれ、ざっくばらんに意見交換をしていただいた後、グループごとに出た意見を発表して、情報の共有を図りました。 いろいろな意見が出ましたので、後日そのまとめの記事をアップしたいと思います。   給食のおはなし その2
期末テストが始まり、その間給食はお休みです。
いつも楽しみにしている「今日の給食」のページが見られないのは、ちょっとさみしいですね。 小学生の弟や妹のいるご家庭では、「今日の給食はどうだった?おいしかった?」「うぅ〜食べたかったな〜」なんて会話が交わされているのでしょうか? 先週の火曜日、台風4号が猛威をふるいました。 幸い小牧では大きな被害もなかったようで、なによりでした。 しかし、保護者にとっての関心は、ズバリ「明日の給食があるかどうか」ではないでしょうか? 今回は、「翌日の給食は実施します」というお手紙が配布され、ヤレヤレと胸をなで下ろしました。 今年は、何度このような「台風でドキドキ」な目に遭うのでしょうか・・・ 給食を中止にするかどうかの判断は、どのようにしているのかな?と疑問がわいたので、台風のときの小牧市の学校給食の対応について調べてみました。 小牧市のホームページに、以下のような説明がありましたので、ご紹介したいと思います。 (以下、市HPの引用です) 台風により暴風警報が発令される恐れのある時は、前日の午前10時までに給食を実施するか、中止するかを市教育委員会が決定し各学校に通知します。ただし、前日が土・日曜日や祝祭日などの休日の場合は、その前の学校が開校している日に決定します。 例えば・・・ * 例1 給食実施予定日の10月18日(月)に暴風警報が予測できる場合には、土・日曜日の前日の15日(金)午前10時までに決定します。つまり、3日前に決めることになります。 * 例2 給食実施予定日の10月12日(火)に暴風警報が予測できる場合には、前日の11日(月)は体育の日で祝日なので、8日(金)午前10時までに決定します。つまり、4日前に決めることになります。 なぜ、そんなに早く給食を実施するか、中止するかを、決めるのかと疑問をもつ方もいらっしゃると思いますが、主な理由としては次のことが挙げられます。 * 保護者への連絡手段は児童・生徒を通して行うので、児童・生徒が下校するまでに決定し連絡する必要があるためです。 * 給食に使用する食材の製造や、納入を前もって中止する必要があるためです。 いずれにしても台風という自然現象のため、予測が困難であり非常に難しい判断を迫られるものです。児童・生徒の登下校時の安全を確保しつつ、また給食の食材についても無駄にしないよう、慎重に判断しています。 (以上、引用ここまで) 夜のうちに台風は通過してしまい、今日は青空が広がっている、という天気であっても、前日に「給食中止」の判断がされていれば、弁当持参になるのは仕方のないことですね。 そんな時、当たり前だと思っている毎日の給食が、とてもありがたいことなんだなと感じます。 生徒の皆さん、3日ぶりの明日の給食を、感謝してもりもり食べて下さいね。  |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
||||||||||