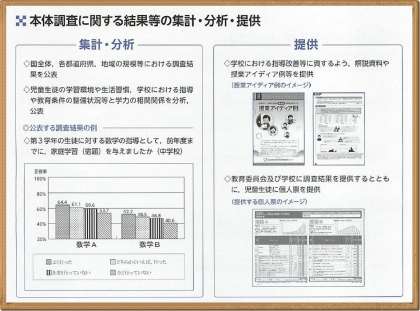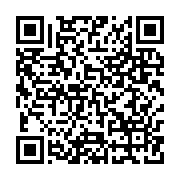|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:6 総数:156411 |
PTA社会見学のご案内  毎年恒例のPTA社会見学ですが、今年度は、滋賀県長浜市の「黒壁スクエア散策とガラス工芸体験」を企画しました。 豊臣秀吉の作った町「長浜」で歴史と文化を体験しませんか? たくさんの皆さんのご参加をお待ちしております。 ●日時: 6月5日(水) 午前8時15分〜午後4時(予定) ●集合場所: 小牧中学校 正門 ※自家用車の校内への駐車はご遠慮ください ●持ち物: とくにありませんが、動きやすい服装で ●費用: 3,000円(昼食代、体験代含む) ●日程 8:15 学校集合 8:30 出発 10:00 長浜 黒壁スクエア到着 黒壁ガラス体験教室にてサンドブラスト 長浜浪漫ビール館にてランチ 黒壁スクエアを自由散策 14:00 現地出発 16:00 学校到着予定 ●申し込み: 申込票に費用(3,000円)を添えて、担任の先生へ提出 ●申込締切: 5/15(水) ●その他 定員(30名)になりしだい締め切りますので、お早めにお申し込みください。 5/25(土)以降のキャンセルは返金できかねますので、ご了承ください。 作品は、秋の文化祭の「PTA作品展」に展示させていただく予定です。 ※写真は「黒壁スクエア」のホームページから引用しています。 「テスト週間」に想う 1年生にとっては、中学生になって初めての定期テストですね。 本人はもちろんですが、保護者の皆さんもけっこう戸惑っていらっしゃるのではないでしょうか。 学校では、先生方が、テスト勉強のしかたを指導して下さっています。 そして子どもたちは、自分でテスト週間中の勉強の計画表を作成しています。 この計画表をもとに、毎日テスト勉強に励むわけですが、計画通りに進んでいるのか、親としては気になるところですね。 中学生ともなれば、自分のことは自分で、というのが基本ですが、初めての経験では、うまくいかない場面も出てくることと思います。 しつこく訊くと嫌われますから、さりげなく(これがポイント)「どんな感じ?順調にやれてる?」と訊いてあげて下さいね。 連休明けからずっと天気がよく、気温が高い日が続いています。 空気も乾燥していますし、とくに1年生は体力的につらいかもしれません。 親としては勉強が気になるところですが、それよりも体調管理に気をつけてあげていただきたいと思います。 他校のHPで見つけた「ステキな言葉」をご紹介します。 ●新城市立千郷中学校HP 今朝聞いた言葉 5/8 ***** 引用開始 ***** 「あたりまえ」を「ありがとう」と言うのが 感謝 「だから,何?」を「おめでとう」と言うのが 賞賛 「もう、ダメだ」を「これからだ」と言うのが 希望 「なりたいな」を「なってやる」と言うのが 決意 「もういいや」を「まだ待とう」と言うのが 忍耐 「疲れた」を「頑張った」と言うのが 努力 ***** 引用ここまで ***** 記事の中で校長先生は「未来(あす)を創る中学生の姿です。頼もしい中学生です」と書かれています。 私たち保護者も、心に留めておきたい言葉ですね。 「もう、ダメだ」という子どもに「まだまだこれからだよ」と希望を持たせる言葉をかけられる親でありたいと思います。 「ABCDの原則」に想う〜集会編〜 (小牧中集会での当たり前のレベル 5/1) 原稿を持たず、しっかり前を向き、堂々と自分の意見を述べる姿は、本当にすばらしいですね。 小牧中では、集会のたびに「当たり前」に見られる光景で、記事の中で校長先生も「牧中の集会においては、ノー原稿で前を向いて堂々と話すこと、これは当たり前のレベルなのです」とおっしゃっています。 「牧中生は本当にすばらしいなぁ」と感心した半面、少し気になることがあります。 それは「当たり前と言っても、誰にでもできることじゃないし、ちょっとハードルが高いよね」ということです。 この「当たり前のレベル」が強要されてしまうと、普段人前で話すことがあまり得意ではない子たちは、ますます尻込みしてしまい、なかなか自分から「発表してみよう」という気持ちにならないのではないか、と少し心配になりました。 舞台で発表する生徒たちは、普段から立派に行動できる子ばかりです。 もちろん、立派に舞台発表をしたこの生徒たちの中にも、すんなりとできるようになったわけではなくて、たくさんの練習を積んで本番に臨んだ人もいるでしょうし、がんばった努力の成果が発揮できた発表だったのだと思います。 でも、子どもたちは「そりゃあの子ならできるでしょう」と思って見ているだけで、「よし、自分もやってみよう!」とは思っていません。 子どもたちは、誰もが皆、すばらしい可能性を秘めています。 「鍛えれば子どもは強くなる」ということもありますし、本来は誰にでも「やればできる」ことなのかもしれません。 しかし、子どもたちはそれぞれ違う個性を持っていて、「得意なこと」「不得手なこと」もそれぞれ違いますし、さらにそのレベルも違いますよね。 引っ込み思案で、自分から何かを発信することが不得手な子どもが、勇気を出して何かの係に手を挙げてみようと思ったとしても、「その係は、みんなの前で発表をする機会があり、その発表はノー原稿でやらなければならない」となると、「自分にはそれはムリだから、やっぱり手を挙げるのはよそう」となってしまうかもしれませんね。 保護者としては、子どもに「自分から何かにチャレンジしてほしい」という思いを持っています。 我が子が「やってみよう」と思えるように、そっと背中を押したり、褒めたり、励ましたりしながら見守っていますね。 子どもに「やってみよう」という強い思いが芽生えたときに、目指すべき最終形として「ノー原稿」を目標とするのは、すばらしいことだと思います。 しかし、「やる気のタネ」をまいて水をやっている段階で、「やってみようかな」という小さな小さな芽が芽生える前から、あまり「ノー原稿」を意識しすぎると、小さな芽は成長してくれないかもしれないと思うのです。 お子さんのことを、一番よくわかっていらっしゃるのは、保護者の皆さんだと思います。 お子さんのペースに合わせて、お子さんと一緒に「やる気のタネ」を 育てていけるといいですね。 「こどもの日」に想う(2) 世の中では「少子化」の問題点ばかり指摘されていますが、子どもにとっては、子どもの数が少なくなっていれば、その分手をかけてもらえるし、大切に育てられて幸せな子ども時代を過ごせて「よい面」もあるのではないでしょうか。 でも現実はそうでもなさそうです。 「大切に育てられるはず」の子どもたちは、「虐待」や「いじめ」に悩み、深く傷ついています。 また「大切に育てられすぎて」自分のことが何もできない子どもや、自分で考えることを全くしない子どももたくさんいます。 親は誰でも、我が子の幸せを願っています。 それなのに、子どもはなかなか親の思うとおりには育ってくれませんね。 それは当り前のことです。 だって、子どもは「その子自身」であって、私たち親とは「違う人間」なんです。 子どもは、親の所有物ではありません。 それぞれが「心」をもった個人です。 そのことを「こどもの日」に改めて思い出してほしいのです。 思春期の子どもを持つ親は「子どもが何を考えているのかわからない」「子どもが何も話してくれない」という悩みを持ちますね。 心配で、ついつい口出しばかりしてしまうので、子どもは嫌がってますます話をしてくれなくなる悪循環です。 でも、本当は子どもは話を聞いてほしいと思っているのです。 まずは、口を挟まず「じっと聴く」ことが大切なのだと思います。 子どもの存在を認めて尊重し「あなたがいることが幸せ」ということを折に触れ伝えれていけば、きっと子どもは自分に自信を持てるようなり、他への思いやりの心も育つのだと思うのです。 わざわざそんなこと言わなくても、保護者の皆さんはよくわかっていらっしゃると思いますが、わかってはいても、なかなか常に実行に移すのは難しいことですよね。 疲れていたり、虫の居所が悪い時には、ダメだとわかっていても感情的に怒ったりしてしまいます。 でもそれでいいのだと思います。 完璧な人間などいませんから、親も子どもも同じ人間として、失敗したりつまづいたりしながら、一緒に成長していけばいいのです。 岩手の小学校の教頭先生(岩手では副校長と呼ぶそうです)のブログに、すてきな記事を見つけました。 「こどもの日」は「お母さんに感謝する日」という内容です。 今日は、「子ども」ばかりが注目される日ですが、「お母さん」に感謝しようという言葉は、とてもうれしいことですね。 ●地域のよさ・日本のよさを伝える授業 5/5 「母の日」よりも一足早いですが、世界中で子どもを育てているすべてのお母さんたちへ「お疲れ様」と「ありがとう」を伝えたいと思います! 「こどもの日」に想う(1) 子どもたちの健やかな成長をお祝いする日ですね。 良いお天気に恵まれ、こいのぼりが気持ちよさそうに大空を泳ぐ姿に心がなごみます。 例年この時期は「こどもの日」に合わせて、総務省から子どもの数が発表されます。 新聞やテレビでも大きくニュースとして取り上げられていますが、「子どもの数は32年連続で減少しており(1,649万人)、人口比も最低を更新した」とのことでした。 ところで、ここで言われている「子ども」の定義ですが、15歳未満のことを言います。 ということは、中学生は「子ども」ですが、公共交通機関では「大人料金」が適用されますし、公共施設では「中学生料金」が設定されているところもあったり、意外とあいまいな扱いですね。 それはさておき、子どもが少なくなっていることの問題は「少子高齢化」という言葉で、常々取り上げられていますね。 先日も「授業参観」に想う(3)でご紹介した、木曽川中学校のHPでも校長先生が記事を書かれています。 ●一宮市立木曽川中学校HP 5.05止まらぬ少子化≪校長室≫ 記事の中で校長先生が書かれているように、日本中の子どもたちにとって「少子高齢化」は避けて通れない道です。 社会保障のあり方や、社会の仕組みを変えないと、対応できない事態になるのは明らかです。 「どうすればいいのか」ということは、大人任せではなく、将来負担を担わなければならない子どもたちも、一緒になって考えていく必要があるのではないかと感じています。 そういうことを考えるためのヒントを子どもたちに持ってもらうためにも、子どもが自分のまわりにも目を向ける機会を持つことは大切だと思うのです。 そのキーワードとして「地域との関わり」があり、小牧中では具体的な活動の一つに「注文ボランティア」や「ジュニア奉仕団」があります。 先日「地域の部屋」で「注文ボランティア募集」の記事が掲載されましたね。 ボランティア活動を通して、地域の方と交流しながら、学校だけでなく地域のことにも関心が持てるような取り組みになるといいですね。 (【地域の部屋】注文ボランティア第1弾 5/2) ちなみに、この「注文ボランティア」ですが、職員室廊下の掲示版に案内が貼り出されていますが、子どもたちは意外に関心がなくて、残念ながら気が付いていません。 ぜひご家庭でも「注文ボランティアがあるみたいだね。掲示板を見てみたら?」と一声かけていただけるとうれしいです。 「授業参観」に想う(5) ●フォー・ネクスト 「いいです」は慎重に使う!? 4/30 「いいです」という言葉は、例えば、 ・先生の質問に対する子どもの答えが正解だったとき、先生が子どもに「いいです」と答える ・子どもの答えを、先生が他の子どもたちに「どうですか?」と聞いた時に子どもたちが「いいです」と答える というような場面で使われているが、子どもの発言を上から目線で判定しているように聞こえるので、子どもにとっては「公開試験」を受けているような気持ちがして、積極的に発言しなくなるのではないだろうか、というお話でした。 大西さんがブログの中で書かれているように、すべての「いいです」が良くない、というわけではないのでしょうが、言葉を慎重に扱ってほしいということのようです。 この「いいです」という言葉、以前に、小学校の授業参観で何度か聞きました。 (そういえば、中学校の授業参観では聞いていないような・・・) 初めて遭遇した時は、とても驚きました。 そして、ちょっとかっこよく見えました。 とくに教科には関係なく、子どもたちは自分が発表した後に、必ず「いいですか?」と付け加えるのです。 それに対して、他の子どもたちが「いいです」と答えて、それが当たり前のように授業が進んでいきました。 あとで子どもに聞いてわかったことですが、担任の先生は授業を受けるときのルールをいろいろと決めていて、子どもたちは言われたようにやっているうちに自然とそのようなスタイルになったようです。 それまでの授業は子どもの「○○だと思います」という発言を、まず先生が受けて「他に意見はありますか?」と子どもたちに投げかけて・・・という、先生と生徒のジグザクな授業ばかりでした。 それがいきなり、子ども自身が「いいですか?」とみんなに聞いて、それに対してみんなが「いいです」と答えているのですから、自分たちで進められるなんて、なんだか子どもがちょっと立派になったなぁと感じたものです。 その他にも、子どもが自分の発言の最初に「○○さんの意見に付け加えて」とか「○○さんの意見と同じですが」などと言葉を添えて、友達の意見をつなぐ形で発表する場面にも、とても驚きました。 たとえ先生にそのような発表の仕方をしなさい、と言われていたとしても、見ている保護者には、ずいぶんと子どもが大人びて見えたものです。 なかには「○○さんの意見に付け加えて」と言っておきながら、「それ全然違う反対の意見じゃん」と突っ込みたくなるような発言の子どももいましたが、それはそれで愛嬌があっていいんじゃないという雰囲気でした。 というように、どちらかと言えば「なんかすごいなぁ」と感心して見ていた「いいですか?」だったのですが、大西さんのブログを拝見して、単純に感心ばかりもしていられないのだなということがわかりました。 先生の発言というのは、一つ一つに意味があって、深いものなのですね。 親は子どもに対して「上から目線」で「〜しなさい」と、いつも命令口調になってしまいがちですよね。 先生方の子どもへの問いかけ方や、子どもの発言の受け方などは、参考にしたいことばかりです。 次回(6/17の予定です)の授業参観では、そんな視点もひとつプラスしてご覧になってはいかがでしょうか? 先生方の問いかけや受け方から、何かしらのヒントが得られるかもしれませんね。 牧中ランナーズ、活動開始!   写真は、4/13(土)の活動の様子です。 これから、体を動かすにはピッタリの季節になります。 運動不足を自認している保護者の皆さま、ぜひ「牧中ランナーズ」の一員となって、さわやかな汗を流しませんか? お待ちしています!
|
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
|||||||||||||