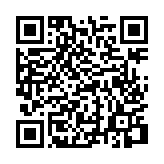|
最新更新日:2024/06/11 |
|
本日: 昨日:212 総数:1321348 |
プレイバック 令和元年度卒業式 5 ー授与ー





受けとる方は、ほとんど練習なしで本番に臨んだわけでしたから緊張気味でしたが、全員上手に受けとることができました。その集中力と対応力に感心しました。その様子は昨日の記事でお伝えした通りですが、話してないことが一つあります。 実は、渡す方は内心焦っていました。証書が1枚ずつうまくとれずいたのです。最近、手指消毒を多用するようになり、指先がつるつるになっていました。クリームは自室の机に置いたまま忘れていました。何度か2枚渡しそうになってリズムが乱れた箇所もあったはずです。でも、何とかトラブルなく終えることができました。卒業生の皆さんは証書を受け取ってほっとしたと思いますが、私も無事渡し終えて思わず胸をなでおろしました。 プレイバック 令和元年度卒業式 4 ー校歌ー





今年はコロナ禍のなかでの縮小版で行いました。来賓も在校生もいません。換気のため2階の窓は開放され、保護者の方には受付時に、手指消毒とマスク着用をお願いしました。座席間もゆったりするように配置しました。 国歌に続き、校歌を歌いました。6年生にとって最後に歌う校歌です。”♪〜木曽の山並み 黎明の〜」心を込めて歌いました。「われらのわれらの北里小学校」では一段と声が大きくなりました。教師席はもちろんですが、保護者席からも歌声が聞こえました。卒業生の方でしょうか。心強い応援団です。 プレイバック 令和元年度卒業式 3 ー登場ー





胸を張り堂々の入場です。保護者と教師の拍手に迎えられての登場。本来なら在校生200人の拍手が加わるはずでしたが、その分を教師がカバーすべく懸命に手をたたきました。 プレイバック 令和元年度卒業式 2 ー説明ー





机上には、幻となった「祝う会」の会場飾りの写真。運動会のソーラン節の踊りや先生たちからのメッセージ(祝う会の出し物)入りのDVD、養護の先生からは素敵にアレンジされた成長の記録。各学年からの手作りのお祝い&応援グッズなど山盛りでした。もちろん楽しみにしていた卒業アルバムも。 再会を喜び合う間もなく体育館へ移動。これからの30分間は時間との戦いです。やりたいことは山ほどあれど、時間がありません。6年生はまだ自分が座る位置も動きも何も知らない状態です。まず、先生から式の流れと各自の動きの説明がありました。誰もが集中して聴き入りました。先生も児童も必死です。これほど真剣に話を聴くのは今年一番ではないでしょうか。この後すぐに本番なのです。説明後、一部練習。とても全員が一通り練習する時間はありません。歌も始めだけ。動きも1組の男子の途中まで。全体の流れ全般を理解するだけでした。 保護者の皆さんには、体育館の外で長い間お待たせしてすみませんでした。しかし、会場内は、とても練習とは呼べない、必死の打合せが行われていたのです。 プレイバック 令和元年度卒業式 1 ー再会ー





6年生は8時前に昇降口に集まり出しました。2月26日の学年閉鎖から数えて23日ぶりの登校です。久しぶりに再会した仲間と大騒ぎしたい気持ちを抑えて、落ち着いて整列する姿に卒業式に向けての気持ちと緊張感を感じました。 担任の先生は、元気よくあいさつする卒業生を昇降口で出迎えました。笑顔があふれました。教室の入り口で、胸に花をつけてもらいました。今年の卒業生に似合う黄色の可憐な花です。先生につけてもらうのが照れくさい顔もありました。 プレイバック 令和元年度卒業式 0 ーつぼみー

校庭の桜はまだでしたが 卒業生の笑顔が咲きました 素敵な卒業式でした。みんなの思いが集結した式でした。思い出に残る感動的な式でした。その1日を朝から順にふり返ってみます。 できたら、校内の桜が開花するまでに、その様子をお伝えできたらいいなと思います。 3月20日午後3時現在の桜は、まだつぼみです。しかし、つぼみは膨らんで堅さがとれ、花びらの柔らかさが感じられます。枝全体にピンクの色が目立つようになりました。この3連休中に、きっと開花するでしょう。 瞳の対話 ー卒業証書授与の場でー 【校長日記】3/19

令和元年度卒業生98名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。保護者やご家族の皆様に心からお祝い申し上げます。 第73回卒業証書授与式が、今日、無事に実施できました。98名の卒業生全員に一人一人卒業証書を渡すことができ、本当にうれしく思います。思わぬ病気感染防止対策のため、世間では様々なイベントが中止・延期されたり、晴れ舞台がなくなったりしている中です。学校も長期の臨時休校となる中、「最高の卒業式」ができました。 舞台の中央。卒業証書授与。説明を受けただけで実際の練習なしの子が大部分の状態で、立派に証書を受けとりました。多少のぎこちなさはありましたが、堂々と受けとった態度は立派です。担任の万感の思いが込められた呼名に、「はいっ」と応え、真正面に立つ卒業生。ほとんどの子と目が合いました。瞳に浮かぶ緊張感と決意。受けとる方も渡す方もマスクをしています。その分、瞳で語ります。「おめでとう」と添えた言葉に、表情が和らぐ瞳、力強く応える瞳、謝意を表す瞳、いろいろな反応がありました。「ありがとうございます」と声に出した子もいました。目と目を合わせた刹那、その子とつながった気がします。過去の活躍の場面がさっと脳裏を巡ります。大会での場面、教室や廊下、校庭で触れ合ったこと。つい言葉を継ぎたくなる自分を抑えます。1人と対面できる時間は、ほんの1、2秒。それは私にとって濃密な対話の、幸せな時間でした。 振り返れば、卒業生の皆さんは、とても頑張り屋でした。いつも率先して動き、野外生活や修学旅行では、その立ち居振る舞いや言動がいろんな場面で褒められました。とても誇らしかったことを覚えています。そして、きょう有終の美を見事に飾ってくれました。卒業生は私の、本校の誇りです。これからも、素直な心のまま、「チャレンジする心」と「感謝する心」をもって令和の時代をたくましく切り拓くこと、夢や美しい願いごとがかなう日が来ることを祈ります。ご卒業おめでとうございます。きょうの日の感動は忘れません。(校長) (※卒業式の記事は今後、続報を更新する予定です) 

祝 北里中学校卒業証書授与式



厳粛な空気の中、卒業生一人一人が呼名に大きな返事で応えて、卒業証書を立派に受け取ったことでしょう。キビキビした所作が清々しさを周りに醸し出したことでしょう。素晴らしい合唱を体育館中に響かせたことでしょう。女声は美しく澄んで、男声は力強く熱く、聴く者の心に迫り魅了したことでしょう。 3年前、堂々とそしてさわやかに、この学舎(まなびや)を巣立っていった卒業生たち。運動会でのソーランの勇姿が、バスケットボール部が躍動し涙でかすんだ女子の優勝シーンが、脳裏を熱く巡ります。命の尊さを教えてくれた仲間がいました。託された思いをしっかりと受けとめ全力で生きて、これからも命を輝かせてくれることでしょう。 臨時休業が始まった2日目。様々な試練を乗り越えた卒業生の皆さんが、新たなステージを目指し飛び立ちます。前途に幸多からんことを、と祈らずにはいられません。 義務教育無事修了、誠におめでとうございます。 表彰伝達は校長室で





表彰伝達をする機会がなくなりましたので、校長室で行いました。 〇第47回人権を理解する作品コンクール 書道の部 県 入選 5年 古澤さん 〇第30回小牧市 小学生バスケットボール選手権大会 男子の部 優勝 北里小学校 おめでとうございます。がんばりましたね。 6年生が登校できなかったので、男子バスケ部の写真は大会後の表彰式の写真を使いました。家で見てくれるでしょうか。 明日から「臨時休業」に
昨日の総理大臣や県知事の発言を受け、愛知県教育委員会より「新型コロナウイルスに関連した感染症予防のために、3月2日から春休みまで臨時休業とする」ように要請がありました。
小牧市においても、この指示のように市内小中学校を、3月2日(月)から春休みまでを「臨時休業」とすることになりました。ただし、 ・3月19日の卒業式は実施の予定(卒業生、保護者、職員参加) ・3月24日は修了式、通知表(修了証)の受け取り 詳細は、本日児童を通して文書を配布しますので、ご確認ください。 こうした判断は現時点のものであり、今後の状況次第では、変更もあり得ますのでご了承ください。 2月28日(金)きょうの里の子 ー月曜日課ー

大変な事態になりました。前代未聞の出来事です。異例の要請に保護者の皆様は大変驚かれたと思いますが、学校現場も言葉を失いました。具体的な今後の動きがわかり次第、ご連絡します。とりあえず、きょう1日、落ち着いて学校生活を営みたいと思います。 <月曜通常日課> ・月曜の授業 ・村瀬先生の読みきかせ 中止 ・学年別下校 【写真「先生の出し物」:祝う会の先生の出し物をビデオ撮影しました。呼びかけあり歌ありコントありの盛りだくさんの内容です】 「ごんぎつね」の授業 ー6年生とー 【校長日記】2/20

「ごんぎつね」とは、ご存じ新美南吉の名作中の名作で、国語の教科書に昭和31年から実に63年間も掲載されています。現在では、日本で使われているすべての4年生の国語の教科書に載っています。きっと保護者の方も、ひよっとしたらお祖父ちゃんお祖母ちゃんも、学校で習ったことでしょう。超ロングセラーの物語です。私が大好きな話です。 朗読の後、最後の六場面を読み描きました。ごんから兵十への視点の転換を確認して、悲劇を招いた兵十の行動をなぞりました。例えば、火なわじゅうのつつ口から出る「青いけむり」の「青い」が意味するものを話し合いました。いろんな意見が出ました。クラスによって多少の違いはありますが、「悲しみ」「ごんの死」「兵十の後悔」「別れ」などが出ました。「細く」と、頼りなげな描写に注目した子もいました。 「この後、兵十はどうするか」を考えました。授業で一番取り上げたかった問いです。テキストにはもちろん書いてありません。想像します。「嘆き悲しむ」「後悔する」「ごんのお墓を作る」「花を供える」「彼岸花の近くに埋める」……感性豊かな意見が出ます。 「で、それから?」私は、さらに想像を促します。村人に対しては?「ごんのことを話す」「ごんの優しさを伝える」「自分の後悔の気持ちを話す」……なるほど。反対に「秘密にしておく」と想像した子もいました。 この話の舞台は、江戸時代であることは冒頭の「おしろ」「おとの様」という言葉から推測できます。今から2、300年も前の話でしょうか。それが今まで伝わっているのです。「『わたし』が村の茂平というおじいさんから聞いたお話」という設定なのです。 とすると、「ごんぎつね」は語り継がれた話でしょう。人から人へ伝承された話なのでしょう。ひょっとしたら、本当に神様のようにあがめられたり、村に祠(ほこら)ができたりしたのかも、と想像は膨らみます。「ごんぎつね」を単なる「悲しい話」「報われない話」「悲劇」と読むよりは、「愛されて語り継がれた話」ととらえる方が夢があると思います。事実、63年間も教科書に載り続けていたのです。そのことに、気づいてくれたらうれしく思います。 卒業が近づくときに、6年生と一緒に「ごんぎつね」を読むことができました。一生懸命に考え、反応してくれた6年生のみなさん、ありがとう。このような機会を与えていただいた担任の先生方、ありがとうございました。いい思い出になりました。 朝会 3 ー校長講話ー【3つのありがとう】



感謝には2段階あると話しました。 まず、 人から何かしてもらって感謝する。これは初級です。まあ、例えるなら低学年向けです。 次の段階は、「当たり前」だと思っていたことに感謝する。例えば、食事や洗濯などお世話になっているおうちの人、毎朝連れてきてくれる班長さんに「ありがとう」と感謝することです。これができると中級です。 でも実は、感謝には、もう一段階あります。上級です。それは、「嫌なことや苦しいとき」にも感謝することです。これは大変難しく、大人でも簡単にはできません。先生だってできるとは言えませんが、できるように心がけています。 例えば、転んで足をすりむいたときには、「足の骨が折れなくてよかった。ありがとう」 何か失敗てしかられたときには「こういうことをすると失敗するとわかった。ありがたい。教えてくれてありがとう」また、友だちとけんかしたときには、なかなか相手に「ありがとう」とは思えませんが、とりあえず、心の中か小さな声で「ありがとう」「ありがとう」「ありがとう」と3回唱えてください。きっと気持ちが前向きになってくると思います。そうすると、あらあら不思議、ピンチがチャンスに変わります。先日、給食の時におじゃましたクラスには「ありがとう」の言葉が教室中にたくさんはってありました。「ありがとう」は、増やしたい言葉だと聞いて、とてもうれしくなりました。 「感謝する」気持ちで生活すると、物事はいい方に向かいます。3つのありがとうを覚えてください。(一緒に言ってみましょう。いいですか) まず、何かしてもらって ありがとう。うれしくなってありがとう。 次に、何もなくても ありがとう。ぜんぶ有り難いことだと気づきます。 さらに、何があっても ありがとう。ピンチがチャンスに変わります。 ぜひ、試してください。1日に「ありがとう」の言葉を最低10回、できる人はもっともっと口にして、3学期の残りの日々を明るく仲よく楽しく生活して、心温まる思い出をいっぱいつくってほしいと思います。きょうもお話をしっかり聴いてくれて「ありがとう」。 第70回記念書き初め大会 ー作品展&表彰式ー

新春にふさわしく、生き生きとした筆の運びで書かれた力作が並んでいました。あさひホール内では、入賞者の表彰式が行われました。北里小学校の児童もたくさん選ばれ、うれしくなりました。よくがんばりましたね。 個人賞をもらった人(舞台で一人ずつ表彰された人)は朝会でも紹介する予定です。賞状等は学校にお持ちください。 

2020年を迎えて ー北里小の初日の出ー 【校長日記】

本年もよろしくお願いいたします 「北小のHPを見れば早起きする必要はないね。いつでも初日の出が見られるから」そんな声に後押しされ、今年も元旦夜明け前に、北館の屋上に上りました。南館は2階、北館は3階あります。北館屋上で一番高い給水塔まで来ました。1年前も、8ヶ月前の令和の夜明けにもここに上がりました。今回は、さらに給水塔を登ると、正真正銘、北里小学校で一番高いところに着きました。ここからは、名古屋高速11号線の高架の向こうに山の稜線が見えます。今年はここから初日の出を拝むことにしました。 小牧の初日の出は6時59分。6時20分過ぎに、東の空は少しずつ明るくなってきました。周りはまだ薄暗がりで灯りがともります。静かです。気温は1度とのことですが、屋上に溜まった水は一面凍っていました。ここでは氷点下になったようです。帽子にマスク、手袋、完全防寒で臨んでいるので寒さはあまり感じません。 雲はほとんどないクリアーな空。初日の出は見られそうです。東の空が明るくなるにつれて、星の輝きが薄れていきました。 6時55分、オレンジ色が濃くなりました。時間の経過につれ鮮やかさは増します。7時。まだ顔をだしません。稜線のどの部分からでしょうか、カメラ越しに見つめます。 7時4分35秒、稜線の一角から眩しい光があふれ出ました。曙光(しょこう)です。 1秒ごとに少しずつ、太陽が顔を出していきます。厳粛(げんしゅく)な気持ちになって、思わず両手を合わせました。太陽は5分ほどかけてすっかり姿を現しました。 新年の陽光は、やがて校舎を運動場を照らし始めました。 令和2年、東京オリンピック&パラリンピックが開催される年、令和の時代が本格的に動き出す年。今年はどんな年になるのでしょうか。どんなドラマが展開されるのでしょうか。 楽しみでなりません。里の子全員が元気に活躍できる年になることを祈らずにはいられません。 初日の出を見た里の子も、多いことでしょう 皆さん、いい正月を楽しくお過ごしください 

あけましておめでとうございます ー2020年の幕開けー

令和2年 希望の年が始まりました 北里小学校の一番高いところにたって 稜線から今年初めて顔を出した太陽に願いました 里の子が健康で元気に学校生活を送れますように 学校に里の子の笑顔がいっぱいあふれますように 世の中が激しく動き世界がますます身近になる今年 皆様にとっても大きく飛躍する年でありますように 12月25日 ー交通安全を誓うー

あの日からもう4年も経ちました 忘れられない 記憶に刻まれた日 ひとりの少女のことを想いながら 交通安全を願う ただひたすらに 個人懇談会2日目 ー寒い廊下でしたがー 【校長日記】

懇談中に校内を巡ると、笑い声が漏れてくるクラスもありました。窓越しに様子を見ても和やかな雰囲気で懇談が進められた教室が多かったように思います。お子さんについての成長した話、いい話がたくさん聞かれたらうれしく思います。 担任は保護者の方と一緒になり、同じ方向を向いてお子さんを導きたいと考えています。今後もご協力・連携をよろしくお願いします。また、気になること、学校に対する要望、ご意見等がありましたら、遠慮なく担任にお話いただくか、アンケート、連絡帳を通してお伝えいただければ幸いです。 下校指導の際にJAの角に立っていると「いつもHPで学校のことがわかり、親子の会話が盛り上がります」とある保護者の方から声をかけていただきました。有り難いことです。励みになります。最近、学校を留守にしがちでHPの更新が少なくなり、ご期待に添えなくて心苦しく思っていました。これからも情報発信に心がけますので、引き続きご家族で楽しくご覧いただければと思います。カウンターを開始した2006年10月24日からの総アクセス数は、きょう今現在、98万6千415件となり、夢の100万件にもう一息となりました。 人権講話 ーどんなかんじかなー

考えることがすきで学者みたいな主人公のひろくんが、友だちのことを「どんなかんじかな」と思いやる内容です。目が見えない子、耳が聞こえない子、両親を震災で亡くした子が登場します。でも相手の立場に立つと、すごい能力、素敵な可能性があることに気づくお話です。最後にひろくん自身の秘密がわかって心にずしんと響くお話です。 あとがきに作者はこのお話が生まれたのは「難病にも負けず、明るく夢を持って生きるある女の子との出会い」がきっかけとなったことを書いています。心を込めて読みました。 その後で、次のように話しました。 【来週の水曜日12月4日から10日は人権週間です。この人権週間は、「思いやりの心でやさしくなるきっかけの週」です。思いやりとは「相手の立場になってみること」。つまり、相手は「どんなかんじかな」「どんな気持ちかな」と考えることからはじまります。ぜひ、みなさんもお話に出てきた「ひろくん」のように「どんなかんじかな」と相手のことを考えてみよう。いろいろな発見があるでしょう。優しい心が生まれるでしょう。 そんな里の子が集まって、素敵な学校になるでしょう。これでお話を終わります】 里の子の心にうまく届いてくれたでしょうか。そうであることを祈ります。 

観劇 感激 ーむすび座さんありがとうー 【校長日記】

人形劇「かくれ山の大冒険」は、脚本や役者さんの演技力はもとより、舞台装置、音楽、照明など全ての演出が効果的に駆使され、とても完成度が高い作品です。私自身、今までに味わったことのない感動を覚え、「むすび座やるなあ!」とつぶやいていました。 感じたことを2つに絞って記します。 まず、人形劇について。これは「人形」劇です。その「人形」が人形遣いの手にかかると、命が吹き込まれ、感情が生まれ喜怒哀楽を表します。まるで、魔法をかけられたかのように。照明の効果もあるのでしょうが、黒子の人形遣いの姿が、視覚から消えるのです。写真を見ると、何だか人がいっぱいいるぞ(1体の人形を3人がかりで操るので当然です)と思うのですが、劇中では全く気になりません。それどころか、ないはずの表情まで見えてくるから不思議です。ネコや人物の動きも本物そのものでした。 もちろん、人形遣いの方の技術と連携があるからこそには違いありませんが、それを「むすび座」さんは「観客が自らの想像力を働かせて観ているから」と説明されます。子どもたちの感想にも「人形が生きているようだった」という声がありました。それは、その子が自分の想像力で補っているからに他なりません。逆に言えば、人形劇には「想像力を育む力」があるということです。これはすごいことです。 2つ目に、やはり「生はいい」ということです。映像と違い、目の前で演じられる「生」は、役者さんの息づかいが聞こえ、体温が感じられ、迫力があります。今回も「生の演劇」を通して、子どもたちには学びにつながるたくさんの気づきがあったことでしょう。それは、目前で演じられたからこそに違いありません。 「想像力は人を思いやる心の源であり、自らの人生を切り拓く力となる」ーそんな内容の言葉がむすび座さんのパンフレットに書かれていたように覚えています。劇を観てナルホドと納得し、観劇の素晴らしさを実感しました。むすび座さんありがとうございました。 

|
小牧市立北里小学校
〒485-0051 愛知県小牧市下小針中島二丁目 50番地 TEL:0568-77-3194 FAX:0568-75-8290 |
|||||||||