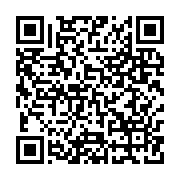|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:10 総数:156331 |
【生指】6/14 ジュニア奉仕団支援 写真館(3)   「イングリッシュガーデン」は、牧中の宝物です。 大人も子どもも、みんなで協力して、草抜きをがんばりました! 【生指】6/14 ジュニア奉仕団支援 写真館(2)   学校の外周のゴミ拾い&草抜きです。 こんなコンクリートの隙間にも、しっかり草が伸びています。 まさに「雑草魂」ですが、かわいそうですが抜いてしまいます。 【生指】6/14 ジュニア奉仕団支援 写真館(1)  たくさんの団員(生徒)が集まってくれました。 担当の先生から、活動内容のお話しがありました。 みんな真剣に聞いています! 【生指】6/14 ジュニア奉仕団支援   団員のたくさんの生徒、PTAからは5人の生徒指導委員さん、ジュニア奉仕団の世話人の方々、学校からも担当の先生方が参加して、みんなで力を合わせて活動しました。 花植え、学校の外周のゴミ拾いと草取り(北側と南側)、イングリッシュガーデンの草取り、とそれぞれの担当に分かれて、汗を流しながら、子どもたちと一緒にがんばりました。 皆さんのおかげで、とてもきれいになりました! 暑い中でしたが、ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました! (コメント: 生徒指導委員 Iさん) 【生指】6/10 登校指導   朝の登校時間に、先生方と一緒に通学路に立ち、登校してくる生徒たちに 「おはようございます!」 と元気に声をかけます。 今回は、次の3ヶ所で行いました ・ 小牧1丁目交差点東交差点(写真上) ・ 山北橋(写真中) ・ 小牧5丁目交差点(写真下) まだ眠そうな表情の子、友達と楽しくおしゃべりしながら歩いている子、どの子もみんな元気よく「おはようございます」のあいさつを返してくれました。 生徒の通学時間帯は、朝の通勤時間帯と重なります。 車道と歩道の幅が狭く、ヒヤヒヤする場面も多くありました。 先生や保護者が見ていないところでも、交通ルールをしっかり守って、安全に登校してほしいと思います。 朝のお忙しい時間にご協力いただいた生徒指導委員会の当番の皆さん、先生方、ありがとうございました。 【コーラス】6/8 活動報告   今回も、眉を上げ、頬を上げ、口を縦に開け、「私はオペラ歌手よ!」と言い聞かせながら、堂々と声を出し、発声練習をしました。 発声練習は、とても大切だそうで、みっちりとやりました。 残りの40分くらいは、「アメイジング・グレイス」と「いのちの歌」の練習をしました。 一生懸命に声を出して、終わったあとは、とてもさわやかな気持ちになります。 興味のある方、いつでも見学、飛び入り参加OKです。 お待ちしています! 【教養】6/4 PTA社会見学 写真館(5)   昼食のあとは、園内の散策。 おみやげをたくさん持っている人、多数。 お母さんは、子どもにおいしいものを食べさせてあげたいんですよね〜 楽しい一日を、ありがとうございました! 【教養】6/4 PTA社会見学 写真館(4)   お待ちかねの昼食! ランチバイキングは、種類もいっぱい。何にしようかな〜 楽しいおしゃべりとともに、お腹もいっぱいになりました。 【教養】6/4 PTA社会見学 写真館(3)   「絵付け体験」 皆さん、真剣です。絵付けに使うのは「釉薬」といって、絵の具とは使い勝手がまるで違うので、けっこう難しいのです。 【教養】6/4 PTA社会見学 写真館(2)  「信楽焼」といえば、やっぱり「たぬき」 「たぬき」は、「たをぬく」(他を抜く)といって、とっても縁起がいいのだそうです。 【教養】6/4 PTA社会見学 写真館(1)   「信楽村」に到着後、信楽焼の説明をお聞きしました。 【教養】6/4 PTA社会見学 3年生は修学旅行中、1・2年生はフレンドシップデーの中、お母さんたちも、存分に遠足を楽しみました。 お天気が心配されましたが、雨に降られることもなく、涼しい風に吹かれながらの一日となりました。 取材をしてくださった広報委員さんのコメントをご紹介します。 ********** 6/4(水)PTA社会見学に行きました。 滋賀県の「信楽陶芸村」で、湯呑みかお皿のどちらかを選んで、自由に絵付け体験をしました。 信楽は、昔、火鉢の生産が盛んで、全国シェア9割以上を作っていましたが、ストーブの普及によりだんだん売れなくなり、売れ残った火鉢の底に穴を開け、植木鉢として売り出したところ、園芸ブームに乗り、ずいぶん売れたそうです。 現在でも、植木鉢の生産はされており、信楽というと「たぬき」のイメージが強いのですが、実は「たぬき」は全体の数パーセントの生産量で、「たぬき」ばかり作っているわけではない、というのは、とても意外でした。 絵付け体験のあとは、三重県の「伊賀の里 モクモク手作りファーム」へ移動し、昼食をとりました。 バイキングで、あれもこれもとたくさん食べて、お腹がいっぱいになりました。とてもおいしかったです。 ********** 絵付け体験の作品は、10月の文化祭の「PTA作品展」に出品します。 それまで楽しみにお待ちください。 教養委員の皆さんには、準備から当日の引率まで、たいへんお世話になりました。 ありがとうございました。 たくさんの保護者にご参加いただき、無事に、楽しい一日を過ごすことができました。 ご参加の皆さま、ありがとうございました。 【コーラス】5/25 活動報告 今回の参加者は5名。 少し寂しい人数ではありますが、これが横井先生の「横井マジック」にかかると、人数以上の歌声となるのです! 今回もストレッチや発声練習に、たっぷりと時間をかけました。 とにかく、歌うときは、眉間の辺りを響かせて歌を出すそうです。 歌詞を「奥さま風」に、フレーズごとに読みます。 そのあとに歌うと、先生の思っているような声に近づくようです。 息は、鼻から吸って、背中に入れ、それをお腹に回して、一度息を止める。そして、歌い出す。と、細かく言葉にして指示を出して教えて下さいました。 まだまだご報告したい練習方法がありますが、あとはぜひコーラスクラブに参加して、直接聞いてみませんか? 一緒に歌いましょう! 見学や飛び入り参加、大歓迎です。 お気軽に練習日に音楽室にお越しください。 5/29 第1回 ミニミニ講演会(2)〜校長先生編〜 【校長先生編】 校長先生は、先日学校HPに掲載された「未来の大人たちへ」でインタビューされた名備運輸の丸川靖彦さんのお話について、お話しして下さいました。 学校HPには書かれていないお話も含まれていて、深く考えさせられる、とてもよいお話でした。 ●「当たり前のことを当たり前に」 丸川さんが社長を務める名備運輸の企業理念には「当たり前のことを当たり前に行うことで信頼を築く」という言葉が掲げられています。 そして、経営方針として「笑顔」「あいさつ」「トラックをきれいに」の3つを大切にされているそうです。 正直に言って、そんなことで儲かるのか?と思った校長先生は、その質問を丸川さんにぶつけてみたそうです。 すると、丸川さんは「それで仕事がやりやすくなるんですよ」と答えられたそうです。 いつも笑顔で、元気にあいさつをしていれば、相手もよい気分になり、信頼してもらえるようになる。 そうすれば、普段なら乱雑に積まれたままの荷物を、トラックに積みやすいように整理しておいてくれたり、ときには搬入を手伝ったりしてくれる。 それは、とても仕事がやりやすくなるだけでなく、仕事が楽しくなることにつながっていく。 こちらからあいさつしても、相手からあいさつが返ってこなかったら、それは相手にあいさつが届いていなかったからだと思えばいい。 相手に届くまで、何度でもあいさつをすればいい。 「笑顔であいさつをする」 こんな当たり前のこと、と思われるでしょうか? しかし、その「当たり前のこと」を実際にやり続けるのは、案外難しいことなのです。 疲れていたり、他のことに気を取られていたりすると、いい加減なあいさつになったり、あいさつすること自体を忘れてしまうことはよくあることです。 「当たり前にできるように」するまでには、強く意識を持っていなければなりませんね。 ●きれいなトラックの効果 「トラックをきれいにする」ということを、丸川さんはある大切な方から教えられたそうです。 半信半疑のままでしたが、思い切ってトラック用の洗車機を導入したそうです。 トラックを洗うのは大変な労力がかかるので、少しでも社員さんが楽に洗車ができるようにとの配慮でした。 毎日、一日の勤務が終わると、社員さんは自分のトラックを洗車してきれいにしました。 すると、そのおかげで事故が減ったのだそうです。 自分のトラック、という愛着がわいて、安全運転を心がけるようになったからでした。 また、きれいなトラックでお客さんのところへ行くと、お客さんも気持ちがよいし、「こんなにトラックを大切にできる会社なんだ」という会社への信頼を持ってもらえるようになったそうです。 きれいなトラックで道路を走っていれば、それを見た人が「あそこの会社はしっかりしていそうだから、次はあの会社に頼もう」という気持ちになることもあるでしょう。 「きれいなトラック」は、このようにいくつもの効果をもたらしてくれたということでした。 ●子どもが夢を持てないのは、大人の責任 校長先生が「最近は、夢を持てない子どもが増えています。どうしたらいいと思いますか?」と質問すると、丸川さんは「子どもが夢を持てないのは、大人の責任ですよ」とおっしゃったそうです。 家で、お父さんやお母さんが、会社に対して、仕事に対して、文句ばかり言っていたら、それを聞かされている子どもたちが、将来に夢を持てるわけがない。 身近な大人である親の姿を、子どもはよく見ていますよ。 とても耳が痛いお話でした。 家で、ついつい仕事の愚痴をこぼすことは、誰でも経験があると思います。 たしかに、世の中は厳しいものだし、そうした現実は知っておいた方がいいということもあるとは思いますが、できれば子どもたちに「チャレンジしてみよう」と思わせるような夢を持たせたいですよね。 愚痴を言うのを我慢しなさい、ということではありません。 なにか大人が「楽しいこと」を見つけて、夢中になる姿を見せることが、大切なのかもしれませんね。 ●お父さんの会社で働きたい 丸川さんが、会社を経営されていく中で感じたことに「子どもたちに『お父さんの会社で働きたい』と思ってもらえるような会社にしたい」ということがあるそうです。 先の「子どもが夢を持てないのは、大人の責任」にあるように、家で愚痴ばかり言っているお父さんでは、子どもは夢を持てません。 しかし、お父さんがいつも楽しそうに仕事の話をしていたらどうでしょうか? きっと子どもは「仕事って楽しいんだ」と思うでしょう。 そのために、丸川さんは、会社のユニフォームを変えたそうです。トラックのデザインも変えたそうです。 社員さんが働きやすいように、その子どもたちが「お父さんの会社で働きたい」と言ってくれるように。 丸川さんが、社員さんやその家族のことをとても大切に思っていることが伝わるお話でした。 そして玉置先生に「校長先生、職員を大切にしない学校はダメだよ」とおっしゃったそうです。 校長先生の心にも、この言葉は深く刻まれたようです。 今年度、小牧中では「ゲスト道徳」を実施しています。 いろいろなゲストをお招きして、ゲストの人生観をお聞きし、子どもたちに深く「想像させる」授業です。 丸川さんにも、この「ゲスト道徳」を行っていただくことに決まったそうです。 「ゲスト道徳」は、保護者も参観できます。 ぜひ参観して、子どもたちと一緒に「想像」してみませんか? 日程などの詳細が決まりましたら、学校から案内がありますので、楽しみにお待ちください。 今回の校長先生の「ミニミニ講演会」は、校長先生自身が深く感銘を受けた様子やその校長先生の感動が、聞いている私たちにしっかり伝わってくる講演会になりました。 学校で、このようなステキなお話が聞ける幸運に感謝しています。 校長先生、ほんとうにありがとうござました! 5/29 第1回 ミニミニ講座(1)〜波多野先生編〜 今回ご登壇いただいたのは、波多野先生と玉置校長先生のお二人です。 【波多野先生編】 波多野先生は、2年1組の担任をされており、教科は国語です。男子バスケットボール部の顧問をされており、ご自身も学生時代はずっとバスケットボールをされていたそうです。 地元小牧出身の若い先生に、ご家族の話や国語の話を、たっぷりとお話しいただきました。 ●地元出身です 波多野先生は、光ヶ丘の出身です。まさに、地元っ子ですね。 身長に比例して、異常に(!)座高が高い、ということがトレードマークで、中学校に入学するときの制服の採寸のときのエピソードを話してくださいました。 制服の業者さんが、納得がいかずに「おかしいなぁ」と言いながら、何度も股下を測り直したので、子ども心に「自分は足が短いのか」と妙に納得した、とおっしゃって爆笑を誘っていました。 おそらく、ずっとコンプレックスに感じていた出来事だったでしょうが、笑いに変えてお話ができるおおらかさには、とても好感を持たれた保護者も多かったのではないでしょうか。 ●2児の父です 「とってもきれいな」奥さまと、5歳の娘さん、2歳の息子さんの4人家族だそうです。 驚いたのは、お二人のお子さんの誕生日が同じ日、それも「ミニミニ講演会」翌日の5/30だということでした。 ちゃっかり、校長先生に「ということなので、明日は早く帰らせてください」なんてお願いをされていました。 きっと楽しいお誕生日になったことと思います。 二人のお子さんは、とても口が達者で、いろいろとおもしろい発言エピソードを聞かせていただきました。 私たち中学生の保護者にとっては、遠い昔の日々を懐かしく思い出すお話で、「そんなこともあったよね」という微笑ましい気持ちになりました。 ●どうして国語を勉強するのか? 「いつも最初の授業のときに、子どもたちにこの質問をします。どうしてだと思いますか?」 「う〜ん、考えたこともなかった」という表情の皆さんに、波多野先生は、ご自分の師である先生の言葉を話されました。 「国語、というのは、国の言葉。植民地だった国は、支配されていた国の言葉が国語になっている。日本語は、2,000年以上の歴史を持つ言葉で、こんなに長い歴史を持った単一言語は非常に珍しい」 波多野先生は、その師の言葉を通じて 「日本語を学ぶことは、日本の歴史そのものを学ぶことだ」 と感じられて、その奥深さに感銘を受けたそうです。 ●国語は文化を学ぶことにもつながる 波多野先生が中学生のときに、「国語って奥が深い」と思われたエピソードを教えてくださいました。 英語の時間に、英作文を作っていたときのことです。 「懐かしい」という言葉を使って、英文を作ろうと思ったところ、どんな単語を使えばよいのかわからず、先生に質問したそうです。 すると、先生の答えは「懐かしい、という表現は、英語にはないよ」というものでした。 日本人なら誰でも持っている「懐かしい」という感覚が、英語を使う人々にはない、ということを知り、文化の違いが国語には表れているんだと感じたそうです。 言葉には、それを使う国々の「文化」までも含まれている、というお話をお聞きして、日本人として「国語」に誇りを持って、大切に使っていこう、という気持ちになりました。 たくさんの保護者の皆さんの注目を一身に受けて、とても緊張されていた波多野先生。 汗だくになりながら、一生懸命にお話される姿に、誠実な人柄がにじみ出ていました。 子どもたちの前で話すのとは勝手が違い、戸惑われたことと思いますが、保護者にとっても、波多野先生から直接お話を聞けてことはとてもよかったです。 ありがとうございました! 【特別講座】第1回特別講座で「大人の学び」(2)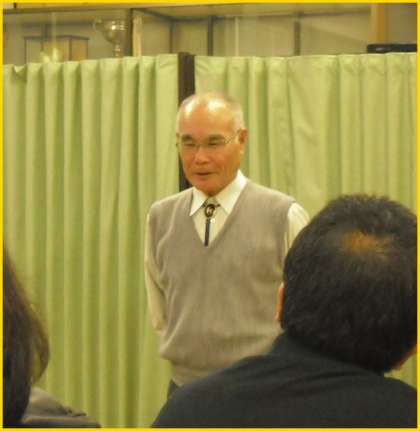 ●家族から家庭へ 角田先生は、「子どもにとって、家はガス抜きの場所。学校ではきちんとしていても、家では全然いう事を聞かなくて、というのは当たり前の話」とおっしゃいました。 昔は、三世代や四世代が同居し、仕事で忙しい親に代わって、祖父母や曽祖父母が子供の面倒を見る、ということが普通でした。 親にこっぴどく叱られた子どもは、祖父母の部屋に逃げ込んで避難し、親も子も心を落ち着かることができました。 また、物事には順序があり、老いた者はやがて亡くなります。 大家族の中で、「身近な大人の死」を経験していくことは、子どもにとって「死」を理解する大切な機会でした。 しかし、今では核家族の方が圧倒的に多くなりました。 角田先生は「家族から家庭の時代になった」とおっしゃいました。 「家庭の時代」は、子どもから、つらいときには安心して逃げ込める「心のふるさと」と、「死を理解する機会」を奪ってしまったのかもしれません。 ●親と子のコミュニケーション 角田先生が一冊の本を紹介してくださいました。 松山三四六さんが書かれた「クマンバチと手の中のキャンディ」という本です。 著者の松山さんは、柔道でオリンピックを目指していましたが、度重なるけがのため柔道選手の道を諦め、現在はラジオのパーソナリティや歌手活動をされながら、全国の小中高校を回り、講演活動をされています。 ご自身の半生から、子どもたちへ強いメッセージを送り続けておられます。 そして、松山さんは、子どもたちだけでなく、私たち親に対しても本の中でメッセージを書かれています。 その一節を紹介されながら、角田先生は、私たちに「コミュニケーション」について教えて下さいました。 文中に「向き合うか、背中を見せるか」と書かれています。 角田先生は 「子どもに媚を売るな。ありのままの自分を見せればよい」 「真剣に生きることが大切。自然のままに生きればよい」 とおっしゃいました。 「向き合う」ことばかりにこだわらず、「背中を見せる」ことも必要なことなのですね。 「コミュニケーション」とは、「人間関係調整能力」で、これは子どものうちに培うもの。 なんでも子どもの要求を受け入れることではなく、いいことも悪いことも、たくさん経験して、自分で身に付けていくもの。 自己主張ばかりではなく、他の主張も聞きながら、さりげなく自分の意見も伝えていける力がコミュニケーション力(りょく)。 角田先生から教えていただきました。 私たちは「子どものため」と思って、先走りしがちです。 それは「実は子どものためになっていないのかもしれない」と一度立ち止まって、自分自身を振り返る時間を、角田先生にいただきました。 大人たちも、子どもたちに負けないように、さまざまに学びながら「コミュニケーション力(りょく)」を磨いていきたいものですね。 今回も、角田先生から、たくさんの学びをいただきました。 ご無理をお願いしましたが、快く講座を引き受けていただいたことに、心から感謝いたします。 角田先生、本当にありがとうござました。 また、ご参加いただいた保護者の皆さま、先生方にも、お礼を申し上げます。 ありがとうございました。 次回も、よろしくお願いいたします。 【関連記事】 ●文屋e-田園ネット 「クマンバチと手の中のキャンディ」  【特別講座】第1回特別講座で「大人の学び」(1) 講師は、昨年度の第1回でもご登壇いただいた角田明先生です。 今回も、角田先生から、「親として子どもとどう接するべきか」ということを「コミュニケーション」の意味と合わせて、教えていただきました。 印象に残ったいくつかを、ご紹介します。 ●「子どもをほめる」で感じる違い 「とてもご立派なお子さんですね」 こう言われて、うれしくない親はいません。お世辞だとわかっていても、親にとっては、わが子をほめられるのは、とてもうれしいことですね。 一方、学校の先生はどうでしょうか? 「とても立派な生徒さんですね」 こう言われた先生は、ちょっとガッカリしてしまうそうです。 それは、先生としてのプライドが傷つくからだそうです。 同じように「子どもをほめる」という場面で、このように感じ方の違いがあるのはおもしろい見方ですね。 親は、子どもをほめられることで、自分がほめられたような気持ちになります。「立派な子どもを育てたのは私」と思うことで、自分が認められた思いを持つのですね。 それは、普段どれだけ育児をがんばっても、家事をがんばっても、なかなか評価されないお母さんにとっては、本当にうれしいことでしょう。 しかし、「ほめられる子ども」に仕立て上げることが、「育てる」ということではない、と角田先生から教えていただきました。 ●「きれいごと」ばかり 聞き分けのよい子どもは、はたから見れば「よい子」に見えます。 親はすぐに子どもに「何が食べたい?」「何がしたい?」「どこへ行きたい?」と、なんでも子どもに聞きます。 子どもの要求に応えていれば、子どもは駄々をこねることはありませんから、「聞き分けのよい子」に見えますね。 私たち親は、このように「子どもに気付かされる」「子どもから学ぶ」といって、子どもの意見を聞いているつもりでいます。 「それはおかしい。『大人が子どもに教える』のだ」と角田先生はおっしゃいました。 「みんな、きれいごとばかり。どうして子どもにやりたいことを聞くのか」と角田先生に問われ、参加者からは「うーん」とため息が漏れました。 「子どもから学ぶ」という響きのよい「きれいごと」に、私たちは逃げているのかもしれません。 いつも子どものしたいようにさせることで、私たちは、子どもが学ばなくてはならない大切なこと「我慢すること」を学ぶ機会を奪っているのかもしれませんね。 ●しつけができていない子どもたち 角田先生は、退職される前、小学校の校長先生をされていました。 そこで強く思ったことは「低学年が一番大事」ということだそうです。 ですから、低学年にきちんと指導ができるベテランの先生を配置した、とおっしゃいました。 ふつう、高学年は難しい年頃に差し掛かってくるので、高学年に厳しい先生がつかれるのだろうと考えますが、角田先生が「低学年が一番大事」とおっしゃる理由は、意外なことでした。 それは、「しつけができていない」子どもが多すぎる、ということでした。 「席に座る」「先生の話を聞く」「給食は座って食べる」「あいさつをする」「呼ばれたら返事をする」「先生の指示に従う」といった、学校での基本的な行動がまるでできていない子どもがたくさんいるというのです。 学校での教育には限度があります。 無尽蔵に時間があるわけではありません。 角田先生は、そうした基本的な行動は、「学校で教えるようなことではなく、家庭のしつけで教えることだ」とおっしゃいました。 そうしたことを「家庭でのしつけ」と理解している親が、少なくなってきているのかもしれません。 ですから、角田先生は在任中に「親塾」を開いて、親に対して「教育」をされてきたのでしょう。 学校は、親も教育しなければいけない時代なのですね。 皆さんは、どうお考えになりますか? 【総務】5/29 第1回 ミニミニ講演会 今回のゲストは、2年生担任の波多野先生と、校長先生でした。 「ミニミニ講演会」が始まる前に、会場の多目的ホールは満員御礼となり、椅子が足りなくなるほどの盛況ぶりでした。 ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。 波多野先生は、ご家族の話と担当教科である国語のお話を、ユーモアたっぷりに語っていただき、誠実な人柄が伝わる講演となりました。 校長先生は、先日インタビューされた「未来の大人たちへ」の続きのお話をしてくださいました。 「ABCDの原則」は、社会でも求められる、大切な資質だ、ということを教えていただきました。 お二人のお話のまとめは、後日「PTAの部屋」にアップする予定ですので、お楽しみに! 波多野先生、校長先生、楽しいお話をありがとうございました。 【保健】5/29 第1回 リサイクル販売 早くから足を運んでくださり、開場前から並んでいただいた方がたくさんいらっしゃいました。 お目当ての「牧中グッズ」がありましたでしょうか? 次回も、ぜひご利用ください。 担当の保健委員の皆さま、ありがとうございました。 なお、今回も、生徒昇降口に「リサイクル品回収ボックス」を設置していただき、多数のリサイクル品をお預かりしました。 ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。  【総務】5/29 第1回 PTAサロン 今年度も、多目的ホールを区切って、「PTAサロン」と「リサイクル販売」を同時開催しました。 「リサイクル販売」を覗いてから、サロンに寄ってくださる方も多くいらっしゃり、ゆっくり座って、お茶を飲みながら、授業参観までの時間を、楽しく過ごしていただけたようです。 また、授業参観中も開催しており、その間も多数の方にご利用いただきました。 今回は、授業参観後に「部活動懇談会」があり、懇談会開始まで、少し時間が空いてしまうため、その待ち時間にご利用いただけるように、PTAサロンの開催時間を延長しました。 ご利用いただいた皆さま、ありがとうございました。 準備から片付けまで、また受付などのお手伝いをしてくださった総務委員の皆さま、ありがとうございました。 |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
|||||||||||||